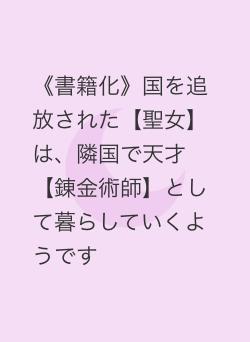目の前に集まったのは数名の衛生兵。
いずれも回復魔法の担い手となることを期待され、戦線に送られてきた女性たちだ。
しかし、話によるとここに着いた時に行われた簡単な訓練の結果、回復魔法を覚えられなかった者はそのままにされてしまっているらしい。
私はその話に憤りを感じながらも、無駄な時間など一秒もないため、胸の中にしまって、今は自分のすべきことをすることを決めた。
「それじゃあ、まずは初歩の初歩、魔力操作についてやるわね」
私が教える側なので、並んで女性たちに向かい合わせで立ち、みんなの顔に向かってそう言う。
しかし、誰もがなんのことだか分からないような顔をして、互いに顔を見合わせている。
「どうしたの? 回復魔法について一応とはいえ、習ったのでしょう? それなら魔力操作は知っているはずよね?」
私がそう言うが、やはり誰もが分からないと首を横にふった。
そして、その中の一人がおずおずと手を挙げる。
明るめの赤茶色の緩やかなカーブを持つ長髪の女性は、深い藍色の瞳で私を探るように見ながら口を開いた。
「すいません。聖女様。私たちみたいな者のためにせっかく時間を使っていただいているのに。あの……魔力操作って……なんでしょうか?」
「まぁ! 魔力操作の概念を知らずに回復魔法を使わせようとするだなんて! それじゃあ、ほとんどの人ができずに終わるはずだわ‼」
私はその質問と、今のみんなの態度で、何故学べば多くの人ができるはずの初歩の回復魔法すら使えないのか合点がいった。
回復魔法を使える一般人はほぼいないと言っていいが、それは単に学ぶ機会がなかっただけで、能力が足りないわけではない。
まがりなりにも学んだのに、使えない者が多くいる理由。
それは単に教える側の問題だったのだ。
「貴方名前は?」
「すいません。デイジーと申します」
「謝る必要はないわ。デイジー。勇気を出してよく質問してくれたわね」
魔法を唱えるためには、自分の中に流れている魔力を操作できないといけない。
持っている魔力の量はそれぞれだし、使えば使っただけ増えるものだけれど、全く持っていない人はほとんどいないはずだ。
私はまずその自身の持つ魔力の操作方法を懇切丁寧に教えることにした。
得手不得手があり、やり方を学んでもできない人もいるらしいが、幸いなことに時間がかかる者はいたけれど、その場にいる全員が使えるようになった。
「これが魔力操作……なんだか身体の芯がポカポカしてきますね」
「ええ。この感覚を覚えて、暇な時には常に魔力を操作してみることをおすすめするわ。魔力は使えば使うほど鍛えられるものなのだから」
次に私は初歩の回復魔法である傷を治す魔法を教え始める。
魔力操作も初めて学んだような相手に、少し急がせている気もするけれど、ここの状況を考えれば悠長なことは言っていられない。
まずはここにいる全員が最低限、回復魔法を使えるようになってもらわなくては。
今はたまたま重篤な人が少ないけれど、負傷兵は今こうしている間にも生まれている。
回復魔法を使うのは体力を著しく消耗するし、魔力だって使えば無くなる。
今のままでは、いつか崩壊しまた以前のように死者が大勢出るだろう。
そうならないように今のうちにできる限りの準備はしなくてければ。
「デイジー。あなた、筋がいいわね。十分に魔力を操作できているし、回復魔法もできているわ」
「ありがとうございます‼ 聖女様のおかげです! 前に習った時はこんなに分かりやすくなかったですし……」
五つあるという衛生兵部隊のここの様子を見れば、他の部隊も同じようなものだろう。
私が新しく配属されてくる新人も含めて、全員に都度指導をするというのも無理がある。
しかるべき時期に教育機関を作らねばならないと私は胸に刻む。
やがて、デイジーを筆頭に数人が回復魔法を習得した。
残念ながら今日はこの場の全員が習得というわけにはいかなかった。
またの機会を作って指導を続けるとして、回復魔法が使えない人はまだたくさん居るのだ。
交代で時間を作っている以上、一人につきっきりになるわけにもいかない。
衛生兵たちに回復魔法の指導を始めてからしばらく経った。
試行錯誤しながら、いくつかのチームに分け、一つのチームを私が指導、残りのチームで治療に当たるというの体制をとっていた。
「聖女様‼ 毒に侵された兵が複数名運ばれています! どうか、お願いします‼」
しかし、まだ解毒までできるようになった者はおらず、こうやって指導を中断されるのもしばしばだった。
「分かったわ。今行く!」
私は呼びに来た者の後に続き治療場へと急ぐ。
みると腕や脚を腫れ上がられた兵士たちが、何人も治療場に並べられていた。
患部を確認すると、ポイズントードという魔獣から受けた毒らしい。
「これなら初級の解毒魔法でできるわね」
そう言いながら、私は次々と魔法を唱えて行く。
すると、隣でそれを見ていたデイジーがおずおずと申し出てきた。
「あの……聖女様。もし良かったら、私にやらせてもらえませんか?」
「どういうこと? あなたにはまだ解毒魔法を教えていないはずだけれど」
最初から回復魔法を使えた人たちは、教えなくても魔力操作を感覚的に行うことのできた人たちで、上達も他の人より早かった。
その人たちに混じって、デイジーも他の人よりも上級な回復魔法の指導を受けていたのは知っている。
デイジーは私の指導を、水を吸う乾いた土のように吸収し、そして水を得た魚のように巧みに使った。
しかし、そもそもそのチームにすらまだ解毒魔法は教えてすらいないのだ。
それは先により上級の傷を癒す魔法を習得してもらった方が良いと考えたからでもある。
つまり、デイジーが解毒魔法を使えるはずはない。
「あの……聖女様の魔法を横で何度も見ていて、覚えました。私……きっとできます!」
「なんてこと……分かったわ。何事もやらせてみないと上達しない。そして、私はあなたを信じるわ」
目の前の負傷兵はそのやり取りを少し不安げに見ていた。
おそらく私が治療をすると思っていたところに、初めてだと分かるデイジーが代わったことが不安なのだろう。
「大丈夫よ。失敗しても今より悪くなることはないわ。もし失敗しても私がきちんと治してあげる。ただ、この子の成長に、少しだけ協力してちょうだい?」
「分かりました……お願いします!」
そう言うと負傷兵は目をつぶる。
場所を譲ると、デイジーはゆっくりと丁寧に、解毒の魔法を使い始めた。
淡い白い光がデイジーの手の平に現れる。
そしてそれを毒に侵された患部に当て、魔法を唱えた。
力強い言葉の後に、負傷兵の腕が一瞬輝きを放つ。
光が収まると、紫色に腫れ上がっていた腕は、もとの色と太さに戻っていた。
「やったわね。ちゃんとできたじゃない」
「やった……やりました! 聖女様! 私できましたよ‼」
喜ぶデイジーに優しく微笑みかける。
何故かデイジーは私の顔を見て頬を紅潮させた。
「ありがとう。助かりましたよ。凄いですね。聖女様も、デイジーさんも」
「ええ。ここ自慢の衛生兵よ」
腕の毒の治療を終えお礼を述べた兵士に、私は笑顔でそう答えた。
いずれも回復魔法の担い手となることを期待され、戦線に送られてきた女性たちだ。
しかし、話によるとここに着いた時に行われた簡単な訓練の結果、回復魔法を覚えられなかった者はそのままにされてしまっているらしい。
私はその話に憤りを感じながらも、無駄な時間など一秒もないため、胸の中にしまって、今は自分のすべきことをすることを決めた。
「それじゃあ、まずは初歩の初歩、魔力操作についてやるわね」
私が教える側なので、並んで女性たちに向かい合わせで立ち、みんなの顔に向かってそう言う。
しかし、誰もがなんのことだか分からないような顔をして、互いに顔を見合わせている。
「どうしたの? 回復魔法について一応とはいえ、習ったのでしょう? それなら魔力操作は知っているはずよね?」
私がそう言うが、やはり誰もが分からないと首を横にふった。
そして、その中の一人がおずおずと手を挙げる。
明るめの赤茶色の緩やかなカーブを持つ長髪の女性は、深い藍色の瞳で私を探るように見ながら口を開いた。
「すいません。聖女様。私たちみたいな者のためにせっかく時間を使っていただいているのに。あの……魔力操作って……なんでしょうか?」
「まぁ! 魔力操作の概念を知らずに回復魔法を使わせようとするだなんて! それじゃあ、ほとんどの人ができずに終わるはずだわ‼」
私はその質問と、今のみんなの態度で、何故学べば多くの人ができるはずの初歩の回復魔法すら使えないのか合点がいった。
回復魔法を使える一般人はほぼいないと言っていいが、それは単に学ぶ機会がなかっただけで、能力が足りないわけではない。
まがりなりにも学んだのに、使えない者が多くいる理由。
それは単に教える側の問題だったのだ。
「貴方名前は?」
「すいません。デイジーと申します」
「謝る必要はないわ。デイジー。勇気を出してよく質問してくれたわね」
魔法を唱えるためには、自分の中に流れている魔力を操作できないといけない。
持っている魔力の量はそれぞれだし、使えば使っただけ増えるものだけれど、全く持っていない人はほとんどいないはずだ。
私はまずその自身の持つ魔力の操作方法を懇切丁寧に教えることにした。
得手不得手があり、やり方を学んでもできない人もいるらしいが、幸いなことに時間がかかる者はいたけれど、その場にいる全員が使えるようになった。
「これが魔力操作……なんだか身体の芯がポカポカしてきますね」
「ええ。この感覚を覚えて、暇な時には常に魔力を操作してみることをおすすめするわ。魔力は使えば使うほど鍛えられるものなのだから」
次に私は初歩の回復魔法である傷を治す魔法を教え始める。
魔力操作も初めて学んだような相手に、少し急がせている気もするけれど、ここの状況を考えれば悠長なことは言っていられない。
まずはここにいる全員が最低限、回復魔法を使えるようになってもらわなくては。
今はたまたま重篤な人が少ないけれど、負傷兵は今こうしている間にも生まれている。
回復魔法を使うのは体力を著しく消耗するし、魔力だって使えば無くなる。
今のままでは、いつか崩壊しまた以前のように死者が大勢出るだろう。
そうならないように今のうちにできる限りの準備はしなくてければ。
「デイジー。あなた、筋がいいわね。十分に魔力を操作できているし、回復魔法もできているわ」
「ありがとうございます‼ 聖女様のおかげです! 前に習った時はこんなに分かりやすくなかったですし……」
五つあるという衛生兵部隊のここの様子を見れば、他の部隊も同じようなものだろう。
私が新しく配属されてくる新人も含めて、全員に都度指導をするというのも無理がある。
しかるべき時期に教育機関を作らねばならないと私は胸に刻む。
やがて、デイジーを筆頭に数人が回復魔法を習得した。
残念ながら今日はこの場の全員が習得というわけにはいかなかった。
またの機会を作って指導を続けるとして、回復魔法が使えない人はまだたくさん居るのだ。
交代で時間を作っている以上、一人につきっきりになるわけにもいかない。
衛生兵たちに回復魔法の指導を始めてからしばらく経った。
試行錯誤しながら、いくつかのチームに分け、一つのチームを私が指導、残りのチームで治療に当たるというの体制をとっていた。
「聖女様‼ 毒に侵された兵が複数名運ばれています! どうか、お願いします‼」
しかし、まだ解毒までできるようになった者はおらず、こうやって指導を中断されるのもしばしばだった。
「分かったわ。今行く!」
私は呼びに来た者の後に続き治療場へと急ぐ。
みると腕や脚を腫れ上がられた兵士たちが、何人も治療場に並べられていた。
患部を確認すると、ポイズントードという魔獣から受けた毒らしい。
「これなら初級の解毒魔法でできるわね」
そう言いながら、私は次々と魔法を唱えて行く。
すると、隣でそれを見ていたデイジーがおずおずと申し出てきた。
「あの……聖女様。もし良かったら、私にやらせてもらえませんか?」
「どういうこと? あなたにはまだ解毒魔法を教えていないはずだけれど」
最初から回復魔法を使えた人たちは、教えなくても魔力操作を感覚的に行うことのできた人たちで、上達も他の人より早かった。
その人たちに混じって、デイジーも他の人よりも上級な回復魔法の指導を受けていたのは知っている。
デイジーは私の指導を、水を吸う乾いた土のように吸収し、そして水を得た魚のように巧みに使った。
しかし、そもそもそのチームにすらまだ解毒魔法は教えてすらいないのだ。
それは先により上級の傷を癒す魔法を習得してもらった方が良いと考えたからでもある。
つまり、デイジーが解毒魔法を使えるはずはない。
「あの……聖女様の魔法を横で何度も見ていて、覚えました。私……きっとできます!」
「なんてこと……分かったわ。何事もやらせてみないと上達しない。そして、私はあなたを信じるわ」
目の前の負傷兵はそのやり取りを少し不安げに見ていた。
おそらく私が治療をすると思っていたところに、初めてだと分かるデイジーが代わったことが不安なのだろう。
「大丈夫よ。失敗しても今より悪くなることはないわ。もし失敗しても私がきちんと治してあげる。ただ、この子の成長に、少しだけ協力してちょうだい?」
「分かりました……お願いします!」
そう言うと負傷兵は目をつぶる。
場所を譲ると、デイジーはゆっくりと丁寧に、解毒の魔法を使い始めた。
淡い白い光がデイジーの手の平に現れる。
そしてそれを毒に侵された患部に当て、魔法を唱えた。
力強い言葉の後に、負傷兵の腕が一瞬輝きを放つ。
光が収まると、紫色に腫れ上がっていた腕は、もとの色と太さに戻っていた。
「やったわね。ちゃんとできたじゃない」
「やった……やりました! 聖女様! 私できましたよ‼」
喜ぶデイジーに優しく微笑みかける。
何故かデイジーは私の顔を見て頬を紅潮させた。
「ありがとう。助かりましたよ。凄いですね。聖女様も、デイジーさんも」
「ええ。ここ自慢の衛生兵よ」
腕の毒の治療を終えお礼を述べた兵士に、私は笑顔でそう答えた。