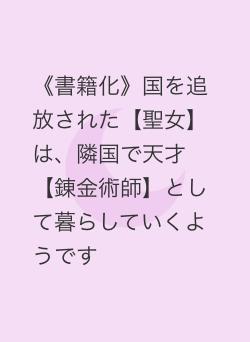デイジーの言葉を受け、私はもう一度報告書を確認する。
能率の下がった衛生兵の多くは第二期訓練兵。
そちらにばっかり気が取られていたが、デイジーの言うように、全員ではないものの、第二期衛生兵でない者も含め、そのほとんどがカルザーが査察にきた際に休憩を取っていた者だった。
私は一度ため息を吐いてからデイジーの方に目線を上げる。
「それにしても、衛生兵の休憩時間なんて、毎日それぞれ違うのに、よく気付いたわね」
「えへへ……穴が開くほど資料を眺めましたから」
そういうデイジーの目の下には薄くない隈ができていた。
恐らく治療の合間、わずかな休憩時間を使って、調べてくれたのだろう。
「ありがとう。デイジー。これがどういう意味を持つのかはまだ分からないけれど、糸口は掴めたわ。カルザーがあの日、私を伴わずに休憩室に行っているはずなの。その時に何があったのかもしれないわね」
「うーん。でも、何があったか知らないですけど、該当する衛生兵たちには既に聴き込み済みですよ? 今さら聞いたって、新しい情報が出てくるとは思えませんが……」
デイジーは顎に右手の指を当て、思案するような素振りを見せる。
それに向かって、私は笑顔で答えた。
「本人に聞いても無駄でしょうね。明らかにカルザーに何か吹き込まれ、それを実践している。当然、口止めもそれとなく言われているはずよ。でも……」
「でも……?」
「その日休憩室にいたはずなのに、能率が落ちてない訓練兵もいるでしょう? 彼女たちに聞けば、何かが分かるかもしれないわね」
「あ! なるほど‼︎ さっそく、確認してみます!」
デイジーは華やかに目を輝かせ、私が指令を出すより先に、隊長室を飛び出していった。
私は苦笑しながらその後ろ姿を扉が閉まるまで眺める。
「ふふ……デイジーの元気さには、いつもこちらが元気づけられるわね。それにしてもカルザー長官。衛生兵たちに何を吹き込んだのかしら……」
その真相が判明するのは、その日の夜のことだった。
☆
「デイジー。分かったことがあるって、随分と早いわね?」
「ええ! 聖女様。早速見つけましたよ! カルザー長官があの日、何を言ったのか知っていて、教えてくれる人物を」
デイジーは一人の衛生兵を伴って隊長室に入ってきた。
明らかに緊張している素振りを見せる衛生兵に、私は優しく声を変えた。
「そんなに緊張しないでちょうだい。あなたが、これから何を言ったとしても、この部隊で罰せられることはないわ。安心して。確か……エリカだったわね?」
「は、はい! 私なんかの名前を覚えてくださっていたんですね! 光栄です!」
両手を自分の腰の前でぎゅっと握りしめ、腕だけじゃなく肩にまで力が入っていそうなエリカに、デイジーが優しく肩に手を乗せる。
そして、とびっきりの笑顔を作って、エリカに声をかけた。
「聖女様の言っていることは本当よ。聖女様は今までに一度だって嘘や偽り言ったことがないのよ? 聖女様が大丈夫って言ったら、絶対大丈夫なんだから」
「は、はい……分かりました。すいません……」
デイジーの笑顔は見る者に安らぎを与える効果があると私は前々から思っていたが、果たしてその効果は絶大のようだ。
固まって仮面のような顔をしていたエリカの顔に、ようやく表情らしい表情が生まれた。
「ありがとうデイジー。それで。何を知っているのか、説明してちょうだい」
「はい……あの日、私たちが休憩室で休憩していたところ、ご存知のようにカルザー長官がお見えになりました――」
☆☆☆
――あの日のこと。エリカの追憶――
エリカはその日、いつものように休憩室で同僚たちと、普段のキツい任務のストレスを少しでも和らげようと、故郷や家族、そしてまだ見ぬ恋の話などに花を咲かせていた。
すると突然、衛生兵部隊を統括する長官の立場の老人が、休憩室に訪れた。
カルザーと名乗ったその老人が胸に付けた勲章や徽章、そして後に控える数名の兵士たち。
それらのことから、休憩室にいた者で、カルザーの立場を疑う者など一人もいなかった。
「やぁ。休憩中に失礼するよ。ああ、そんなに畏まらなくていい」
柔和な笑みを浮かべるカルザーの言葉は、どこか薄ら寒く、誰もするはずもないが、言葉通りに受け取って少しでも無礼を働けば、命に危険が及ぶとエリカは感じていた。
それほどまでに、自分と同じくらいの小柄な体躯を持ち、白髪の老人は、見えない奇妙な威圧感に満ち溢れていた。
「僕はね。感心しているんだ。君たちにね。僕が言うのもなんだけれど、ここは酷い所だ。魔族や魔獣との戦争の最前線。多くの兵士が戦い、そして命を落としていく」
突然語り始めたカルザーにエリカは、目を、耳を、そらすことができずにいた。
人に自分の言葉を傾聴させる、そんな不思議な力をこの小さな老人が持っているのではないかとまで、エリカは思った。
「君たちも善戦してくれているおかげで、前よりもずっと死者は減った。これについては僕から心から礼を言おう。ありがとう」
カルザーの言葉一つ一つが、エリカの心に侵食してくる。
「ありがとう」という言葉さえ、言われたこちらが、言ってもらって感謝の念を持たないといけないような錯覚まで感じた。
「本当に君たちには頭が下がる。君たちはすでに十分な回復魔法を使える。それなのに! さらに高等な魔法を習得しようと、日々訓練に明け暮れているようだね。その上、毎日の任務にも勤勉だ」
ここまで来て、エリカは周囲に目を配った。
カルザーの言葉に何か裏がありそうだと、初めから警戒して聞いていたエリカに比べ、他の衛生兵は恍惚の表情をしていた。
それはまるで、天上の神から、自分自身の行いの正しさを褒められているような者の表情だった。
確かに一般兵から見れば、部隊長のさらに上、長官など、こうやって近くに寄ることもできない存在だ。
その天上の存在が、自分を、自分自身の行いを称賛している。
エリカは、自分がむしろひねくれた考えに囚われているのではないかと、反省しそうになった。
しかし、その次の瞬間。
エリカは自分の直感が間違っていなかったことを確信した。
「そんな滅私の精神を持つ君たちは、この戦争のさぞ尊い犠牲になってくれることだろう」
カルザーがそう言った後、一瞬の間があった。
まるで、衛生兵たちがカルザーの言った言葉をきちんと理解する時間を作るために、わざと空けられた時間にも思えた。
「本来の衛生兵ってのは後衛に控えるもんなんだけど? そりゃそうだ。なんの戦闘能力も持たない衛生兵が危険な前線なんかに来たら危険だからね」
ここからはカルザーの言葉は矢継ぎ早に放たれた。
まるで思考を持つことを許さないように。
「この部隊は特殊なんだよ。しかし優秀な衛生兵ならその困難にも打ち勝てるはずだ。多くの犠牲は伴うだろうけどね。任務の手際が悪く、訓練も疎かにするような衛生兵なら、すぐに別部隊に移されたり、除名されたりするだろう」
そこでカルザーは人差し指を顔の前に立て、少し顔を傾けた。
「君たちは知っているかい? 初級の治癒の魔法でも使えれば、貴族たちから引く手数多だ。一生安泰が保証されるだろう。それなのに国のため、軍のため、自分の身を危険な戦地に置くことを選択してくれたんだ。涙が出るよ」
カルザーはわざとらしく立てた指で濡れてなどいない、右目を拭く素振りを見せた。
「さて……それじゃあ、僕はそろそろ行くよ。ああそれと……今度、君たちには攻撃部隊に同行して現場に向かってもらうことになると思う。きっと優秀な者から選ばれていくことだろう。よろしく頼むよ」
カルザーは最後に含みを持たせた言葉を残し、休憩室から立ち去っていった。
後に残された衛生兵たちは、みな、動揺の色を隠せずに、互いの顔色を窺っていた。
能率の下がった衛生兵の多くは第二期訓練兵。
そちらにばっかり気が取られていたが、デイジーの言うように、全員ではないものの、第二期衛生兵でない者も含め、そのほとんどがカルザーが査察にきた際に休憩を取っていた者だった。
私は一度ため息を吐いてからデイジーの方に目線を上げる。
「それにしても、衛生兵の休憩時間なんて、毎日それぞれ違うのに、よく気付いたわね」
「えへへ……穴が開くほど資料を眺めましたから」
そういうデイジーの目の下には薄くない隈ができていた。
恐らく治療の合間、わずかな休憩時間を使って、調べてくれたのだろう。
「ありがとう。デイジー。これがどういう意味を持つのかはまだ分からないけれど、糸口は掴めたわ。カルザーがあの日、私を伴わずに休憩室に行っているはずなの。その時に何があったのかもしれないわね」
「うーん。でも、何があったか知らないですけど、該当する衛生兵たちには既に聴き込み済みですよ? 今さら聞いたって、新しい情報が出てくるとは思えませんが……」
デイジーは顎に右手の指を当て、思案するような素振りを見せる。
それに向かって、私は笑顔で答えた。
「本人に聞いても無駄でしょうね。明らかにカルザーに何か吹き込まれ、それを実践している。当然、口止めもそれとなく言われているはずよ。でも……」
「でも……?」
「その日休憩室にいたはずなのに、能率が落ちてない訓練兵もいるでしょう? 彼女たちに聞けば、何かが分かるかもしれないわね」
「あ! なるほど‼︎ さっそく、確認してみます!」
デイジーは華やかに目を輝かせ、私が指令を出すより先に、隊長室を飛び出していった。
私は苦笑しながらその後ろ姿を扉が閉まるまで眺める。
「ふふ……デイジーの元気さには、いつもこちらが元気づけられるわね。それにしてもカルザー長官。衛生兵たちに何を吹き込んだのかしら……」
その真相が判明するのは、その日の夜のことだった。
☆
「デイジー。分かったことがあるって、随分と早いわね?」
「ええ! 聖女様。早速見つけましたよ! カルザー長官があの日、何を言ったのか知っていて、教えてくれる人物を」
デイジーは一人の衛生兵を伴って隊長室に入ってきた。
明らかに緊張している素振りを見せる衛生兵に、私は優しく声を変えた。
「そんなに緊張しないでちょうだい。あなたが、これから何を言ったとしても、この部隊で罰せられることはないわ。安心して。確か……エリカだったわね?」
「は、はい! 私なんかの名前を覚えてくださっていたんですね! 光栄です!」
両手を自分の腰の前でぎゅっと握りしめ、腕だけじゃなく肩にまで力が入っていそうなエリカに、デイジーが優しく肩に手を乗せる。
そして、とびっきりの笑顔を作って、エリカに声をかけた。
「聖女様の言っていることは本当よ。聖女様は今までに一度だって嘘や偽り言ったことがないのよ? 聖女様が大丈夫って言ったら、絶対大丈夫なんだから」
「は、はい……分かりました。すいません……」
デイジーの笑顔は見る者に安らぎを与える効果があると私は前々から思っていたが、果たしてその効果は絶大のようだ。
固まって仮面のような顔をしていたエリカの顔に、ようやく表情らしい表情が生まれた。
「ありがとうデイジー。それで。何を知っているのか、説明してちょうだい」
「はい……あの日、私たちが休憩室で休憩していたところ、ご存知のようにカルザー長官がお見えになりました――」
☆☆☆
――あの日のこと。エリカの追憶――
エリカはその日、いつものように休憩室で同僚たちと、普段のキツい任務のストレスを少しでも和らげようと、故郷や家族、そしてまだ見ぬ恋の話などに花を咲かせていた。
すると突然、衛生兵部隊を統括する長官の立場の老人が、休憩室に訪れた。
カルザーと名乗ったその老人が胸に付けた勲章や徽章、そして後に控える数名の兵士たち。
それらのことから、休憩室にいた者で、カルザーの立場を疑う者など一人もいなかった。
「やぁ。休憩中に失礼するよ。ああ、そんなに畏まらなくていい」
柔和な笑みを浮かべるカルザーの言葉は、どこか薄ら寒く、誰もするはずもないが、言葉通りに受け取って少しでも無礼を働けば、命に危険が及ぶとエリカは感じていた。
それほどまでに、自分と同じくらいの小柄な体躯を持ち、白髪の老人は、見えない奇妙な威圧感に満ち溢れていた。
「僕はね。感心しているんだ。君たちにね。僕が言うのもなんだけれど、ここは酷い所だ。魔族や魔獣との戦争の最前線。多くの兵士が戦い、そして命を落としていく」
突然語り始めたカルザーにエリカは、目を、耳を、そらすことができずにいた。
人に自分の言葉を傾聴させる、そんな不思議な力をこの小さな老人が持っているのではないかとまで、エリカは思った。
「君たちも善戦してくれているおかげで、前よりもずっと死者は減った。これについては僕から心から礼を言おう。ありがとう」
カルザーの言葉一つ一つが、エリカの心に侵食してくる。
「ありがとう」という言葉さえ、言われたこちらが、言ってもらって感謝の念を持たないといけないような錯覚まで感じた。
「本当に君たちには頭が下がる。君たちはすでに十分な回復魔法を使える。それなのに! さらに高等な魔法を習得しようと、日々訓練に明け暮れているようだね。その上、毎日の任務にも勤勉だ」
ここまで来て、エリカは周囲に目を配った。
カルザーの言葉に何か裏がありそうだと、初めから警戒して聞いていたエリカに比べ、他の衛生兵は恍惚の表情をしていた。
それはまるで、天上の神から、自分自身の行いの正しさを褒められているような者の表情だった。
確かに一般兵から見れば、部隊長のさらに上、長官など、こうやって近くに寄ることもできない存在だ。
その天上の存在が、自分を、自分自身の行いを称賛している。
エリカは、自分がむしろひねくれた考えに囚われているのではないかと、反省しそうになった。
しかし、その次の瞬間。
エリカは自分の直感が間違っていなかったことを確信した。
「そんな滅私の精神を持つ君たちは、この戦争のさぞ尊い犠牲になってくれることだろう」
カルザーがそう言った後、一瞬の間があった。
まるで、衛生兵たちがカルザーの言った言葉をきちんと理解する時間を作るために、わざと空けられた時間にも思えた。
「本来の衛生兵ってのは後衛に控えるもんなんだけど? そりゃそうだ。なんの戦闘能力も持たない衛生兵が危険な前線なんかに来たら危険だからね」
ここからはカルザーの言葉は矢継ぎ早に放たれた。
まるで思考を持つことを許さないように。
「この部隊は特殊なんだよ。しかし優秀な衛生兵ならその困難にも打ち勝てるはずだ。多くの犠牲は伴うだろうけどね。任務の手際が悪く、訓練も疎かにするような衛生兵なら、すぐに別部隊に移されたり、除名されたりするだろう」
そこでカルザーは人差し指を顔の前に立て、少し顔を傾けた。
「君たちは知っているかい? 初級の治癒の魔法でも使えれば、貴族たちから引く手数多だ。一生安泰が保証されるだろう。それなのに国のため、軍のため、自分の身を危険な戦地に置くことを選択してくれたんだ。涙が出るよ」
カルザーはわざとらしく立てた指で濡れてなどいない、右目を拭く素振りを見せた。
「さて……それじゃあ、僕はそろそろ行くよ。ああそれと……今度、君たちには攻撃部隊に同行して現場に向かってもらうことになると思う。きっと優秀な者から選ばれていくことだろう。よろしく頼むよ」
カルザーは最後に含みを持たせた言葉を残し、休憩室から立ち去っていった。
後に残された衛生兵たちは、みな、動揺の色を隠せずに、互いの顔色を窺っていた。