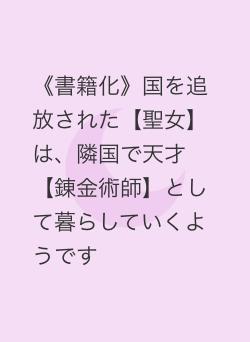「お呼びでしょうか? 部隊長」
「ええ。少し話を聞いてみたいと思ってね」
私に呼び出されたロベリアは、何事かと心配そうな様子で部屋に入ってきた。
ただでさえ新米の訓練兵と、年は近いとは言ってもその部隊の部隊長。
この若さで緊張するなというのは、無理というものだろう。
私はそんなロベリアに目を向けると、早速本題に入った。
「ロベリア。あなたは魔力操作には問題が見られない。けれど、一向に回復魔法を覚えられない。と聞いているわ。間違いない?」
「え⁉ あ、あの……それは……」
「違うの?」
「……違いません」
ロベリアの反応を見て、私は配属当初のやり取りを思い出す。
そういえば、ロベリアは回復魔法が取得できなければどうなるか、と質問をしていた。
「安心してちょうだい。まだ、帰還命令を出すまでには時間があるわ。これはあなたが回復魔法を使えるようになるために必要なことだと理解してちょうだい」
「え? あ、そうなんですね。よかったぁ。わたし、てっきり……」
「それで、魔力操作が既にできていたにも関わらず、回復魔法が使えないというのが、どうしてなのか。調べたいと思うの。いいわね?」
「はい! わたしもどうすればいいのか全然分からなくて……」
私はロベリアにまずは魔力操作を実演させてみる。
魔力操作は、身体で練った魔力を手先に持ってくることを意味する。
ロベリアは私に一度だけ返事をすると、その場で目をつぶり、魔力を練り上げ始めた。
魔力の総量自体も人それそれだけれど、いかに効率良く練り上げられるかも、回復魔法を使うには重要になってくる。
しかしその感覚は本人しか分からず、次の手先に持ってくるという行為を通してからしか、できているのかどうかは他人には分からない。
やがて、ロベリアは練り上げたであろう魔力を手先に移動させようと、右手を胸の辺りに持ち上げ、両目でしっかりと見据えた。
「出来ました」
「分かったわ。それじゃあ、確かめるわね」
私はロベリアの右手に自分の手を置く。
魔力の波動とそれに応じた熱を感じ、確かにロベリアは魔力操作はできていることが確認できた。
しかし、量が少ないこともあるけれど、それ以外にも何か違和感を感じた私は、ロベリアに基本的なことについて質問を投げかけた。
私の考えが正しいのなら、回復魔法が使えない理由がそこにあるかもしれない。
「ロベリア。魔力操作は出来ているようだわ。ところで、基礎的な質問なのだけれど、魔力を練る時、身体のどこを意識してる?」
「えーっと、この辺りですね……」
ロベリアはそう言いながら、自分の腹部、へその下辺りを右手で撫でた。
それを見た私は、考えが正しかったと確信する。
「ロベリア、誰か。そうね。親しい人に攻撃魔法を使う人が居るかしら?」
「え⁉ なんで分かったんですか⁉ 兄が、歳の離れた兄がいます。第二攻撃部隊に所属しています」
「魔力操作は、そのお兄さんから学んだのかしら?」
「部隊長はなんでも分かるんですね。その通りです。兄は独学で攻撃魔法を学び扱えるようになった人でした。そんな兄について回っているうちに私も興味を持って……それが何か?」
私は一度息を吐く。
ロベリアが回復魔法を使えない理由はここにあるのは確定したものの、それを直すのはなかなかに骨が折れることだった。
右手を自分の胸の中心に当て、私はロベリアが絶望しないように言葉を選んで説明を始めた。
「実はね、ロベリア。男性が得意な攻撃魔法。そして女性が得意な回復魔法。どちらも魔力操作を伴うのだけれど」
「はい」
「あなたが魔力を練っている場所。それは攻撃魔法を使うための場所なの。回復魔法はここで練るのよ」
「え⁉」
そう言いながら私は右手で胸を軽く叩く。
それを見たロベリアは驚きのあまり目を見開いている。
「回復魔法はね、心で魔力を練るの。言葉では上手く説明が難しいけれど、普通の人は考えずにそうしているのよ」
「それじゃあ、私はどうすれば?」
「あなたが回復魔法を使えない理由は、魔力の質が違うから。攻撃を目的とした魔力と、回復を目的とした魔力とでは質が全く違うの」
私の説明を聞きながら、ロベリアは困惑した表情をこちらに向ける。
それを見た私は悲しい気持ちになる。
魔力を練る感覚は、人によって違う。
そして、それは他人が教えて分かるものではないのだ。
一度癖としてついてしまったことを忘れて、別の方法を正しく身につけるのは、新しく始めるよりはるかに難易度の高いことだった。
正直なところ、私も書物で知識として知ってはいるものの、実際にへその下で魔力を練ってみろと言われても、実現することはできない。
「心苦しいけれど、ロベリア。あなたが、魔力の練り方を自力で直さなければ、あなたは一生回復魔法を使うことはできないわ」
「そんな! それは、困ります……私、衛生兵になって、兄を……アイオラにもしものことがあれば助けたい一心で!」
ロベリアはこの戦場に赴くには若いとは思っていたが、なるほど、どうやら志願兵だったようだ。
できるかどうかも定かではないのに、衛生兵を志願したということは、よほど兄が心配なのだろう。
しかし、私にできるのはここまでだ。
あとは、自分で魔力の練り方を直すしか方法はない。
「冷たいことを言うようだけれど、ロベリア。間違っていることは教えられても、どうすれば正しい方法で出来るのかは、あなたにしか分からないわ」
「はい……」
「そうね……今日から、治療場での業務は休止しなさい。そして、どうすれば魔力の練り方を変えられるか、それを試行錯誤しなさい」
「分かりました……でも、どうやったら違いが分かるんですか?」
聞かれて私は頭を回転させた。
私も違和感を感じただけで、魔力に触れたとしても、正確にどちらの魔力の質なのかまでは自信がない。
「そうね。実際に回復魔法を使ってみるしかないでしょうね。出来るようになったと思ったら、治療場に顔を出しなさい。実際に負傷兵に回復魔法をかけて確認する他ないわ」
「分かりました。それでは……失礼します」
こうしてロベリアは間違って身に付けてしまった魔力操作を修整するために、ひたすら自己訓練にあけくれていた。
しかし、しばらく経ってもロベリアが治療場に顔を出すことはなかった。
そんなある日のこと、いつも通りひっきりなしに負傷兵が運ばれてきていた治療場に、血相を変えたロベリアが飛び込んできた。
その形相は、成功した喜びを持っているようにはとても見えない。
ロベリアは辺りを見渡した後、私を見つけて、駆けつけてくる。
そして開口一番にこう言った。
「部隊長‼ 兄が‼ アイオラがここに運ばれたって本当ですか⁉」
「ええ。少し話を聞いてみたいと思ってね」
私に呼び出されたロベリアは、何事かと心配そうな様子で部屋に入ってきた。
ただでさえ新米の訓練兵と、年は近いとは言ってもその部隊の部隊長。
この若さで緊張するなというのは、無理というものだろう。
私はそんなロベリアに目を向けると、早速本題に入った。
「ロベリア。あなたは魔力操作には問題が見られない。けれど、一向に回復魔法を覚えられない。と聞いているわ。間違いない?」
「え⁉ あ、あの……それは……」
「違うの?」
「……違いません」
ロベリアの反応を見て、私は配属当初のやり取りを思い出す。
そういえば、ロベリアは回復魔法が取得できなければどうなるか、と質問をしていた。
「安心してちょうだい。まだ、帰還命令を出すまでには時間があるわ。これはあなたが回復魔法を使えるようになるために必要なことだと理解してちょうだい」
「え? あ、そうなんですね。よかったぁ。わたし、てっきり……」
「それで、魔力操作が既にできていたにも関わらず、回復魔法が使えないというのが、どうしてなのか。調べたいと思うの。いいわね?」
「はい! わたしもどうすればいいのか全然分からなくて……」
私はロベリアにまずは魔力操作を実演させてみる。
魔力操作は、身体で練った魔力を手先に持ってくることを意味する。
ロベリアは私に一度だけ返事をすると、その場で目をつぶり、魔力を練り上げ始めた。
魔力の総量自体も人それそれだけれど、いかに効率良く練り上げられるかも、回復魔法を使うには重要になってくる。
しかしその感覚は本人しか分からず、次の手先に持ってくるという行為を通してからしか、できているのかどうかは他人には分からない。
やがて、ロベリアは練り上げたであろう魔力を手先に移動させようと、右手を胸の辺りに持ち上げ、両目でしっかりと見据えた。
「出来ました」
「分かったわ。それじゃあ、確かめるわね」
私はロベリアの右手に自分の手を置く。
魔力の波動とそれに応じた熱を感じ、確かにロベリアは魔力操作はできていることが確認できた。
しかし、量が少ないこともあるけれど、それ以外にも何か違和感を感じた私は、ロベリアに基本的なことについて質問を投げかけた。
私の考えが正しいのなら、回復魔法が使えない理由がそこにあるかもしれない。
「ロベリア。魔力操作は出来ているようだわ。ところで、基礎的な質問なのだけれど、魔力を練る時、身体のどこを意識してる?」
「えーっと、この辺りですね……」
ロベリアはそう言いながら、自分の腹部、へその下辺りを右手で撫でた。
それを見た私は、考えが正しかったと確信する。
「ロベリア、誰か。そうね。親しい人に攻撃魔法を使う人が居るかしら?」
「え⁉ なんで分かったんですか⁉ 兄が、歳の離れた兄がいます。第二攻撃部隊に所属しています」
「魔力操作は、そのお兄さんから学んだのかしら?」
「部隊長はなんでも分かるんですね。その通りです。兄は独学で攻撃魔法を学び扱えるようになった人でした。そんな兄について回っているうちに私も興味を持って……それが何か?」
私は一度息を吐く。
ロベリアが回復魔法を使えない理由はここにあるのは確定したものの、それを直すのはなかなかに骨が折れることだった。
右手を自分の胸の中心に当て、私はロベリアが絶望しないように言葉を選んで説明を始めた。
「実はね、ロベリア。男性が得意な攻撃魔法。そして女性が得意な回復魔法。どちらも魔力操作を伴うのだけれど」
「はい」
「あなたが魔力を練っている場所。それは攻撃魔法を使うための場所なの。回復魔法はここで練るのよ」
「え⁉」
そう言いながら私は右手で胸を軽く叩く。
それを見たロベリアは驚きのあまり目を見開いている。
「回復魔法はね、心で魔力を練るの。言葉では上手く説明が難しいけれど、普通の人は考えずにそうしているのよ」
「それじゃあ、私はどうすれば?」
「あなたが回復魔法を使えない理由は、魔力の質が違うから。攻撃を目的とした魔力と、回復を目的とした魔力とでは質が全く違うの」
私の説明を聞きながら、ロベリアは困惑した表情をこちらに向ける。
それを見た私は悲しい気持ちになる。
魔力を練る感覚は、人によって違う。
そして、それは他人が教えて分かるものではないのだ。
一度癖としてついてしまったことを忘れて、別の方法を正しく身につけるのは、新しく始めるよりはるかに難易度の高いことだった。
正直なところ、私も書物で知識として知ってはいるものの、実際にへその下で魔力を練ってみろと言われても、実現することはできない。
「心苦しいけれど、ロベリア。あなたが、魔力の練り方を自力で直さなければ、あなたは一生回復魔法を使うことはできないわ」
「そんな! それは、困ります……私、衛生兵になって、兄を……アイオラにもしものことがあれば助けたい一心で!」
ロベリアはこの戦場に赴くには若いとは思っていたが、なるほど、どうやら志願兵だったようだ。
できるかどうかも定かではないのに、衛生兵を志願したということは、よほど兄が心配なのだろう。
しかし、私にできるのはここまでだ。
あとは、自分で魔力の練り方を直すしか方法はない。
「冷たいことを言うようだけれど、ロベリア。間違っていることは教えられても、どうすれば正しい方法で出来るのかは、あなたにしか分からないわ」
「はい……」
「そうね……今日から、治療場での業務は休止しなさい。そして、どうすれば魔力の練り方を変えられるか、それを試行錯誤しなさい」
「分かりました……でも、どうやったら違いが分かるんですか?」
聞かれて私は頭を回転させた。
私も違和感を感じただけで、魔力に触れたとしても、正確にどちらの魔力の質なのかまでは自信がない。
「そうね。実際に回復魔法を使ってみるしかないでしょうね。出来るようになったと思ったら、治療場に顔を出しなさい。実際に負傷兵に回復魔法をかけて確認する他ないわ」
「分かりました。それでは……失礼します」
こうしてロベリアは間違って身に付けてしまった魔力操作を修整するために、ひたすら自己訓練にあけくれていた。
しかし、しばらく経ってもロベリアが治療場に顔を出すことはなかった。
そんなある日のこと、いつも通りひっきりなしに負傷兵が運ばれてきていた治療場に、血相を変えたロベリアが飛び込んできた。
その形相は、成功した喜びを持っているようにはとても見えない。
ロベリアは辺りを見渡した後、私を見つけて、駆けつけてくる。
そして開口一番にこう言った。
「部隊長‼ 兄が‼ アイオラがここに運ばれたって本当ですか⁉」