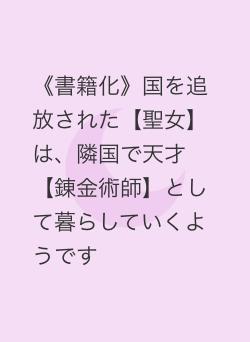「月が綺麗ですねー」
クロムと並び、陣営の中を当てもなく歩いていると、突然空を見上げたクロムがそう言い出した。
釣られて私も目線を上げると、確かに雲ひとつない夜空に、月が煌々と浮かんでいた。
「そうね。ねぇ。クロムは出身はどの辺りなの?」
無言で歩き続けるのもなんだと、思い付いた話題を口に出してみる。
私からの質問に、聞かれた本人は驚いたのか、目を見開いた。
「お、俺ですか。えっと、知っているかどうかわかりませんが、ロメル村っていう小さな村です。ここから北の方にあるマッカーブ山脈の麓にあるんです」
「あら。随分と寒い地域に住んでいたのね」
マッカーブ山脈というのは、この国の最北に連なる山脈で、一年中冠雪している山も多いと聞く。
今は辺りが暗く分かりにくいが、確かに北出身に多い、色白で透き通るような肌と、淡い青緑の瞳をしていたことが記憶から呼び起こされた。
「寒いですよ。冬は村から出ることもできないほどです。そんな暮らしが嫌で、村を飛び出したんですよ。俺」
「まぁ! それは大変だったわね。じゃあ、ここへは志願で?」
「はは。実はそうなんです。本当は街で暮らすつもりだったんですが、上手くいかなくて」
クロムはバツが悪そうに頬をかく。
そこで私は、こんな風に誰かの身の上を聞くのは初めての経験だと気付いた。
私は改めてクロムを見つめる。
それに気付いたのか、クロムは長いまつ毛が生え揃った大きな瞳を瞬かせた。
「あ、あの! 聖女様は、慕っている男性とかはいらっしゃらないんですか⁉」
一瞬の間を置いて、クロムは少し身体を強ばらせながら、上擦った声でそんなことを聞いてきた。
思わぬ質問に、私は少し考え込んでしまう。
慕っている男性というのは、どういう意味の質問だろうか。
会ったことはないが、攻撃や回復魔法の基礎となる魔力に関する著書を書いたオルマン伯爵には、尊敬の念を抱いてる。
しかし、今までの話の流れで、そんなことを聞くような話はあっただろうか。
適切な答えが分からず黙っていると、クロムは痺れを切らしたように、先ほどの自分の言葉を否定し始めた。
「ああ! 今の話は忘れてください! なんでもないんです。俺、何を聞いてるんだろ!」
「あら。そう? ごめんなさいね。いい答えが思い付かなくて――」
そういい切ろうとした瞬間、陣営の見張り台から、敵襲を知らせる合図が鳴り響いた。
私は驚き動きを止めるが、クロムはそんな私を自分の方に引き寄せ、辺りに警戒を向ける。
「聖女様! どうやら敵襲です! 早く建物の中へお戻りください‼」
「え、ええ! クロム、あなたは⁉」
「私は衛兵。この時のために私は居るのです。入口まで送りましょう。さぁ、早く‼」
クロムに手を引かれる形で、私は建物の入口へと走る。
もうすぐ入口へと辿り着くといったところで、目の前に何かが降りてきた。
私は思わず声を上げる。
目に入ったのは、黒い羽を持つ魔獣だった。
「くそっ! ガーゴイルか‼ こいつ、空を飛んで陣営の壁を越えやがった‼」
「クロム! 無理はしないで‼ 増援をっ‼」
しかし、辺りを見渡しても近くに他の兵士の姿はなく、どうにか二人だけで切り抜けなくてはいけなさそうだ。
ガーゴイルと呼ばれる、身体が石のような見た目をした魔獣は、牙が生え揃った裂けた口で威嚇の鳴き声を上げる。
次の瞬間、鋭い爪が生えた腕を突き出し、私を庇うように前に立ったクロムに向かって、身体ごと突進してきた。
しかし、クロムは動じることなく、両手で構えた剣を器用に振るって、ガーゴイルの腕を、そして羽の付け根を切り落とした。
思わぬ反撃をくらいうろたえた様子のガーゴイルを、クロムは縦一文字に切り伏せる。
初めて目の当たりにするクロムの実力に、私は目を白黒させてしまった。
「ふぅ……もう大丈夫です。さぁ、今のうちに中へ‼ 俺は、戻ります。あっちの塀の外に沢山群がって来ているようですから」
「ありがとう、クロム。助かったわ。本当に。でも無理はしないでね。死んでしまってはいくら私でも助けられないわ」
私の言葉にクロムは目を細め、そして軍式の礼をする。
「承知しました‼ 副隊長の命令、必ずや守ってみせます‼」
「ええ。そうしてちょうだい。命令違反は、しないでね」
クロムは一度頷くと、大量の魔獣が押し寄せているであろう、戦闘音が響く方へと走り出した。
私はそれを見送ると、建物の中へと入り、寝ている衛生兵を起こしながら治療場へと向かう。
「聖女様、一体何事ですか?」
今まで寝ていたのか、目を擦りながらデイジーが聞いてくる。
「敵襲よ! 前のようにここが襲われているわ。負傷兵が大量に運ばれる可能性が高いわ。心してちょうだい‼」
「わ、分かりましたぁ‼」
状況が飲み込めたのか、デイジーは一気に目が覚めたようで、治療場へと向かう足を速めた。
私は受入係に布をできるだけ速く、かつ正確に負傷兵に付ける様に指示を出した後、気を引き締め運ばれてくるであろう負傷兵を待ち構えた。
クロムと並び、陣営の中を当てもなく歩いていると、突然空を見上げたクロムがそう言い出した。
釣られて私も目線を上げると、確かに雲ひとつない夜空に、月が煌々と浮かんでいた。
「そうね。ねぇ。クロムは出身はどの辺りなの?」
無言で歩き続けるのもなんだと、思い付いた話題を口に出してみる。
私からの質問に、聞かれた本人は驚いたのか、目を見開いた。
「お、俺ですか。えっと、知っているかどうかわかりませんが、ロメル村っていう小さな村です。ここから北の方にあるマッカーブ山脈の麓にあるんです」
「あら。随分と寒い地域に住んでいたのね」
マッカーブ山脈というのは、この国の最北に連なる山脈で、一年中冠雪している山も多いと聞く。
今は辺りが暗く分かりにくいが、確かに北出身に多い、色白で透き通るような肌と、淡い青緑の瞳をしていたことが記憶から呼び起こされた。
「寒いですよ。冬は村から出ることもできないほどです。そんな暮らしが嫌で、村を飛び出したんですよ。俺」
「まぁ! それは大変だったわね。じゃあ、ここへは志願で?」
「はは。実はそうなんです。本当は街で暮らすつもりだったんですが、上手くいかなくて」
クロムはバツが悪そうに頬をかく。
そこで私は、こんな風に誰かの身の上を聞くのは初めての経験だと気付いた。
私は改めてクロムを見つめる。
それに気付いたのか、クロムは長いまつ毛が生え揃った大きな瞳を瞬かせた。
「あ、あの! 聖女様は、慕っている男性とかはいらっしゃらないんですか⁉」
一瞬の間を置いて、クロムは少し身体を強ばらせながら、上擦った声でそんなことを聞いてきた。
思わぬ質問に、私は少し考え込んでしまう。
慕っている男性というのは、どういう意味の質問だろうか。
会ったことはないが、攻撃や回復魔法の基礎となる魔力に関する著書を書いたオルマン伯爵には、尊敬の念を抱いてる。
しかし、今までの話の流れで、そんなことを聞くような話はあっただろうか。
適切な答えが分からず黙っていると、クロムは痺れを切らしたように、先ほどの自分の言葉を否定し始めた。
「ああ! 今の話は忘れてください! なんでもないんです。俺、何を聞いてるんだろ!」
「あら。そう? ごめんなさいね。いい答えが思い付かなくて――」
そういい切ろうとした瞬間、陣営の見張り台から、敵襲を知らせる合図が鳴り響いた。
私は驚き動きを止めるが、クロムはそんな私を自分の方に引き寄せ、辺りに警戒を向ける。
「聖女様! どうやら敵襲です! 早く建物の中へお戻りください‼」
「え、ええ! クロム、あなたは⁉」
「私は衛兵。この時のために私は居るのです。入口まで送りましょう。さぁ、早く‼」
クロムに手を引かれる形で、私は建物の入口へと走る。
もうすぐ入口へと辿り着くといったところで、目の前に何かが降りてきた。
私は思わず声を上げる。
目に入ったのは、黒い羽を持つ魔獣だった。
「くそっ! ガーゴイルか‼ こいつ、空を飛んで陣営の壁を越えやがった‼」
「クロム! 無理はしないで‼ 増援をっ‼」
しかし、辺りを見渡しても近くに他の兵士の姿はなく、どうにか二人だけで切り抜けなくてはいけなさそうだ。
ガーゴイルと呼ばれる、身体が石のような見た目をした魔獣は、牙が生え揃った裂けた口で威嚇の鳴き声を上げる。
次の瞬間、鋭い爪が生えた腕を突き出し、私を庇うように前に立ったクロムに向かって、身体ごと突進してきた。
しかし、クロムは動じることなく、両手で構えた剣を器用に振るって、ガーゴイルの腕を、そして羽の付け根を切り落とした。
思わぬ反撃をくらいうろたえた様子のガーゴイルを、クロムは縦一文字に切り伏せる。
初めて目の当たりにするクロムの実力に、私は目を白黒させてしまった。
「ふぅ……もう大丈夫です。さぁ、今のうちに中へ‼ 俺は、戻ります。あっちの塀の外に沢山群がって来ているようですから」
「ありがとう、クロム。助かったわ。本当に。でも無理はしないでね。死んでしまってはいくら私でも助けられないわ」
私の言葉にクロムは目を細め、そして軍式の礼をする。
「承知しました‼ 副隊長の命令、必ずや守ってみせます‼」
「ええ。そうしてちょうだい。命令違反は、しないでね」
クロムは一度頷くと、大量の魔獣が押し寄せているであろう、戦闘音が響く方へと走り出した。
私はそれを見送ると、建物の中へと入り、寝ている衛生兵を起こしながら治療場へと向かう。
「聖女様、一体何事ですか?」
今まで寝ていたのか、目を擦りながらデイジーが聞いてくる。
「敵襲よ! 前のようにここが襲われているわ。負傷兵が大量に運ばれる可能性が高いわ。心してちょうだい‼」
「わ、分かりましたぁ‼」
状況が飲み込めたのか、デイジーは一気に目が覚めたようで、治療場へと向かう足を速めた。
私は受入係に布をできるだけ速く、かつ正確に負傷兵に付ける様に指示を出した後、気を引き締め運ばれてくるであろう負傷兵を待ち構えた。