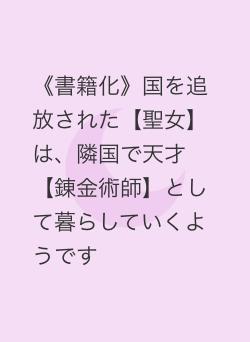「本日よりこちらに配属されたフローラです。よろしくお願いします」
「ああ。いらっしゃい。まぁ、そんなに畏まらず、楽にやってよ」
ベリル王子に要望を出して、次の日には王都を出立して再び戦線へと向かった。
今回配属するのは第二衛生兵部隊。
そこに着くと、その足で司令室にいる部隊長のゾイスの元へ挨拶に向かった。
ゾイスは歳はアンバーより若く見えるが、軍属の割には緩んだ身体の持ち主だった。
初期のアンバーとはまた毛色の違った笑みを顔に貼り付け、右手に持つハンカチーフで額と首元の汗を拭いている。
人を見かけで判断してはいけないけれど、あまり好ましいと思うような相手には思えなかった。
「それでは、早速業務に携わりたいのですがよろしいでしょうか?」
「ん? ああ、ああ。まぁ、そんな気張らなくていいってば。えーっと、フローラ君だっけ? 君に会ったら聞きたい事があったんだ」
「なんでしょうか?」
「君さ。誰に取り入ったの? もし良かったら教えてよ。何? やっぱり女性の武器ってやつを使ったのかな? いいよねぇ」
そう言いながらゾイスはすでに上がっている口角を更に上げる。
どうやら侮辱を受けているようだ。
「なんのことだか分かりません。それでは、早く現場に慣れたいのでこれで失礼します」
「あ、そう。まぁいいや。所詮君は副隊長。部隊長の俺には逆らえないんだから、ちゃんと地位を弁えた行動を頼むね。それじゃ、行っていいよ」
そう言いながら、ゾイスは手に持つハンカチーフを前後に振る。
かなり良い性格の持ち主のようだが、私の目的は部隊長に気に入られることではない。
にやけ顔の上官を無視するように、最低限の礼をしてから司令官室を後にした。
そこではたと、この陣営の治療場の場所を聞くのを忘れたのに気付いた。
通りすがりの兵士に自己紹介をしてから、治療場の場所を聞く。
私が新しく配属された副隊長だと言った時には、かなり驚いた顔をしたが、胸につけてある徽章を見て納得したようだ。
改めて軍特有の礼を私にしてから、丁寧な口調で案内してくれた。
治療場に向かう間、私はその兵士に色々と聞いてみることにした。
「ここの衛生兵の人数を知っている?」
「はい。全部で三十名ほどだと思います」
「結構多いのね。それで、その中で回復魔法を使えるのは何人くらいいるのかしら?」
「回復魔法ですか? 誰がどのくらい使えるかまでは詳しく知りませんが、ここにいる衛生兵は全員使えるはずです。ご存知なかったのですか?」
返答を聞いて、私は驚いた顔をしてしまった。
以前いた第五衛生兵部隊の衛生兵は、今では全員が回復魔法を使えるものの、初めは数人しかいなかった。
それが、ここでは全員が使えるというのだ。
私は、この僥倖に思わず顔を緩めてしまう。
始めから使えるのであれば、それなりの素質を持つ者ばかりなのだろう。
うまく訓練を行えば、その内解呪の魔法すら使いこなす者も多く誕生するかもしれない。
私は喜び勇んで兵士に返答する。
「ごめんなさい。知らないの。ここの衛生兵が全員回復魔法を使えることに、何か理由があるの?」
私の言葉を聞いた兵士は、少し考え込み、そして戸惑いを見せながらこう答えた。
「ここに所属するためには最低限回復魔法を元々使えることが条件なのです。ですから――」
始めの言葉に、素晴らしいと思ったのも束の間、続く言葉は、あまり好ましいものではなかった。
兵士の話はこういうことだった。
衛生兵として送られる者は、回復魔法の適性を鑑みて女性、しかも危険な前線に送られるのは、一身上に様々な問題がある者ばかり。
夫を亡くした未亡人や、雇い先から解雇を告げられたメイドなどだ。
一方、回復魔法を教える施設などは一般的には無い。
私も、父が家庭教師を呼び、様々な書物を買い与えてくれたからこそ、学ぶ事ができた。
それにはそれなり以上の資金が必要だ。
そして、夫や職を失った女性が、簡単に払えるような額では無い。
人によってはその身を売った人もいるだろう。
そうやってなんとか捻出した資金で、ようやく回復魔法の教えを乞い、身に付けて配属されたのがここいる大半らしい。
彼女らの努力は買うが、そこまでしなければならない現状を再度理解し、私はベリル王子に再度教育機関の創設を打診することを心に決めた。
「着きました。ここが治療場です。今、呼び集めますのでお待ちください」
「いいえ。結構よ。挨拶なら作業をしながらでもできるわ。ありがとう。持ち場へ戻って大丈夫よ」
そう言うと、兵士はまた一礼をしてその場から去っていった。
一人残った私は、治療場の状況を確認するために一望する。
広さは第五部隊よりも少し広いがそこまで変わらず、多少臭いや汚れが気になるものの、そこまで酷い状況にはなっていなかった。
安心した気持ちで、治癒に当たっている人たちに目を移していく。
確かに兵士が言っていた通り、その場にいる全員が回復魔法を使えるようだ。
ほとんどが初級の回復魔法ではあるものの、手際よく負傷している兵士の傷を治していくのが見えた。
「なるほど。これならまずは大丈夫そうね――」
そう独り言を呟いた矢先、一人の衛生兵の行動が目に付いた。
その衛生兵は、右足を失った兵士の治癒に当たっている。
その女性は先ほどから初級の回復魔法しか使っていないように思える人物だった。
せいぜい出来ても傷口を塞ぐだけ、失った四肢を再生させるのには無理がある。
もしかしたら、そのような魔法も使えるのかもしれないと、注視していると、果たして使ったのは、やはり初級の治癒の魔法だった。
布で止血をしていた負傷兵の傷が光に包まれ、そして光が消える頃には傷口は塞がっていた。
そこまでやると、衛生兵は立ち上がり、別の負傷兵の方へと向かう。
もちろん、傷口は塞がったものの、脚は再生されておらず、失ったままだ。
負傷兵は悔しそうな顔をして起き上がると、別の者から渡された木の棒を杖代わりにその場を後にしようとしている。
他の衛生兵もその兵士に構う者は見当たらない。
「ちょっと! あなたたち! 何をしているの⁉」
思わず私は叫んでいた。
その声に、その場にいた全員が私の方を向く。
見ていた限り、ごく少数ではあるものの、四肢を再生させることのできる中級の治癒の魔法を使える者も中にはいた。
その衛生兵に任せれば、今目の前にいる杖を突いた兵士の脚を取り戻すことができたはずだ。
「なぜ、治せる者が治さないの⁉ この人の脚は⁉」
状況が掴めていないのか、誰も何も言わず、不思議そうな顔を私に向ける。
時間の無駄を感じ、私は目の前を通り過ぎようとしている脚を失った兵士に声をかける。
「その場に横になりなさい。やり直しよ。脚を、切るわね」
「ああ。いらっしゃい。まぁ、そんなに畏まらず、楽にやってよ」
ベリル王子に要望を出して、次の日には王都を出立して再び戦線へと向かった。
今回配属するのは第二衛生兵部隊。
そこに着くと、その足で司令室にいる部隊長のゾイスの元へ挨拶に向かった。
ゾイスは歳はアンバーより若く見えるが、軍属の割には緩んだ身体の持ち主だった。
初期のアンバーとはまた毛色の違った笑みを顔に貼り付け、右手に持つハンカチーフで額と首元の汗を拭いている。
人を見かけで判断してはいけないけれど、あまり好ましいと思うような相手には思えなかった。
「それでは、早速業務に携わりたいのですがよろしいでしょうか?」
「ん? ああ、ああ。まぁ、そんな気張らなくていいってば。えーっと、フローラ君だっけ? 君に会ったら聞きたい事があったんだ」
「なんでしょうか?」
「君さ。誰に取り入ったの? もし良かったら教えてよ。何? やっぱり女性の武器ってやつを使ったのかな? いいよねぇ」
そう言いながらゾイスはすでに上がっている口角を更に上げる。
どうやら侮辱を受けているようだ。
「なんのことだか分かりません。それでは、早く現場に慣れたいのでこれで失礼します」
「あ、そう。まぁいいや。所詮君は副隊長。部隊長の俺には逆らえないんだから、ちゃんと地位を弁えた行動を頼むね。それじゃ、行っていいよ」
そう言いながら、ゾイスは手に持つハンカチーフを前後に振る。
かなり良い性格の持ち主のようだが、私の目的は部隊長に気に入られることではない。
にやけ顔の上官を無視するように、最低限の礼をしてから司令官室を後にした。
そこではたと、この陣営の治療場の場所を聞くのを忘れたのに気付いた。
通りすがりの兵士に自己紹介をしてから、治療場の場所を聞く。
私が新しく配属された副隊長だと言った時には、かなり驚いた顔をしたが、胸につけてある徽章を見て納得したようだ。
改めて軍特有の礼を私にしてから、丁寧な口調で案内してくれた。
治療場に向かう間、私はその兵士に色々と聞いてみることにした。
「ここの衛生兵の人数を知っている?」
「はい。全部で三十名ほどだと思います」
「結構多いのね。それで、その中で回復魔法を使えるのは何人くらいいるのかしら?」
「回復魔法ですか? 誰がどのくらい使えるかまでは詳しく知りませんが、ここにいる衛生兵は全員使えるはずです。ご存知なかったのですか?」
返答を聞いて、私は驚いた顔をしてしまった。
以前いた第五衛生兵部隊の衛生兵は、今では全員が回復魔法を使えるものの、初めは数人しかいなかった。
それが、ここでは全員が使えるというのだ。
私は、この僥倖に思わず顔を緩めてしまう。
始めから使えるのであれば、それなりの素質を持つ者ばかりなのだろう。
うまく訓練を行えば、その内解呪の魔法すら使いこなす者も多く誕生するかもしれない。
私は喜び勇んで兵士に返答する。
「ごめんなさい。知らないの。ここの衛生兵が全員回復魔法を使えることに、何か理由があるの?」
私の言葉を聞いた兵士は、少し考え込み、そして戸惑いを見せながらこう答えた。
「ここに所属するためには最低限回復魔法を元々使えることが条件なのです。ですから――」
始めの言葉に、素晴らしいと思ったのも束の間、続く言葉は、あまり好ましいものではなかった。
兵士の話はこういうことだった。
衛生兵として送られる者は、回復魔法の適性を鑑みて女性、しかも危険な前線に送られるのは、一身上に様々な問題がある者ばかり。
夫を亡くした未亡人や、雇い先から解雇を告げられたメイドなどだ。
一方、回復魔法を教える施設などは一般的には無い。
私も、父が家庭教師を呼び、様々な書物を買い与えてくれたからこそ、学ぶ事ができた。
それにはそれなり以上の資金が必要だ。
そして、夫や職を失った女性が、簡単に払えるような額では無い。
人によってはその身を売った人もいるだろう。
そうやってなんとか捻出した資金で、ようやく回復魔法の教えを乞い、身に付けて配属されたのがここいる大半らしい。
彼女らの努力は買うが、そこまでしなければならない現状を再度理解し、私はベリル王子に再度教育機関の創設を打診することを心に決めた。
「着きました。ここが治療場です。今、呼び集めますのでお待ちください」
「いいえ。結構よ。挨拶なら作業をしながらでもできるわ。ありがとう。持ち場へ戻って大丈夫よ」
そう言うと、兵士はまた一礼をしてその場から去っていった。
一人残った私は、治療場の状況を確認するために一望する。
広さは第五部隊よりも少し広いがそこまで変わらず、多少臭いや汚れが気になるものの、そこまで酷い状況にはなっていなかった。
安心した気持ちで、治癒に当たっている人たちに目を移していく。
確かに兵士が言っていた通り、その場にいる全員が回復魔法を使えるようだ。
ほとんどが初級の回復魔法ではあるものの、手際よく負傷している兵士の傷を治していくのが見えた。
「なるほど。これならまずは大丈夫そうね――」
そう独り言を呟いた矢先、一人の衛生兵の行動が目に付いた。
その衛生兵は、右足を失った兵士の治癒に当たっている。
その女性は先ほどから初級の回復魔法しか使っていないように思える人物だった。
せいぜい出来ても傷口を塞ぐだけ、失った四肢を再生させるのには無理がある。
もしかしたら、そのような魔法も使えるのかもしれないと、注視していると、果たして使ったのは、やはり初級の治癒の魔法だった。
布で止血をしていた負傷兵の傷が光に包まれ、そして光が消える頃には傷口は塞がっていた。
そこまでやると、衛生兵は立ち上がり、別の負傷兵の方へと向かう。
もちろん、傷口は塞がったものの、脚は再生されておらず、失ったままだ。
負傷兵は悔しそうな顔をして起き上がると、別の者から渡された木の棒を杖代わりにその場を後にしようとしている。
他の衛生兵もその兵士に構う者は見当たらない。
「ちょっと! あなたたち! 何をしているの⁉」
思わず私は叫んでいた。
その声に、その場にいた全員が私の方を向く。
見ていた限り、ごく少数ではあるものの、四肢を再生させることのできる中級の治癒の魔法を使える者も中にはいた。
その衛生兵に任せれば、今目の前にいる杖を突いた兵士の脚を取り戻すことができたはずだ。
「なぜ、治せる者が治さないの⁉ この人の脚は⁉」
状況が掴めていないのか、誰も何も言わず、不思議そうな顔を私に向ける。
時間の無駄を感じ、私は目の前を通り過ぎようとしている脚を失った兵士に声をかける。
「その場に横になりなさい。やり直しよ。脚を、切るわね」