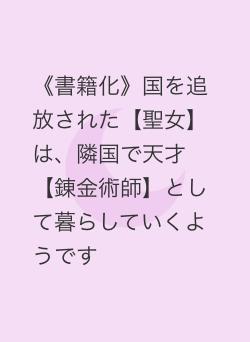ルチル王子の一件があった後、数日経って私は再び王城に呼び出された。
その間、父が「よく戻ってきた」とか「今からでも遅くない」とかを、毎日のように聞かせてくるので、若干うんざりしてしまった。
「やぁ。よく来てくれたね。座ってよ」
「失礼いたします」
今回通されたのは、ベリル王子の私室の一つだった。
ゆったりとしたソファが向かいあわせで置かれていて、奥の方にすでにベリル王子が座っている。
隣に佇むクリスが私に向かって会釈する。
私もベリル王子、そしてクリスにそれぞれ一礼してから、向かいあう形で空いているソファに座った。
「なんだい。こっちにも空きがあるんだから、こっちに座ればいいのに。そこじゃあ、遠いだろ?」
「ご冗談を。今日のご用件はなんでしょうか?」
私の言葉にベリル王子は笑みを強くする。
どうやら私にはこの人の考えを読むのは難しそうだ。
「ああ。そうだね。他でもない。兄さんのことさ」
ベリル王子は呪いが解けた後のルチル王子のことについては淡々と述べた。
その口調や表情からは、そのことを悲しんでいるのか喜んでいるのかは読み取れなかった。
ルチル王子は案の定、心を壊してしまったようだ。
身体に異常がないにもかかわらず、反応もいまいちで、一日中どこか遠くを見つめているだけらしい。
「それで、相談なんだけど。兄さんを元に戻すことはできるのかな?」
「分かりかねます。ただ、魔法の力で、ということでしたら、現時点で方法はありません」
「そうか……それは残念だね。本人の口から直接聞きたかったんだけどな」
「なんのことでしょうか?」
ベリル王子が困った顔でそんなことを言うので、思わず私は聞き返してしまった。
「どうやら、毒を盛られていたみたいなんだ。国王、つまり父がね」
「どういうことです⁉」
「そのまんまの意味さ。しかも困ったことに毒自体は既に解毒したのだけれど、衰弱してしまっていてね。もうそんなに長くないだろう。問題は、誰が毒を盛っていたか、ということなんだけど」
「ルチル王子が犯人だと?」
私のはっきりとした物言いに、ベリル王子の眉が一瞬跳ねた。
「状況的に一番怪しいのはね。私ですら、父にはそんなに近寄れなかったんだ。誰かを使おうにも、かなり難しいだろうね」
「それを話させるために、ルチル王子の治療が必要だと?」
「いや。それだけの気持ちではもちろんないさ。純粋に良くなって欲しいとは思っている。一応でも私の兄だからね。そうだ。話のついでに、あの女がどうなったか――」
「必要ありません」
ベリル王子にわざわざ聞かなくても、マリーゴールド、そしてその一族がどうなったかは簡単に想像できる。
家の使用人からマリーゴールドの家が取り潰しにあったと聞いた。
事が事なだけに理由は大っぴらにはなっていないが、そういう事なのだろう。
私は一瞬目を瞑り、マリーゴールドとその一族の安寧を祈った。
「そうか。それで、色々と処理をしないといけないことが多すぎて、君を正式に聖女だと言うことは当分難しそうなんだ。済まないね」
「いえ。構いません。なんでしたら今後も必要ありません」
元々聖女になどなる気はないのだ。
それは実際に戦地へ赴き、負傷兵たちの治療に従事して、より強い気持ちになった。
今さら聖女になりたい気持ちなど一切なかった。
むしろ王都に繋ぎ止められている今が、どうしようもなく感じられた。
今こう話している間にも、負傷兵の治癒は行われているだろう。
デイジーたちは問題なくこなせているだろうか。
「相変わらずだね。ただ、それでは王族としての威厳が保てない。私のできる範囲で、個人的にお礼をしたいと思っている。何か欲しいものはあるかな?」
「どんなことでもいいのでしょうか?」
「私ができる範囲ならね。どんなことでも叶えよう」
「それでは、私を衛生兵として戦場に戻してください。今すぐに」
私は考えるまでもなく、願いを言った。
それを聞いたベリル王子は目を見開き驚いた顔をした後、声を出して笑った。
「あっはっは。まさか、あの地獄から帰還して、それでもあそこに行きたいなんて言うとは思っていなかったよ」
「地獄だからこそ行くのです。そうしなければ、いつまでも地獄のままです」
「分かった。私が総司令官だということも知っての願いなのだろう。私から言い出したことだ。約束は守ろう」
「ありがとうございます」
これでやり残したことを再びできる。
しかし、ベリル王子から出た言葉は私が想像していない事だった。
「ただし。戻る部隊は別の部隊だ。未来の聖女に、それなりの席を用意しなくては。ちょうど、第二部隊の副隊長に空きが出来たところだったはずだ」
以前居た第五衛生兵部隊に戻れると思っていたところ、どうやらこれから向かうのは第二衛生兵部隊のようだ。
しかも、その部隊の副隊長として。
役に就けば自分のやりたいことも通しやすいだろう。
慣れ親しんだ彼女たちと一緒に働けないのは残念だけれど。
そんなことを思いながら、私は自分の信念を実現するために、戦地で自分がやるべきことに思いを馳せていた。
その間、父が「よく戻ってきた」とか「今からでも遅くない」とかを、毎日のように聞かせてくるので、若干うんざりしてしまった。
「やぁ。よく来てくれたね。座ってよ」
「失礼いたします」
今回通されたのは、ベリル王子の私室の一つだった。
ゆったりとしたソファが向かいあわせで置かれていて、奥の方にすでにベリル王子が座っている。
隣に佇むクリスが私に向かって会釈する。
私もベリル王子、そしてクリスにそれぞれ一礼してから、向かいあう形で空いているソファに座った。
「なんだい。こっちにも空きがあるんだから、こっちに座ればいいのに。そこじゃあ、遠いだろ?」
「ご冗談を。今日のご用件はなんでしょうか?」
私の言葉にベリル王子は笑みを強くする。
どうやら私にはこの人の考えを読むのは難しそうだ。
「ああ。そうだね。他でもない。兄さんのことさ」
ベリル王子は呪いが解けた後のルチル王子のことについては淡々と述べた。
その口調や表情からは、そのことを悲しんでいるのか喜んでいるのかは読み取れなかった。
ルチル王子は案の定、心を壊してしまったようだ。
身体に異常がないにもかかわらず、反応もいまいちで、一日中どこか遠くを見つめているだけらしい。
「それで、相談なんだけど。兄さんを元に戻すことはできるのかな?」
「分かりかねます。ただ、魔法の力で、ということでしたら、現時点で方法はありません」
「そうか……それは残念だね。本人の口から直接聞きたかったんだけどな」
「なんのことでしょうか?」
ベリル王子が困った顔でそんなことを言うので、思わず私は聞き返してしまった。
「どうやら、毒を盛られていたみたいなんだ。国王、つまり父がね」
「どういうことです⁉」
「そのまんまの意味さ。しかも困ったことに毒自体は既に解毒したのだけれど、衰弱してしまっていてね。もうそんなに長くないだろう。問題は、誰が毒を盛っていたか、ということなんだけど」
「ルチル王子が犯人だと?」
私のはっきりとした物言いに、ベリル王子の眉が一瞬跳ねた。
「状況的に一番怪しいのはね。私ですら、父にはそんなに近寄れなかったんだ。誰かを使おうにも、かなり難しいだろうね」
「それを話させるために、ルチル王子の治療が必要だと?」
「いや。それだけの気持ちではもちろんないさ。純粋に良くなって欲しいとは思っている。一応でも私の兄だからね。そうだ。話のついでに、あの女がどうなったか――」
「必要ありません」
ベリル王子にわざわざ聞かなくても、マリーゴールド、そしてその一族がどうなったかは簡単に想像できる。
家の使用人からマリーゴールドの家が取り潰しにあったと聞いた。
事が事なだけに理由は大っぴらにはなっていないが、そういう事なのだろう。
私は一瞬目を瞑り、マリーゴールドとその一族の安寧を祈った。
「そうか。それで、色々と処理をしないといけないことが多すぎて、君を正式に聖女だと言うことは当分難しそうなんだ。済まないね」
「いえ。構いません。なんでしたら今後も必要ありません」
元々聖女になどなる気はないのだ。
それは実際に戦地へ赴き、負傷兵たちの治療に従事して、より強い気持ちになった。
今さら聖女になりたい気持ちなど一切なかった。
むしろ王都に繋ぎ止められている今が、どうしようもなく感じられた。
今こう話している間にも、負傷兵の治癒は行われているだろう。
デイジーたちは問題なくこなせているだろうか。
「相変わらずだね。ただ、それでは王族としての威厳が保てない。私のできる範囲で、個人的にお礼をしたいと思っている。何か欲しいものはあるかな?」
「どんなことでもいいのでしょうか?」
「私ができる範囲ならね。どんなことでも叶えよう」
「それでは、私を衛生兵として戦場に戻してください。今すぐに」
私は考えるまでもなく、願いを言った。
それを聞いたベリル王子は目を見開き驚いた顔をした後、声を出して笑った。
「あっはっは。まさか、あの地獄から帰還して、それでもあそこに行きたいなんて言うとは思っていなかったよ」
「地獄だからこそ行くのです。そうしなければ、いつまでも地獄のままです」
「分かった。私が総司令官だということも知っての願いなのだろう。私から言い出したことだ。約束は守ろう」
「ありがとうございます」
これでやり残したことを再びできる。
しかし、ベリル王子から出た言葉は私が想像していない事だった。
「ただし。戻る部隊は別の部隊だ。未来の聖女に、それなりの席を用意しなくては。ちょうど、第二部隊の副隊長に空きが出来たところだったはずだ」
以前居た第五衛生兵部隊に戻れると思っていたところ、どうやらこれから向かうのは第二衛生兵部隊のようだ。
しかも、その部隊の副隊長として。
役に就けば自分のやりたいことも通しやすいだろう。
慣れ親しんだ彼女たちと一緒に働けないのは残念だけれど。
そんなことを思いながら、私は自分の信念を実現するために、戦地で自分がやるべきことに思いを馳せていた。