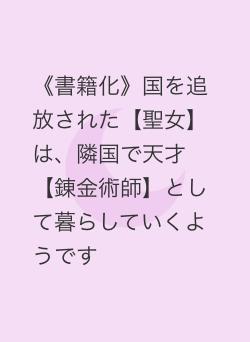「え? 王都への帰還命令ですか⁉」
「うん。そうだね」
司令室に突然呼び出され、最初にアンバーに告げられたのが、王都に戻れという話だった。
あまりの唐突な命令に、私は異議を申し出る。
「突然過ぎます! 帰還理由を教えてください。私の行動に問題があったとは思えませんが、何か理由があるなら改善します。やっと軌道に乗り始めている最中なのは部隊長もご存知のはずです‼」
一気にまくし立てる私に、アンバーは両手を前に出してなだめる仕草をする。
「まぁまぁ。今から説明するから。聖女様。いいね?」
アンバーの表情を見て、この命令が今目の前にいる人物の本意では無いと悟り、少し気持ちを落ち着かせる。
「まず、僕だって寝耳に水さ。実際君はよくやってくれている。知ってるかい? 君が来る前のここに運ばれた負傷兵の致死率は約四割だったんだ。それが、今では、ほぼゼロと言っていい」
「ええ。色々とやっていますからね。だけど、まだ足りません。今では衛生兵の質も量も十分とは言えません」
デイジーを始め、徐々に何人かは、初級の解毒魔法や中級の治癒魔法への足掛かりができ始めようとしていた。
しかし、それでも重傷の兵士の対応はほとんど私がしている。
もしここで私が抜ければ、瓦解する、とまではいかないものの、かなりの無理を強いることになるだろう。
そうすれば、緊急の場合に対応が難しくなる。
魔石が十分に確保できていない現状、無理をすれば衛生兵にも犠牲が出る危険性がある。
犠牲の上での奉仕ではいけないのだ。
「うんうん。そうだね。その点も聖女様はよくやってくれていると思うよ。彼女らがあそこまで回復魔法を使いこなすようになるとは。正直僕は思いもしなかったよ」
「運良く素質が高い人たちが多くいてくれたおかげです。また、彼女らも勤勉で、私も助かっています」
「ちょっと話が逸れたね。とにかく、君には王都に帰還してもらわないといけない。これは総司令官命令だからね」
「総司令官……ですか?」
総司令官と言われて私は首を傾げる。
国王は今も病に伏せているはずで、実権を任されているルチル王子もまだ療養中の身のはずだ。
「うん。ベリル王子直々の命令らしいよ。いやぁたまげたね。聖女様はさすが侯爵令嬢だけあるってことかな? ベリル王子と面識があるなんて」
「ベリル王子が総司令官ということは、正式に決まったのですか⁉」
「うん。どうやらそうみたい。この前僕の所にも伝令が来たよ。それでね、とにかく戻るしかない。寂しくなるけどね」
「分かりました……とりあえず、荷物の整理をして来ます。日時はいつでしょうか?」
前にアンバーが言っていたように、とうとうベリル王子が総司令官に就任したということは、今までに送っていた手紙の内容の実現の可能性も出て来たということだ。
そう考えれば考えるほど、今この状況で現場を後にするのが口惜しくてたまらなかった。
「いや。そんな暇はないんだ。今すぐに出発だ。とりあえず、最低限必要なものを持って行ってくれ。荷物は後から送る手配をすることになっている」
「なんですって⁉ それだけ緊急、ということでしょうか?」
「どうだろうね……正直お偉いさんの考えることなんて僕は分からないさ。とりあえず、すでに移動の用意は済ませてある。護衛もね。思えば短い間だったけど、寂しくなるよ……」
「分かりました。ありがとうございます。部隊長も……色々とありがとうございました」
私は衛生兵たちに簡単な伝言を頼み、また、伝えきれないことは後日手紙で送ることを伝えてその場を後にする。
前線の状況も気になるものの、すでに自分の力でどうすることもできないというのは理解していた。
それよりも、今は王都への帰還命令のことについて考えていた。
ベリル王子が思いつきで何かをする人物だとは思えない。
これだけ急かすということは、何かしらの重大な理由があるということだろう。
移動する間、私はこれから起こることが何なのかをぼんやりと考えていた。
「聖女様。考えことですか? でも、良かったですね。安全な場所に帰ることができて。俺としては正直、寂しいってのがありますけど」
「ああ……クロム。ええ、ちょっと何故突然呼び戻されたのかと考えていてね」
護衛として付けられたクロムが、私に話しかけて来た。
何でも、手紙のやり取りの際も、護衛の件も本人がアンバーに直に頼んでその役目を勝ち取ったのだとか。
手紙のやり取りはともかく、護衛という点ではクロムは第五衛生兵部隊に所属する者の中で、アンバーを除けば一番有能だと言えた。
逆に言えば、そんな彼が陣営を離れることを許可してくれたアンバーの、私に対する配慮も並々ならないと感謝している。
実際、陣営へ向かう最中に魔獣に襲われ戦線に辿り着くことなく命を失う、ということがないわけではない。
そのため、ある程度重要な人物の陣営から最寄りの街までの移動の際は、護衛が付くのがほとんどだった。
しかし、てっきりクロムも街までの護衛かと思っていたら、王都まで一緒に付いてくるとのことだった。
何でも、護衛を王都まで付けることも総司令官、つまりベリル王子の要求だったとか。
「もうすぐ王都に着きますよ。俺、王都に行くの初めてなんですよ。凄いですね……」
クロムの言葉に外の風景に目を向ける。
目の前には、生まれてからつい最近まで育った街並みが広がっていた。
「うん。そうだね」
司令室に突然呼び出され、最初にアンバーに告げられたのが、王都に戻れという話だった。
あまりの唐突な命令に、私は異議を申し出る。
「突然過ぎます! 帰還理由を教えてください。私の行動に問題があったとは思えませんが、何か理由があるなら改善します。やっと軌道に乗り始めている最中なのは部隊長もご存知のはずです‼」
一気にまくし立てる私に、アンバーは両手を前に出してなだめる仕草をする。
「まぁまぁ。今から説明するから。聖女様。いいね?」
アンバーの表情を見て、この命令が今目の前にいる人物の本意では無いと悟り、少し気持ちを落ち着かせる。
「まず、僕だって寝耳に水さ。実際君はよくやってくれている。知ってるかい? 君が来る前のここに運ばれた負傷兵の致死率は約四割だったんだ。それが、今では、ほぼゼロと言っていい」
「ええ。色々とやっていますからね。だけど、まだ足りません。今では衛生兵の質も量も十分とは言えません」
デイジーを始め、徐々に何人かは、初級の解毒魔法や中級の治癒魔法への足掛かりができ始めようとしていた。
しかし、それでも重傷の兵士の対応はほとんど私がしている。
もしここで私が抜ければ、瓦解する、とまではいかないものの、かなりの無理を強いることになるだろう。
そうすれば、緊急の場合に対応が難しくなる。
魔石が十分に確保できていない現状、無理をすれば衛生兵にも犠牲が出る危険性がある。
犠牲の上での奉仕ではいけないのだ。
「うんうん。そうだね。その点も聖女様はよくやってくれていると思うよ。彼女らがあそこまで回復魔法を使いこなすようになるとは。正直僕は思いもしなかったよ」
「運良く素質が高い人たちが多くいてくれたおかげです。また、彼女らも勤勉で、私も助かっています」
「ちょっと話が逸れたね。とにかく、君には王都に帰還してもらわないといけない。これは総司令官命令だからね」
「総司令官……ですか?」
総司令官と言われて私は首を傾げる。
国王は今も病に伏せているはずで、実権を任されているルチル王子もまだ療養中の身のはずだ。
「うん。ベリル王子直々の命令らしいよ。いやぁたまげたね。聖女様はさすが侯爵令嬢だけあるってことかな? ベリル王子と面識があるなんて」
「ベリル王子が総司令官ということは、正式に決まったのですか⁉」
「うん。どうやらそうみたい。この前僕の所にも伝令が来たよ。それでね、とにかく戻るしかない。寂しくなるけどね」
「分かりました……とりあえず、荷物の整理をして来ます。日時はいつでしょうか?」
前にアンバーが言っていたように、とうとうベリル王子が総司令官に就任したということは、今までに送っていた手紙の内容の実現の可能性も出て来たということだ。
そう考えれば考えるほど、今この状況で現場を後にするのが口惜しくてたまらなかった。
「いや。そんな暇はないんだ。今すぐに出発だ。とりあえず、最低限必要なものを持って行ってくれ。荷物は後から送る手配をすることになっている」
「なんですって⁉ それだけ緊急、ということでしょうか?」
「どうだろうね……正直お偉いさんの考えることなんて僕は分からないさ。とりあえず、すでに移動の用意は済ませてある。護衛もね。思えば短い間だったけど、寂しくなるよ……」
「分かりました。ありがとうございます。部隊長も……色々とありがとうございました」
私は衛生兵たちに簡単な伝言を頼み、また、伝えきれないことは後日手紙で送ることを伝えてその場を後にする。
前線の状況も気になるものの、すでに自分の力でどうすることもできないというのは理解していた。
それよりも、今は王都への帰還命令のことについて考えていた。
ベリル王子が思いつきで何かをする人物だとは思えない。
これだけ急かすということは、何かしらの重大な理由があるということだろう。
移動する間、私はこれから起こることが何なのかをぼんやりと考えていた。
「聖女様。考えことですか? でも、良かったですね。安全な場所に帰ることができて。俺としては正直、寂しいってのがありますけど」
「ああ……クロム。ええ、ちょっと何故突然呼び戻されたのかと考えていてね」
護衛として付けられたクロムが、私に話しかけて来た。
何でも、手紙のやり取りの際も、護衛の件も本人がアンバーに直に頼んでその役目を勝ち取ったのだとか。
手紙のやり取りはともかく、護衛という点ではクロムは第五衛生兵部隊に所属する者の中で、アンバーを除けば一番有能だと言えた。
逆に言えば、そんな彼が陣営を離れることを許可してくれたアンバーの、私に対する配慮も並々ならないと感謝している。
実際、陣営へ向かう最中に魔獣に襲われ戦線に辿り着くことなく命を失う、ということがないわけではない。
そのため、ある程度重要な人物の陣営から最寄りの街までの移動の際は、護衛が付くのがほとんどだった。
しかし、てっきりクロムも街までの護衛かと思っていたら、王都まで一緒に付いてくるとのことだった。
何でも、護衛を王都まで付けることも総司令官、つまりベリル王子の要求だったとか。
「もうすぐ王都に着きますよ。俺、王都に行くの初めてなんですよ。凄いですね……」
クロムの言葉に外の風景に目を向ける。
目の前には、生まれてからつい最近まで育った街並みが広がっていた。