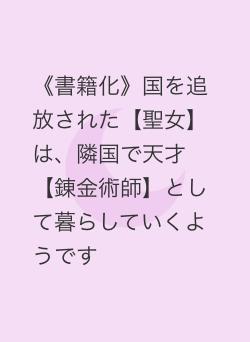「フローラが聖女ではないとは、どういうことですか⁉ ルチル王子!」
私の父、アルマン・ルイ・ド・ゴール侯爵が叫ぶ。
父と相対するのは、この国の第一王子であるルチル・ヘンリー・ド・シャルル王子。
柔らかな金髪と自らの力を象徴する紅い瞳を持つこの男性は、病弱な国王が療養中の今、実質的な権限を持つ王太子だ。
「どうもこうも、事実を述べただけだよ。アルマン。聖女と思ってフローラには尽くしてもらったが、真の聖女は他にいた、ということだ」
「そんなことは……! 現にフローラは【リラの花】を紫色に咲かせたのですから」
【リラの花】と言うのは聖女の証と呼ばれる花で、聖女が毎年育てている花だ。
聖女選定の際には、それがめぼしい候補者に配られる。
そして育てていくと、育てたものの魔力を吸い花を咲かせる。
普通は白色だが、聖女に選ばれるもの花は鮮やかな紫色に色付く。
私は父にプレゼントされたこの花をそうとは知らずに育て、見事に濃い紫色の花が咲いた。
「だからそれが偽物だったと言っておるのだ。白い花弁に丁寧に色を塗って騙そうとしたのだ」
「そ、そんな馬鹿なことが! では! 本当の聖女はどこにいると言うのですか⁉」
「ここにいる。このマリーゴールドこそが真の聖女だよ。なぁ? マリーゴールド」
「ば、馬鹿なことを! 聖女に選ばれると言うことがどれほど重要なことかお分かりにならぬのですか⁉」
父はなおも私を聖女にしようと言うのか。
今までも何度もご辞退すると伝えてきたと言うのに。
聖女というのは、回復魔法を習得した貴族の令嬢の中でも、一人だけがなることを許される特別な存在だ、と父は言う。
前聖女が亡くなり、次の聖女が誰になるかは父を含め、多くの貴族の関心ごとらしい。
しかし私にはそんなことはどうでもいいことだった。
聖女はその身を国に捧げる――これについてはなんの問題もない。
だけどその後が気に食わないのだ。
一日中平和のために祈りを捧げ、国王を始めとした王族が怪我をした時にだけその卓越した回復魔法を使う。
そんな物になるために私は回復魔法を学んだのではない。
私が回復魔法を学んだ理由。それは今も前線で傷つき倒れている兵士たちを癒すためだ。
兵士たちだけではない。
国民全体が怪我をしても十分な回復魔法を受けることができず、落とさなくてもいい命を落としている。
それを改善したいと、私は必死で回復魔法を学んだ。
それなのに、王族にしか使うことが許されず、それ以外は祈るだけの聖女などに、誰がなりたいと言うのだろうか。
また、聖女はその国の王太子と婚姻関係を結ばされる。
つまり、私が聖女になれば、ルチル王子の妻にならなくてはならない。
私がまるで他人事のようにルチル王子と父のやりとりを見ていると、ふとマリーゴールドと目が合う。
緩やかなカーブを持つ桃金色の髪と、緑藍色の瞳を持つ彼女は、非常にふくよかな肢体をしていた。
ルチル王子は物腰柔らかで、この少しお頭の弱いマリーゴールドのような女性が好みなのは知っていた。
私は直毛の灰銀色の髪と薄褐色の瞳、そしてスレンダーな肢体していて、聖女に選ばれたと伝えた時のルチル王子の落胆を見ると、残念ながら好みではなかったのだろう。
(胸はそれなりにある方だと思うのだけれど……)
そんなことを思いながら目線を自分の体に向けると、父が私の婚姻について話しているのが聞こえた。
「しかし! それでは王子と娘の! フローラとの婚姻は⁉」
「そんなものは当然破棄だ。もういいぞ。アルマン。これ以上俺に楯突くのであれば、いくらお前でも処罰せねばならなくなる。親子揃って戦場に行かせるのはさすがに忍びない」
「なっ! なんですと⁉ 娘を! 娘を戦地へと赴かせるとおっしゃるのですか‼」
「ああ。そうだ。本来ならば、国を欺こうとした罪で一生幽閉が妥当かと思ったのだがな。ベリルの進言で、せっかく使える回復魔法を国のために使ってもらう方が少しは役に立つ、と言うことになった」
ベリルというのはこの国の第二王子であるベリル王子のことだろう。
ベリル王子は兄のルチル王子と異なり合理的な考えの持ち主だ。
さらに昔一度だけ舞踏会でエスコートをしてくれた際に、私の考えを伝えたことがあり、賛同してくれた記憶がある。
ただ随分と昔のことで、そのことをベリル王子が覚えているかどうかは定かではない。
まさか、ベリル王子がその時の私の考え通りに進言してくれるとは思ってもいなかったので、私は目を見開き、続きを聴き入った。
「まぁ、さすがに死亡率が高い前線に行かせるわけじゃない。せいぜい陣営の指揮官付きの回復魔導士として重宝されるだろう」
これで話はお終いだというふうに、ルチル王子は手で合図を送った。
いくら私の父が侯爵だとはいえ、この国の王子であり実質的な第一権力者に歯向かうことなどできるはずもない。
父はルチル王子の合図に従いその場を離れようとする。
私もそれにならい、踵を返す。
ふと、振り返りもう一度だけルチル王子とマリーゴールドの顔を見ると、二人は満足そうな顔で笑っていた。
☆
「そうだ‼ 国王に! 国王に直訴すればよいのだ‼」
父は屋敷に戻ってから、落ち着きなく部屋中をうろうろと歩き回っていた。
そして名案を思いついたとばかりに手を打つと、そんなことを言い出す。
「お父様。それはできるはずがありません。国王様は病床に伏せております。前聖女様が亡くなった今、お会いできるのは次期聖女に選ばれた者だけです」
「だから! お前が行って国王の病を治してくれば良いのだ! そうすれば、国王もお前を聖女として認めるに違いない」
父はなおもこの案が素晴らしいと思ってやまないらしい。
しかしどう考えても、実権を握っているルチル王子の承諾を得ることなく王に会うことなど不可能だ。
「お父様。お父様が普段からは考えられないような思考をお持ちになるほど、私のことを愛していることは分かりました」
「そ、そうだぞ‼ 儂は何も変なことを考えているのではなく、お前のためを思って」
「ということで、これ以上お父様、この家にご迷惑をおかけするつもりはございません。もうじき使いの者が来るはずです。私はルチル王子のご指示通り、戦地で負傷兵のため、奉仕してきます」
「なぁ⁉ ならぬ! ならぬというのだ‼」
慌てる父を置き去りにして、私は自室に戻り、必要な荷造りを始めたのだった。
私の父、アルマン・ルイ・ド・ゴール侯爵が叫ぶ。
父と相対するのは、この国の第一王子であるルチル・ヘンリー・ド・シャルル王子。
柔らかな金髪と自らの力を象徴する紅い瞳を持つこの男性は、病弱な国王が療養中の今、実質的な権限を持つ王太子だ。
「どうもこうも、事実を述べただけだよ。アルマン。聖女と思ってフローラには尽くしてもらったが、真の聖女は他にいた、ということだ」
「そんなことは……! 現にフローラは【リラの花】を紫色に咲かせたのですから」
【リラの花】と言うのは聖女の証と呼ばれる花で、聖女が毎年育てている花だ。
聖女選定の際には、それがめぼしい候補者に配られる。
そして育てていくと、育てたものの魔力を吸い花を咲かせる。
普通は白色だが、聖女に選ばれるもの花は鮮やかな紫色に色付く。
私は父にプレゼントされたこの花をそうとは知らずに育て、見事に濃い紫色の花が咲いた。
「だからそれが偽物だったと言っておるのだ。白い花弁に丁寧に色を塗って騙そうとしたのだ」
「そ、そんな馬鹿なことが! では! 本当の聖女はどこにいると言うのですか⁉」
「ここにいる。このマリーゴールドこそが真の聖女だよ。なぁ? マリーゴールド」
「ば、馬鹿なことを! 聖女に選ばれると言うことがどれほど重要なことかお分かりにならぬのですか⁉」
父はなおも私を聖女にしようと言うのか。
今までも何度もご辞退すると伝えてきたと言うのに。
聖女というのは、回復魔法を習得した貴族の令嬢の中でも、一人だけがなることを許される特別な存在だ、と父は言う。
前聖女が亡くなり、次の聖女が誰になるかは父を含め、多くの貴族の関心ごとらしい。
しかし私にはそんなことはどうでもいいことだった。
聖女はその身を国に捧げる――これについてはなんの問題もない。
だけどその後が気に食わないのだ。
一日中平和のために祈りを捧げ、国王を始めとした王族が怪我をした時にだけその卓越した回復魔法を使う。
そんな物になるために私は回復魔法を学んだのではない。
私が回復魔法を学んだ理由。それは今も前線で傷つき倒れている兵士たちを癒すためだ。
兵士たちだけではない。
国民全体が怪我をしても十分な回復魔法を受けることができず、落とさなくてもいい命を落としている。
それを改善したいと、私は必死で回復魔法を学んだ。
それなのに、王族にしか使うことが許されず、それ以外は祈るだけの聖女などに、誰がなりたいと言うのだろうか。
また、聖女はその国の王太子と婚姻関係を結ばされる。
つまり、私が聖女になれば、ルチル王子の妻にならなくてはならない。
私がまるで他人事のようにルチル王子と父のやりとりを見ていると、ふとマリーゴールドと目が合う。
緩やかなカーブを持つ桃金色の髪と、緑藍色の瞳を持つ彼女は、非常にふくよかな肢体をしていた。
ルチル王子は物腰柔らかで、この少しお頭の弱いマリーゴールドのような女性が好みなのは知っていた。
私は直毛の灰銀色の髪と薄褐色の瞳、そしてスレンダーな肢体していて、聖女に選ばれたと伝えた時のルチル王子の落胆を見ると、残念ながら好みではなかったのだろう。
(胸はそれなりにある方だと思うのだけれど……)
そんなことを思いながら目線を自分の体に向けると、父が私の婚姻について話しているのが聞こえた。
「しかし! それでは王子と娘の! フローラとの婚姻は⁉」
「そんなものは当然破棄だ。もういいぞ。アルマン。これ以上俺に楯突くのであれば、いくらお前でも処罰せねばならなくなる。親子揃って戦場に行かせるのはさすがに忍びない」
「なっ! なんですと⁉ 娘を! 娘を戦地へと赴かせるとおっしゃるのですか‼」
「ああ。そうだ。本来ならば、国を欺こうとした罪で一生幽閉が妥当かと思ったのだがな。ベリルの進言で、せっかく使える回復魔法を国のために使ってもらう方が少しは役に立つ、と言うことになった」
ベリルというのはこの国の第二王子であるベリル王子のことだろう。
ベリル王子は兄のルチル王子と異なり合理的な考えの持ち主だ。
さらに昔一度だけ舞踏会でエスコートをしてくれた際に、私の考えを伝えたことがあり、賛同してくれた記憶がある。
ただ随分と昔のことで、そのことをベリル王子が覚えているかどうかは定かではない。
まさか、ベリル王子がその時の私の考え通りに進言してくれるとは思ってもいなかったので、私は目を見開き、続きを聴き入った。
「まぁ、さすがに死亡率が高い前線に行かせるわけじゃない。せいぜい陣営の指揮官付きの回復魔導士として重宝されるだろう」
これで話はお終いだというふうに、ルチル王子は手で合図を送った。
いくら私の父が侯爵だとはいえ、この国の王子であり実質的な第一権力者に歯向かうことなどできるはずもない。
父はルチル王子の合図に従いその場を離れようとする。
私もそれにならい、踵を返す。
ふと、振り返りもう一度だけルチル王子とマリーゴールドの顔を見ると、二人は満足そうな顔で笑っていた。
☆
「そうだ‼ 国王に! 国王に直訴すればよいのだ‼」
父は屋敷に戻ってから、落ち着きなく部屋中をうろうろと歩き回っていた。
そして名案を思いついたとばかりに手を打つと、そんなことを言い出す。
「お父様。それはできるはずがありません。国王様は病床に伏せております。前聖女様が亡くなった今、お会いできるのは次期聖女に選ばれた者だけです」
「だから! お前が行って国王の病を治してくれば良いのだ! そうすれば、国王もお前を聖女として認めるに違いない」
父はなおもこの案が素晴らしいと思ってやまないらしい。
しかしどう考えても、実権を握っているルチル王子の承諾を得ることなく王に会うことなど不可能だ。
「お父様。お父様が普段からは考えられないような思考をお持ちになるほど、私のことを愛していることは分かりました」
「そ、そうだぞ‼ 儂は何も変なことを考えているのではなく、お前のためを思って」
「ということで、これ以上お父様、この家にご迷惑をおかけするつもりはございません。もうじき使いの者が来るはずです。私はルチル王子のご指示通り、戦地で負傷兵のため、奉仕してきます」
「なぁ⁉ ならぬ! ならぬというのだ‼」
慌てる父を置き去りにして、私は自室に戻り、必要な荷造りを始めたのだった。