reply 第3話 「鳴き声」
―――...なんか、顔が
変な感じ...、
あれ。私今起きてるんだっけ。...それとも、
いや...寝てるんだ。
でも、この頬の感触は、何?
......
舐められて...る?
パチッと目を覚ます。
目線を下にずらすと、ピンクの舌が飛び込んできた。
あまりに驚き、無言で飛び起きる。
するとその持ち主も私に驚いて後ずさった気配がした。
なになになに!?
パニック状態になりながら、ベッド近くの電気スタンドに手を伸ばし明かりを点ける。
いきなり明るくなった空間に思わず目を瞑ったが
眩しさに堪えながらも、微かに開けた。

そこには、耳と尻尾を伏せて悲しそうにこちらを見つめるこぎつね。
そうだった。
昨日の出来事をすっかり忘れてた。
なんて馬鹿な私...。
かわいそうに、怯えたかしら。
「ごめんね。」
さっき頬を舐めてくれていたのは、このこぎつねか...
そっと抱きあげ膝の上に置く。
せっかく慣れてきてくれたのに。
これがきっかけで怯えだしたらどうしよう。
頭を優しく撫でる。
...じっとしているから、大丈夫かも知れない。
――それにしても、
まだ辺りは暗い。
今は何時なんだろう。
目覚まし時計を見ると、朝の5時だった。
今日は朝イチで会議があるし...もう起きるか。
ベッド脇に足を下ろし、スリッパを履く。
こぎつねはもう少し寝かせておこうと毛布をかけたが
するりとベッドから下りて部屋を出て行ってしまった。
...そうだ。
狐のご飯も用意しないと!
トイレは前に猫を預かった時のトイレシートが残っていたはず。
パタパタとスリッパの音を立てながら台所へ向かった。

...狐って何食べるのよ。
冷蔵庫を漁るが、見当が付かない。
あ、昔話とかでは油揚げを食べるってあったな。
えーっと、“狐 食べ物”...っと。
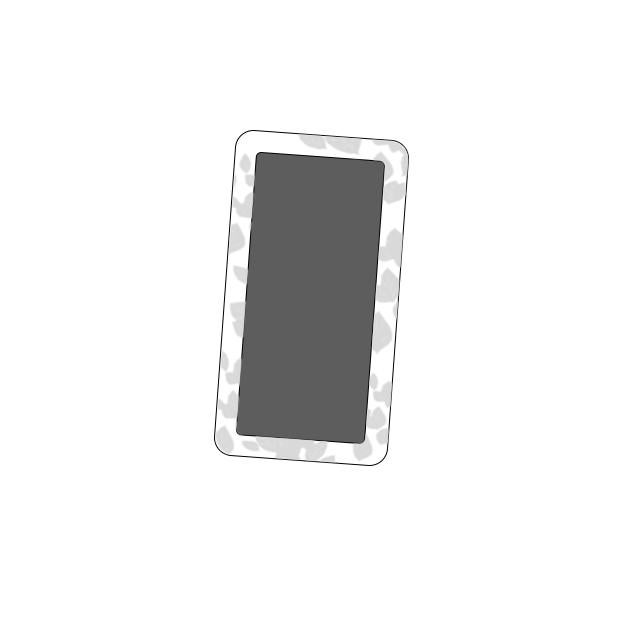
狐は雑食。
油揚げは食べることは食べる...か。
...。
一応、作ってみるか。
フライパンに二枚乗せて軽く焼く。
すると、いつの間にかこぎつねが足元まできていて、こちらを見上げていた。
......正解?

小さく切って皿に乗せ、目の前に差し出す。
すると匂いを嗅いだ後、少しずつ食べだした。
...よかった。
ひとまず、お昼ごはん用にも作って置いておこう。

朝食を済ませた後、身支度を整えた。
――早いけど、そろそろ行こうかな。
「こぎつねちゃん。」
クルッと振り返ったこぎつねに、目線が近くなるようしゃがんで話し掛ける。
「今から、出かけてくるね。」
「夕方には帰って来れるようにするから。」
伝わるわけないけど、と思いながらも話し掛ける。
でも。この狐は...どこか不思議なところがある。
本当は言葉が理解出来るのかも知れない。
だってほら、
こうしている間もじっと私の目を見つめている。
...。
「じゃあね。」
と、笑いかけて立ち上がった。
バッグを掴み、玄関へ進む。
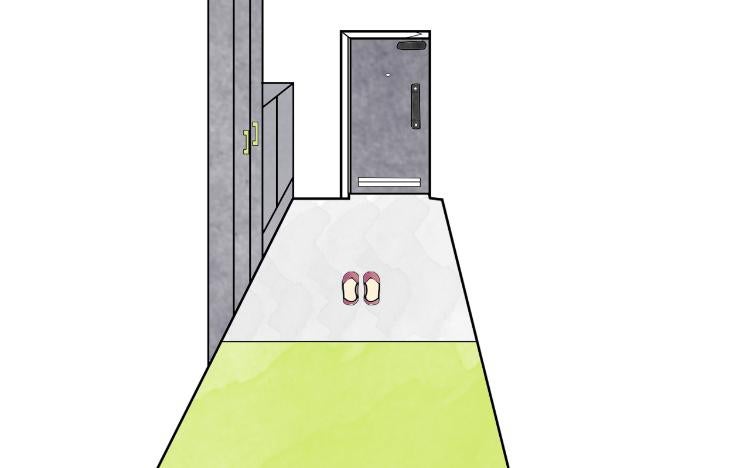
すると
「――キャワワッ」
...え?
今の鳴き声は...
もしかして、この子が?
振り返ると、フサフサの尻尾を振っている。
その愛らしい姿に自然とまた笑顔になれた。
「行ってきます!」

仕事をしながら、ボーッとこぎつねのことを考えていた。
その時、森高先輩の声がフロアに響く。
「みんな、聞いてくれ。」
その言葉に、一同が視線を向ける。
森高先輩の隣には糸川君が立っていた。
「この度、糸川君が統括部長に就任することになった!」
「社長直々の推薦だ。みんなもよろしくな!」
「宜しくお願いします。」
糸川君が小さく会釈すると、何人かの女の子が黄色い声をあげた。
大きな拍手がフロアに響きわたる。
...さすが、糸川君。
でも、またあなたは遠い存在に...。
彼から目を逸らすことが出来なかった。
その時の私は、一体どんな表情をしていたんだろう。
席に着いた糸川君に、女の子たちが慌てて駆け寄る。
周りには人だかりができていた。
...相変わらず、凄い光景だ。
はあ、と息をつき書類に目を通し始める。
すると、影が覆いかぶさった。
不思議に思って見上げると、向こうで囲まれていたはずの糸川君。
驚いていると、彼は手に持っていた書類を差し出した。
「植野、すまないがこれもいいか。」
「あ、...はい。」
受け取ると、さっさと自分のデスクに戻って行く。
その後ろ姿に、慌てて
「おめでとうございます!」
と声を掛けた。
彼は振り返り、しばらく私と目を合わせたが
何も言わずに席へ戻って行った。

...よし。今日の仕事完了。
早く帰ろう!
カバンを肩に掛けて急いで出ようとすると、有美に上着を引っ張られた。
「なに?」
「それはこっちの台詞。なに慌ててんの。」
「ちょっと用事が。」
「用事?...まさか、」
その瞬間、有美が何を言おうとしたのか察しがついて
素早く彼女の口に蓋をした。
「ふごっ、...」
「違う。断じて違うから。」
「ふやふい...」
「怪しくない!とにかく、急いでるから。」
そう言って会話を無理矢理中断し、扉を開けて会社を後にした。
◇鳴き声◇End ...続く。
―――...なんか、顔が
変な感じ...、
あれ。私今起きてるんだっけ。...それとも、
いや...寝てるんだ。
でも、この頬の感触は、何?
......
舐められて...る?
パチッと目を覚ます。
目線を下にずらすと、ピンクの舌が飛び込んできた。
あまりに驚き、無言で飛び起きる。
するとその持ち主も私に驚いて後ずさった気配がした。
なになになに!?
パニック状態になりながら、ベッド近くの電気スタンドに手を伸ばし明かりを点ける。
いきなり明るくなった空間に思わず目を瞑ったが
眩しさに堪えながらも、微かに開けた。

そこには、耳と尻尾を伏せて悲しそうにこちらを見つめるこぎつね。
そうだった。
昨日の出来事をすっかり忘れてた。
なんて馬鹿な私...。
かわいそうに、怯えたかしら。
「ごめんね。」
さっき頬を舐めてくれていたのは、このこぎつねか...
そっと抱きあげ膝の上に置く。
せっかく慣れてきてくれたのに。
これがきっかけで怯えだしたらどうしよう。
頭を優しく撫でる。
...じっとしているから、大丈夫かも知れない。
――それにしても、
まだ辺りは暗い。
今は何時なんだろう。
目覚まし時計を見ると、朝の5時だった。
今日は朝イチで会議があるし...もう起きるか。
ベッド脇に足を下ろし、スリッパを履く。
こぎつねはもう少し寝かせておこうと毛布をかけたが
するりとベッドから下りて部屋を出て行ってしまった。
...そうだ。
狐のご飯も用意しないと!
トイレは前に猫を預かった時のトイレシートが残っていたはず。
パタパタとスリッパの音を立てながら台所へ向かった。

...狐って何食べるのよ。
冷蔵庫を漁るが、見当が付かない。
あ、昔話とかでは油揚げを食べるってあったな。
えーっと、“狐 食べ物”...っと。
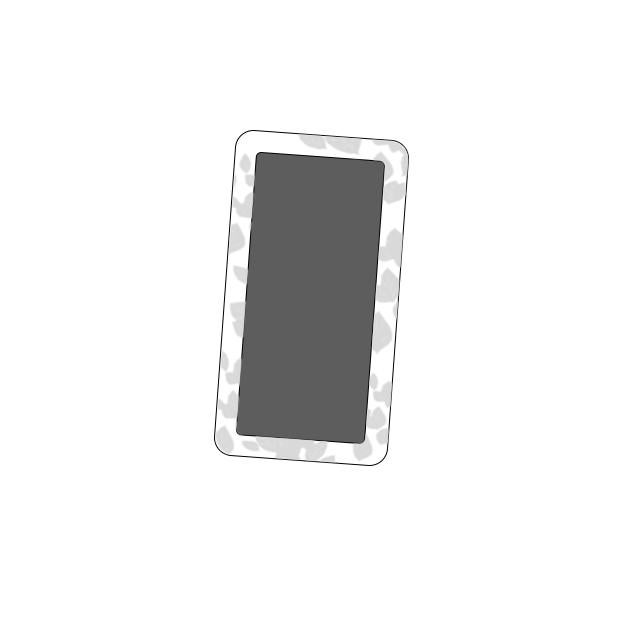
狐は雑食。
油揚げは食べることは食べる...か。
...。
一応、作ってみるか。
フライパンに二枚乗せて軽く焼く。
すると、いつの間にかこぎつねが足元まできていて、こちらを見上げていた。
......正解?

小さく切って皿に乗せ、目の前に差し出す。
すると匂いを嗅いだ後、少しずつ食べだした。
...よかった。
ひとまず、お昼ごはん用にも作って置いておこう。

朝食を済ませた後、身支度を整えた。
――早いけど、そろそろ行こうかな。
「こぎつねちゃん。」
クルッと振り返ったこぎつねに、目線が近くなるようしゃがんで話し掛ける。
「今から、出かけてくるね。」
「夕方には帰って来れるようにするから。」
伝わるわけないけど、と思いながらも話し掛ける。
でも。この狐は...どこか不思議なところがある。
本当は言葉が理解出来るのかも知れない。
だってほら、
こうしている間もじっと私の目を見つめている。
...。
「じゃあね。」
と、笑いかけて立ち上がった。
バッグを掴み、玄関へ進む。
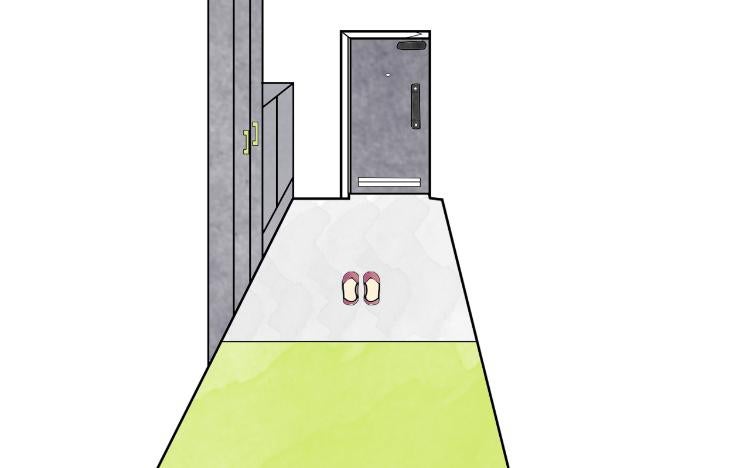
すると
「――キャワワッ」
...え?
今の鳴き声は...
もしかして、この子が?
振り返ると、フサフサの尻尾を振っている。
その愛らしい姿に自然とまた笑顔になれた。
「行ってきます!」

仕事をしながら、ボーッとこぎつねのことを考えていた。
その時、森高先輩の声がフロアに響く。
「みんな、聞いてくれ。」
その言葉に、一同が視線を向ける。
森高先輩の隣には糸川君が立っていた。
「この度、糸川君が統括部長に就任することになった!」
「社長直々の推薦だ。みんなもよろしくな!」
「宜しくお願いします。」
糸川君が小さく会釈すると、何人かの女の子が黄色い声をあげた。
大きな拍手がフロアに響きわたる。
...さすが、糸川君。
でも、またあなたは遠い存在に...。
彼から目を逸らすことが出来なかった。
その時の私は、一体どんな表情をしていたんだろう。
席に着いた糸川君に、女の子たちが慌てて駆け寄る。
周りには人だかりができていた。
...相変わらず、凄い光景だ。
はあ、と息をつき書類に目を通し始める。
すると、影が覆いかぶさった。
不思議に思って見上げると、向こうで囲まれていたはずの糸川君。
驚いていると、彼は手に持っていた書類を差し出した。
「植野、すまないがこれもいいか。」
「あ、...はい。」
受け取ると、さっさと自分のデスクに戻って行く。
その後ろ姿に、慌てて
「おめでとうございます!」
と声を掛けた。
彼は振り返り、しばらく私と目を合わせたが
何も言わずに席へ戻って行った。

...よし。今日の仕事完了。
早く帰ろう!
カバンを肩に掛けて急いで出ようとすると、有美に上着を引っ張られた。
「なに?」
「それはこっちの台詞。なに慌ててんの。」
「ちょっと用事が。」
「用事?...まさか、」
その瞬間、有美が何を言おうとしたのか察しがついて
素早く彼女の口に蓋をした。
「ふごっ、...」
「違う。断じて違うから。」
「ふやふい...」
「怪しくない!とにかく、急いでるから。」
そう言って会話を無理矢理中断し、扉を開けて会社を後にした。
◇鳴き声◇End ...続く。


