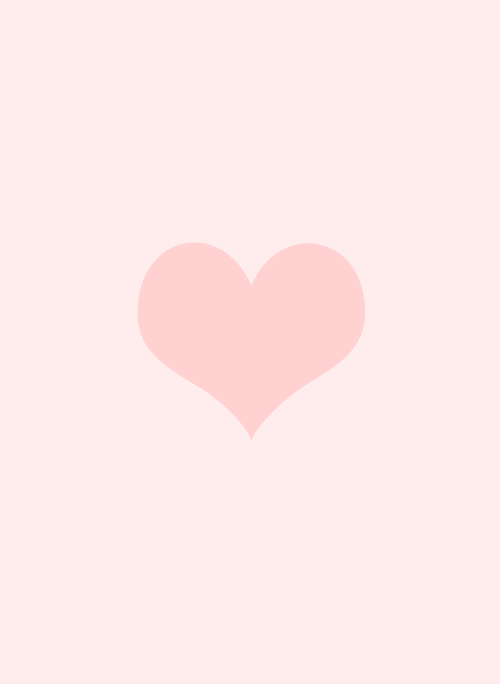「でも、これは全部、ぼくのせいだ。きみはちっとも悪くない。最初に嘘をついて、仕掛けたぼくが、一番悪い。あの歌を作ったのは、ぼくじゃないから」
「――それじゃあ、誰が、あの歌を作ったの?」
蒼くんが、この場所で、目の前で、歌ってくれた。
でも、わたしは、いつからか、そのことに違和感を覚えていた。
そして、もしかしたら、という気持ちが大きくなっている。
「ぼくは、彼が歌を作っているときに、たまたまそばで聴いていたんだ。そして、ぼくが勝手に歌っていただけ。その歌に惹かれて寄ってきたきみを、ただ、彼に渡すのがいやで、彼よりも先に、ぼくが付き合おうって言ったんだ」
「え……」
「でも、悔しいなあ。感性が合うふたりってのは、こうも無自覚に惹かれあって、響きあうんだね。ぼくがそばにいるのに、きみの目は、あいつの姿を探しているなんて」
「蒼くん……」
「――それじゃあ、誰が、あの歌を作ったの?」
蒼くんが、この場所で、目の前で、歌ってくれた。
でも、わたしは、いつからか、そのことに違和感を覚えていた。
そして、もしかしたら、という気持ちが大きくなっている。
「ぼくは、彼が歌を作っているときに、たまたまそばで聴いていたんだ。そして、ぼくが勝手に歌っていただけ。その歌に惹かれて寄ってきたきみを、ただ、彼に渡すのがいやで、彼よりも先に、ぼくが付き合おうって言ったんだ」
「え……」
「でも、悔しいなあ。感性が合うふたりってのは、こうも無自覚に惹かれあって、響きあうんだね。ぼくがそばにいるのに、きみの目は、あいつの姿を探しているなんて」
「蒼くん……」