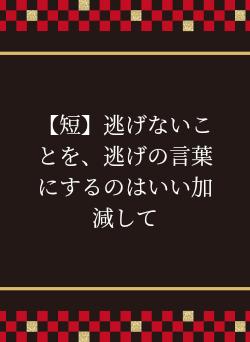「…ねぇー?もう帰るのー?」
仄暗いホテルの一室で、激しい情事の後に熱いシャワーを浴びてバスルームから出て来れば、ごそごそとワイシャツに腕を通し、無造作に髪を掻き上げている彼がいた。
私はつまらない、と言った様に甘えて彼に近付こうとする。
けれど…。
「圭子…やめろよ」
と、素っ気なく止められた。
それでも私はムッとすることもなく、彼のまだ少しだけ濡れている髪を指で漉いていく。
「やーめない。いいじゃない。どうせお人形サンが待ってる家に帰るだけデショ?」
そう言った私に向けて、彼はふっと息を吐き私を見つめて来た。
「あいつは、そんなんじゃ…」
「へぇ?そう。じゃあ帰れば?その代わり、…私苛めちゃうかもよ?あのなーんにも知らないお姫様に」
「圭子、俺が悪い、だから…やめてくれ」
違う。
そんな言葉が聞きたいんじゃない。
それなのに、どうしてこの人には私の気持ちがこれでもかと言うくらい、伝わらないのだろう?
「んー…つまんないなぁ?駿てばそんなキャラだっけ?人の事抱いてる時は、あんなに理性飛ばしてる癖にね?可笑しくない?」
私のこの裏腹の言葉達に早く気付いて…。
じゃないと、私の方が壊れてしまうから。
「そんな風に言うなよ。俺は…真剣に…」
「真剣に、何?」
「…いや…その」
「…しゅーん?逃げないでよ、今更じゃない。こんな事。真剣に…の先は?彼女を愛してるとか?…はっ、馬鹿にしてんの?」
ぐいっ
締め掛けたネクタイを強引に掴んで、背けている顔を此方に向かわせた。
「奥さんいるって…最初から言えばよかったじゃない」
「圭子、それは…」
「そうよねぇ?彼女と私じゃ天と地…?ううん、違うわね…華と毒程の差があるものね?…いいわ、別れてあげる」
とすっ
握り締めていた、ネクタイをぱっと離して彼をベッドに投げ出す。
私は冷たい視線を投げて、彼を見下す。
そんな私に許しを乞うようにして、彼は私の手に触れようとした。
それを、ぱしっと叩き落として吐き捨てるように呟いた。
「縋りつかないでよ、みっともない」
それを聞いた彼は、真っ青な顔をして言葉を失った。