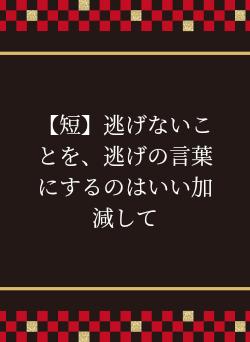それは…ぬるりとした、生温かい風が全身に吹き抜けた瞬間だった。
私より少し背が低くて、笑うと片方の頬にえくぼが出来る、清楚で可愛らしい人。
だけど、何処か幼さが滲み出ている、単純な人。
それが、私の第一印象。
あぁ、私とは真逆だな。
直感的にそう思った。
そして、私は彼の理想の世界からは掛け離れていると言う事も…。
どれだけ体を重ねても、熱を交わし合っても、けして告げられない「愛してる」の六文字。
それが最初は不満だった。
でも…。
それ以上に情欲の方が勝ってしまい、最終的に如何でもいい事になっていった。
…本当は分かっていたのかもしれない。
けれど、私のなけなしのプライドがそれを認める事を許さなかったのかもしれない。
「そろそろ潮時かな…」
呟いた言葉はカラカラに乾いて…やっぱり、彼に対する情愛がまだ亡霊のようにして、この心に取り憑いている事を痛感させられた。
生温かい風。
大嫌いな憂鬱をもたらす、季節。
気圧の乱高下が酷く、混沌とする…全て。
私は彼の好みのまま伸ばしに伸ばした、ストレートの髪をジェルネイルで彩った爪で乱暴に引っ掻いて、溜息を吐いた。
「でもさ、嘘付くならとことん付き合ってやろうじゃないの」
チリチリと焦げた心は、ひしゃげて真っ黒く染まって行く。
誰が、泣くものか。
馬鹿馬鹿しい。
欲しい物はどんな手段を使ってでも、手に入れる。
それが、例え誰かを傷付けようとも。
誰かを泣かせようとも。
ドス黒い雲を追うようにして、私はなんでもない事のように、先を歩く二人を追い越し『偶然』を装った演技をした。
「あ、こんばんは。園部主任、お疲れ様です」
「え…、あ、あぁ。そっちこそ、お疲れ様」
可笑しいくらいの、動揺。
その瞳は、私達の関係を露呈していること間違いなしだ。
どうしてここへ?
なんで声を掛けてきた?
物語る彼の視線。
私はそれを完全に無視して、隣にいる彼女へと声を掛けた。
「随分と可愛らしい方をお連れですね?あ、もしかして"彼女"さんですか?」
そう言った瞬間に、彼女の頬がカッと赤くなった。
「私は…」
その後を接がせない為に、一呼吸置いてからにっこりと微笑んだ。
「あれ…?主任?主任に妹さんていましたっけ?」
その一言に、彼女の口元がぎゅっと歪む。
でも、私のその一言にすっかり動転してしまっている彼は、私の問い掛けに思う様に応えられず、ただただ、狼狽えるばかり…。
「ふふ。まぁ、どちらにせよ私はお邪魔ですね。それじゃあ…失礼しまーす」
ふんわりと、笑い掛け颯爽と踵を返して前を向く。
虚しさよりも、その時私は何故か恍惚としていた。
ズタズタになればいい。
私を裏切ったのは、其方の方。
だったら、罰を受けるのは当然の事でしょう?
私は持ってたミニショルダーバッグの持ち手を、少し腕に巻いてくるくると振り回して鼻歌を歌った。
…追い掛けて来ない、彼に対して少しの胸の塊を持ちながら。