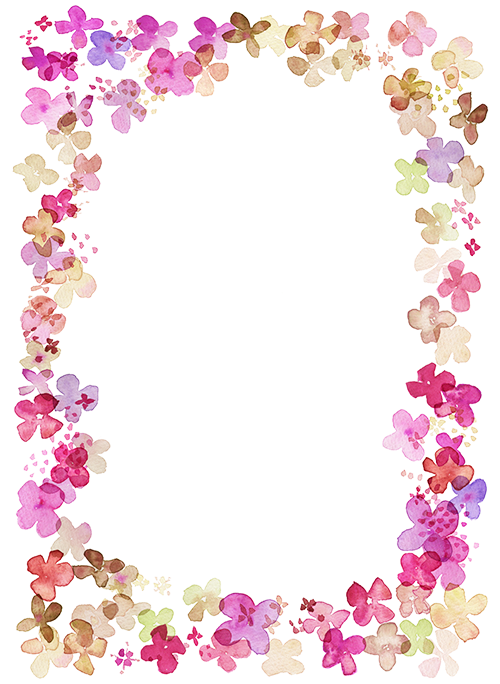「嘘……。だってお兄ちゃんは私のこと……」
「ずっと前から、好きだったよ。初めて気持ちに気付いたのは、おまえが中学生の時だった」
そんなはずない……。
だってその頃の私は本当に子どもで。
大人びたお兄ちゃんに追い付きたくて、いっぱい背伸びした。
でもどんなに頑張っても、お兄ちゃんは私のこと、幼馴染としか見てくれなくて。
「最初は四歳も年下の幼馴染にどうかしてる、って自分を誤魔化していた。でも高校生になったおまえは、会うたびに綺麗になっていって――気持ちを抑えるのに精一杯だった。大学の途中から、俺は消防士になろうと決めていたし。命を張る仕事だ。万が一おまえを悲しませるようなことになったらと思うと、勇気が出せなかった。それで、おまえからの連絡も次第に返さないようにして離れようと思ったんだ」
私を離すと、お兄ちゃんはじっと見つめてきた。
微かに紅潮しているように見えるその顔からは、いつものような毅然としていて冷静な様子が消えていた。
どこか緊張しているようで、余裕のなさまで感じる……。
「……困らせるなよ。泣いても綺麗だなんて、違反だぞ」
お兄ちゃんは、私の顔を大きな両手で包んだ。
「ずっと前から、好きだったよ。初めて気持ちに気付いたのは、おまえが中学生の時だった」
そんなはずない……。
だってその頃の私は本当に子どもで。
大人びたお兄ちゃんに追い付きたくて、いっぱい背伸びした。
でもどんなに頑張っても、お兄ちゃんは私のこと、幼馴染としか見てくれなくて。
「最初は四歳も年下の幼馴染にどうかしてる、って自分を誤魔化していた。でも高校生になったおまえは、会うたびに綺麗になっていって――気持ちを抑えるのに精一杯だった。大学の途中から、俺は消防士になろうと決めていたし。命を張る仕事だ。万が一おまえを悲しませるようなことになったらと思うと、勇気が出せなかった。それで、おまえからの連絡も次第に返さないようにして離れようと思ったんだ」
私を離すと、お兄ちゃんはじっと見つめてきた。
微かに紅潮しているように見えるその顔からは、いつものような毅然としていて冷静な様子が消えていた。
どこか緊張しているようで、余裕のなさまで感じる……。
「……困らせるなよ。泣いても綺麗だなんて、違反だぞ」
お兄ちゃんは、私の顔を大きな両手で包んだ。