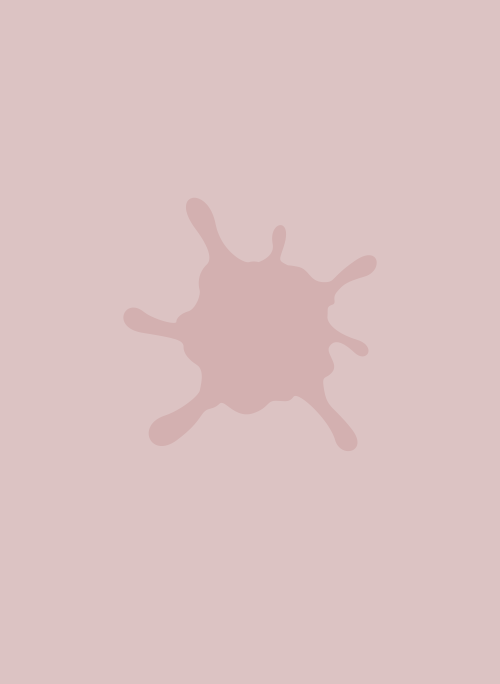よく分かったよ。この世界が何なのか。
本当に「素敵」なワンダーランドで嬉しいね。
まさか。
まさか、よりにもよって。
「『玉響』が生きている世界」を、俺に見せるなんて。
…この、くそったれが。
「え!?す、すぐり君!?」
驚いたツキナが、じょうろを取り落として立ち上がった。
でも、俺はそれに構わない。
この世界は、間違いなく異次元世界。
魔封じの石が作った、偽物の世界。
従ってこのツキナも、偽物だからね。
偽物に構っている暇はない。
俺は今すぐにでも、このクソみたいな世界を壊さなければならない。
『玉響』が生きているなんて。
彼が生きて、一緒にイーニシュフェルト魔導学院にいるなんて。
園芸部で、ツキナを交えて、一緒に活動してるなんて。
そんな世界は、絶対に有り得ないのだから。
終わる。終われ。終わってしまえ。こんな夢。
何度も夢に見て、そうだったら良いなと思い続けた、まさに夢のような世界。
でもそれは、夢でなくてはならないのだ。
決して現実のものになってはいけない。
そんな仮初めの世界に、何の価値もないのだから。
「や、『八千歳』…!なに、す…」
『玉響』が、苦しそうにもがいた。
どうでも良い。
「…君は、死んでなきゃならない存在なんだ…」
それが正しい世界の在り方。
それが本来の世界の在り方なんだ。
俺は、君を殺したことに罪悪感しか感じてないけど。
それでも、君が生きてちゃ駄目なんだよね。
「死んだ者が…生き返っちゃ駄目なんだ…!」
これ以上。
これ以上、何も知らない他人の分際で。
これ以上、『玉響』の死を穢すような行為を、俺は許さない。
…許さないよ。絶対に。
…しかし。
「…っ」
『玉響』の襟首を掴む俺の腕に。
グサリと、クナイが突き刺さった。
「…何してるの?『八千歳』」
「…『八千代』…」
クナイが投げられた方向には、『八千代』が立っていた。
真剣な顔つきで、今度は小太刀に手を回していた。
本当に「素敵」なワンダーランドで嬉しいね。
まさか。
まさか、よりにもよって。
「『玉響』が生きている世界」を、俺に見せるなんて。
…この、くそったれが。
「え!?す、すぐり君!?」
驚いたツキナが、じょうろを取り落として立ち上がった。
でも、俺はそれに構わない。
この世界は、間違いなく異次元世界。
魔封じの石が作った、偽物の世界。
従ってこのツキナも、偽物だからね。
偽物に構っている暇はない。
俺は今すぐにでも、このクソみたいな世界を壊さなければならない。
『玉響』が生きているなんて。
彼が生きて、一緒にイーニシュフェルト魔導学院にいるなんて。
園芸部で、ツキナを交えて、一緒に活動してるなんて。
そんな世界は、絶対に有り得ないのだから。
終わる。終われ。終わってしまえ。こんな夢。
何度も夢に見て、そうだったら良いなと思い続けた、まさに夢のような世界。
でもそれは、夢でなくてはならないのだ。
決して現実のものになってはいけない。
そんな仮初めの世界に、何の価値もないのだから。
「や、『八千歳』…!なに、す…」
『玉響』が、苦しそうにもがいた。
どうでも良い。
「…君は、死んでなきゃならない存在なんだ…」
それが正しい世界の在り方。
それが本来の世界の在り方なんだ。
俺は、君を殺したことに罪悪感しか感じてないけど。
それでも、君が生きてちゃ駄目なんだよね。
「死んだ者が…生き返っちゃ駄目なんだ…!」
これ以上。
これ以上、何も知らない他人の分際で。
これ以上、『玉響』の死を穢すような行為を、俺は許さない。
…許さないよ。絶対に。
…しかし。
「…っ」
『玉響』の襟首を掴む俺の腕に。
グサリと、クナイが突き刺さった。
「…何してるの?『八千歳』」
「…『八千代』…」
クナイが投げられた方向には、『八千代』が立っていた。
真剣な顔つきで、今度は小太刀に手を回していた。