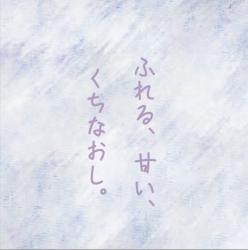「はぁ……っはぁ。」
荒い息づかいも関係ないような気がしてきた。
六月十一日の今日はもしかしたら記念すべき日になるのかもしれない。
見慣れた校門にはまだ生徒が大勢いて少しだけ胸がホッとした。
「うわー朝から篠塚見るとか最悪だわ。」
「よく学校来れるよねー?」
いくら時間が経ったって私へのウワサは消えてない。
けど、それ以前に仁村たちのことで頭はいっぱいの私にはそんなの聞こえていなかった。
走る足のスピードをだんだんと遅くして教室まで向かった。
荒い息づかいも関係ないような気がしてきた。
六月十一日の今日はもしかしたら記念すべき日になるのかもしれない。
見慣れた校門にはまだ生徒が大勢いて少しだけ胸がホッとした。
「うわー朝から篠塚見るとか最悪だわ。」
「よく学校来れるよねー?」
いくら時間が経ったって私へのウワサは消えてない。
けど、それ以前に仁村たちのことで頭はいっぱいの私にはそんなの聞こえていなかった。
走る足のスピードをだんだんと遅くして教室まで向かった。