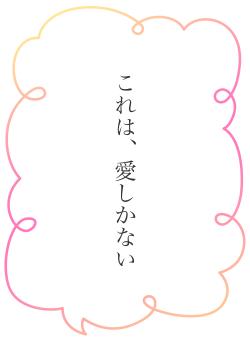先輩が照れた表情なんて、初めて見た。
私の言葉で先輩の心が自分に向きかけているのかもしれない。
少しでも、私のことを意識してくれているのだと思うとなんだか嬉しくなってくる。
「先輩が喜んでくださるなら、そのっ…私、沢山先輩の心を掴みたいです…!」
「!?」
自分でも何を言っているのかわからず、湯気が出そうなくらい体温が上昇していく。
「かっこ悪い先輩も、かっこいい先輩も素敵ですし…」
「あの、萩ちゃ──…」
「笑った顔も照れた顔も、かっこ悪い所を見せたくない…と考えてる先輩も含めて、全部が愛おしいと思ってます…!!」
さりげなくとんでもない発言をしてしまったことにも気づかないまま、話を続けようとすると、
「萩ちゃん…!」
先輩の慌てた声によって、遮られる。
「…あの、もう、わかった、から……勘弁してください……」
両手で顔を覆う先輩が目に焼き付いて、何故だか身の置きどころがない空気に包まれる。
「…? あれっ…??」
お互い、よく熟れたトマトのように顔全体が真っ赤に染まっていく中、
───コトンッ。
ぶどうゼリーの容器が机から落ちる音がした。