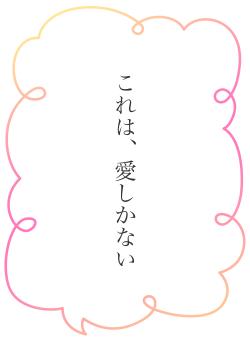「好きな人の悪口言われたらムカつくし、誰でも怒るだろ」
「俺も実際にそういう時あったし…」と、玲太くんは視線を足下に落とした。
玲太くんの言葉を聞いて、私は首を傾げる。
「……玲太くんって、好きな人いるの?」
そういえば、彼の浮いた話を一度も聞いたことがない気がする。
小学生の頃からたくさんの女の子たちに告白されている場面は何度も目撃していたし、告白される度に玲太くんは『ごめん』と断っていた。
同級生の子たちは皆、玲太くんのことを『かっこいい』と言っていたっけ。
私から見て、玲太くんがかっこいいかどうかはわからない。
だけど、彼に好きな人がいるというのは初耳だった。
「す、好きな人って…今もその人のことが好きなの?」
「……」
「誰のことが好きなの!?」
「おまえには教えない」
「え"っ…!?」
ガーンッ…とショックを受ける私を差し置いて、玲太くんはポケットから鍵を取り出し、私の手の平の上に乗せた。
よく見てみると、私の家の合鍵だった。