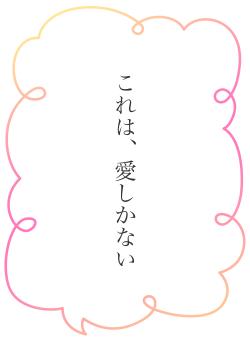あぁ、そうなのか。
そういうことなのか。
お母さんが苦しんでいた原因は、全て私なのだと。
私が生まれたから、私が生まれてこなければ、お母さんを苦しめることにはならなかったのに───…。
「…そっか。でもおれ、いやだよ。萩ちゃんがいなくなるなんて、絶対いや」
「ご、ごめんなさい。今はもう普通に楽しく元気に過ごしてるので大丈夫です…」
ぐいっと口角をむりやり上げて笑いかけたが、先輩はどういった感情なのかわからない表情で私を真っ直ぐに見つめる。
「『どうか、自分のこと否定しないで』」
「えっ…」
「そう言ってくれたのは、萩ちゃんだよ」
今の先輩の表情は、無表情だ。
怒っているわけではないことくらいはわかる。
だって、私を見つめる先輩の瞳が優しかったから。
「『自分がいなかったら』とか『消えたい』とか、そんな悲しいこと言わないでよ」
先輩の手がそっと私の頭に乗せられた。