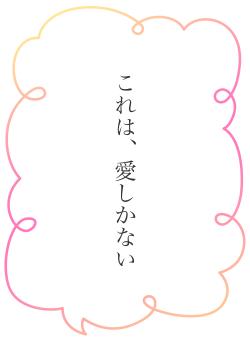「あのね」と、先輩は話を続ける。
「永遠、いるでしょ?萩ちゃんが聞いてた時の話はちょうど永遠と永遠の好きな子が険悪な関係になってた時期?だったっていうか、おれがその2人の間にいるのが結構気まずくてさ。何か雰囲気が明るくなることはできないかって必死に考えて、最終的にたどり着いたのが『セフレにしよう』って言葉しか出なかったわけなんだけど……」
先輩は、体ごと私の方へと向けて、ソファーの上で正座をする。
「あの時、萩ちゃんが何であんな暗い顔してたのかも今頃気づいた。誤解させてしまった上に、萩ちゃんを傷つけてごめん。本当にごめんなさい」
「セフレはマジでいないから!」と付け足して、先輩は頭を下げながらもう一度謝った。
「……あっ、わ、私も、先輩の話を聞かずに避けたり、勝手に連絡先を消してごめんなさい…」
「いや、完全に悪いのはおれの方だし…」
「はい。先輩が悪いです」
「うん、だから──…って、萩ちゃん??」
ソファーから降りて、先輩を見下ろすように立ちはだかり、不思議そうに見上げる先輩の頬を両手で包み込んだ。
ゆっくりと口を開いて、「先輩」と言葉を紡ぐ。