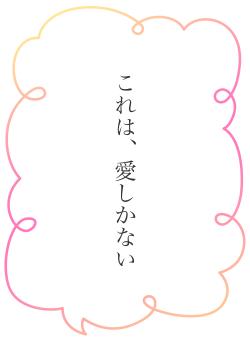先輩の手は温かくて、握られた部分から少しずつ、じわじわと熱を帯びていく。
「……」
「……」
数秒程、お互いに見つめ合っていたが、何故だか恥ずかしくなってきて、2人同時に目を逸らしてしまう。
だけど、どうしても先輩の顔が見たくて、ゆっくりと視線を戻すと、再び先輩と目が合った。
その瞬間、ドクンッ…と心臓が飛び跳ね、徐々に早鐘を打っていく。
──『おれも、会いたかった』
そう言ってくれた先輩の言葉が嬉しくて、カァッ…と頬が熱くなった。
口角が緩み始めてきて、ニヤけているのをバレないよう、握られている手に視線を落とす。
すると、頭上から「…うぁーっ、どうしよ……」と、唸るような、悩ましげな声が降ってきた。
「……おれ、このまま萩ちゃんとバイバイしたくないんだけど」
「せっかく久しぶりに会えたのに…」「あっ、でも帰らなかったらお家の人に迷惑か…」と、先輩はブツブツ言いながら離したくなさそうに握る手の力を少しだけ強める。
どうやら、先輩は帰りたくないらしい。