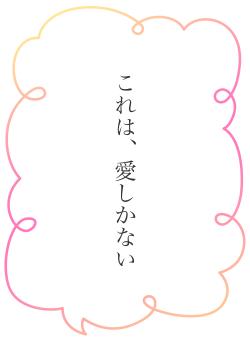学校が同じだから、きっとどこかで会ってしまうかもしれないが、できるだけ校内は出歩かないようにして、もし先輩が教室にやって来たら、いないフリをするか、お手洗いに直行するか、明日からはどの方法でやり通すのか考えていく必要がある。
「……恋愛はもういいのかよ」
「あー…うん。しばらくは……っていうか、しないかな。真ちゃん先輩以上に好きになれるような人、見つかる気がしないし…」
「……」
一瞬だけ、玲太くんの表情が曇ったように見えたが、すぐさま眉間にしわを寄せて、険しい顔つきへと変わっていく。
「おまえさ、目覚ませよ。深森先輩みたいないい加減な男なんか好きになったって、最終的に自分自身が傷つくだけだろ。結局、今だってそうじゃねえか。ああいうやつはろくでもない人間なんだから、そんな男のことさっさと──…」
私は、玲太くんの話を遮るように、ガタンッと椅子から立ち上がり、彼の胸ぐらを勢いよく掴んだ。
その衝撃で、水が入っているグラスの中の氷がからりと音を立てる。