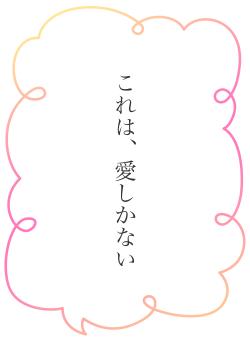「ね〜え、シンシン。今好きな子いるんでしょ〜?最近その子とはどうなのぉ?」
────は…?
再度、目を大きく見開いた。
この人、今何て言った?
好きな子?
どういうこと…?
先輩の方を見ると、本人は一切動揺することもなく、否定する素振りもせずに、ただ少し険しい顔つきで「うるさいな」と、一言答えるだけだった。
「おれ、今この子と話してるから、どっか行ってくんない?」
「えー、なんなのその態度〜(笑)」
「ずいぶん生意気になったじゃーん」
「……」
ベタベタと先輩の腕に触れる女の人たちに怒りが込み上げてくる。
先輩は優しいから、女の子が先輩に触っても振り払おうとしない。
私が先輩の小指を握りたいと言った時も、彼は拒まなかった。
私もこの人たちと同じ扱いだったんだ。
その内の1人にすぎなくて、先輩にとって特別ではなかった。
以前、私は先輩のタイプに含まれているかどうか聞いたことがあり、『入ってる』と答えてくれたけれど、それは先輩なりの気遣いだったのだと改めて気づかされた。
「……っ」
この場からさっさと離れればよかったのに、私はゆっくりと手を伸ばしていて。