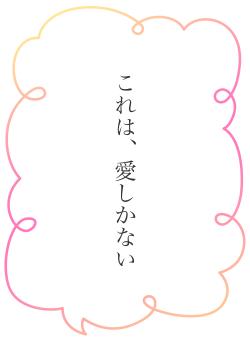グッと親指を上に立てて、ウインクをする先輩からバチコーンッ☆という、効果音が鼓膜に届いたような気がした。
「んなはは〜っ!」と笑う先輩に、私は呆然と立ち尽くした。
圧倒的陽気なオーラを放つ先輩が眩しくて、このまま灰になってもおかしくはないと思うほど、先輩は輝いていた。
「あっ……なんか、スミマセン…。早とちりした挙句、年下の分際で偉そうなことたくさん言っちゃいました…。私の発言はどうか忘れてくださると幸いです…」
「えー、なんで?やだよ、忘れたくない」
「わずれでぐだざいっ…!!」
一刻も早く、数分前の記憶を消し去りたい。
なかったことにしてほしい、と必死に訴えたが、先輩は首を横に振って、「絶対忘れない」と言い張った。
「だって、おれは大切な人たちから愛されてるんだって、恵まれてるんだって改めてわかったし。それに、今のおれがいるのは、萩ちゃんのおかげでもあるんだよ」
「……えっ、私、ですか?」
心当たりがなくて、何か先輩にしただろうかと一生懸命思い出そうとしていると、先輩がクスッと笑みをこぼす。
「さっきも話したけど、萩ちゃんが『先輩の笑顔が好き』って言ってくれた時から、なんか救われたような気分がして、心がスッと軽くなったんだよね〜」