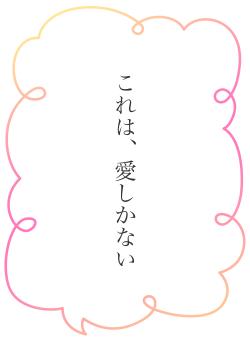最後まで言い切った瞬間、目頭が熱くなっていき、堪えていた涙が一気に溢れ出してしまう。
子どもみたいにポロポロ涙を流す私を見た先輩は、ギョッとして慌てながらもハンカチを貸してくれた。
「な、なんかごめん。泣かせるつもりなかったんだけど…」
「ゔぐふっ…。ごぢらごぞ、ずびばぜん…!でもごれは涙じゃないので安心じでぐだざい……」
「それは無理があるよ、萩ちゃん…」
「ゔっ…。で、でも本当のごどなので……」
「うん、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい」
先輩は、体ごと私の方に向けて、フッとやわらかく微笑んだ。
「あー…まあ、さっきは昔のこと話して、チヤホヤされたかったーとか、必要とされてないのやだーとか言って、しんみりとした空気作っちゃったけど、今はもう全然気にしてないから大丈夫だよ」
ケロリとした顔で言う先輩に、私は「えぇっ??」と間抜けな声を出す。
「さっき萩ちゃんに言われて気づかされたこともあったけど、今は好きなように生きてるし、普通に楽しいって思ってるし?最近まで色々悩んでたこともあったけど、落ち込んでたって時間の無駄だし、とりま、気楽にいきまっしょい!って思いながら毎日充実した生活送ってるよんっ☆」