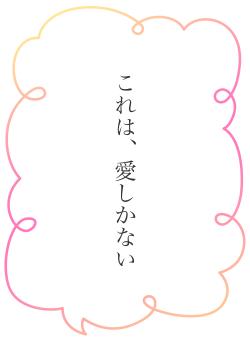「小学生の時も、中学生の時も、周りはみんな永遠のことしか視界に入れてくれなくて、隣にはおれもいるのになぁ…て。『誰もおれのこと眼中にないんだなぁ…』『だれもおれの顔覚えてくれないんだなぁ…』とか、みんな、いつもおれのこと『永遠と一緒にいる人』としてしか認識してくれないんだなぁ…とか考えてたら、なんか寂しくなってきて、もう何もかもどうでもよくなった時には、適当に女の子に声かけて、ベッドの上で何の感情ももっていない相手と肌を合わせてた。それ以降は、できるだけ愛想よくしようと、ヘラヘラ笑いながら生きるようになったってわけ。……まあ、これは、おれも永遠みたいにみんなからチヤホヤされたかったなあ…って話なんだけど…」
「永遠の話してたのに、いきなり自分語りしちゃってごめん」と、先輩は困り顔を浮かべながら謝った。
校内で真ちゃん先輩と会う度、
──『どしたの、萩ちゃん。もしや永遠に見惚れちゃった〜?』
──『あっ、永遠に会いに来た?』
と、よく日山先輩の名前を出していることが多かった。
「……真ちゃん先輩は、日山先輩のこと、今でも好きですか…?」