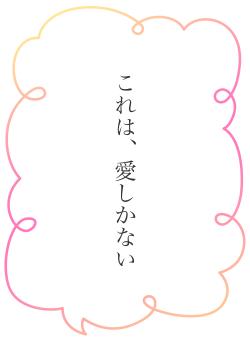「わ、わたしおいしくないんで……」
「? だいじょぶだよ?」
「大丈夫じゃないよ…!」
成り立っていない会話に気づく暇もなく、ゆうくんのおじさんの姿を勝手に想像した。
叔父が2人いて、ゆうくんより大きいということは、2人とも20歳以上の男性の可能性が高い。
サングラスをかけ、片腕には大きな刺青が入っているスキンヘッドのおじさんだったらどうしよう。
『ワシの甥っ子に何してくれとんじゃ!!』とか、問答無用で殴りかかってきたら終わりだ。
せめて、普通の見た目をした人が来てくれますように。
極道みたいな人が来ませんように…!!
「おねいちゃん、おえかきしよ〜!」
「かめんらいだーかいて〜」と、ゆうくんの無茶振りに答えることもできず、萎縮しながら待つこと数分後───…。
「悠!!」
どこかで聞き覚えのある、焦ったような声が鼓膜に届いた。
「あっ、おじちゃん!」
反射的に振り返ると、目の前にいる人物が視界に映り、思わず息を呑んだ。
───まさか、会えるとは思わなかった。
「しんちゃん、せんぱい…」
私にそう呼ばれた本人も驚いた表情で、「えっ、萩ちゃん…?」と、ぱちくりと何度か瞬きをしていた。
私のことを、"萩ちゃん"と呼ぶのは、真ちゃん先輩しかいない。
「あっ、えっと……ひさしぶり…」
「へぁっ、あっ、ひゃいっ……」
久々に会う先輩は、私服姿というのもあるのか、なんだか少し大人びているように見えた。