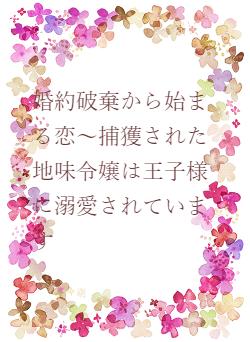「じゃあ、認めるのだな。エマに嘘を吹き込み信じ込ませたうえで、犯行を唆したことを」
「ち、違います。犯行を唆すだなんて、そんなことはしておりませんわ」
わたくしはそんなことを言った覚えはない。誘拐だなんて思いつきもしなかったわ。なのに、何故わたくしが疑われなくてはいけないの。
父親から犯罪を疑われるなんて情けない。唇を噛むと握っていた扇子をギュッと握りしめた。
「わしだって、我が娘を疑いたくはない。しかし……」
「お父様、信じてくださいませ。わたくしはエマに誘拐のことなど話していませんわ。もしやったとしたらエマの独断です。本当です。わたくしは何もしておりません」
共犯だと思われてはたまらない。わたくしは無実よ。必死に弁明してお父様に訴えた。
「そうか。だが、エマに嘘をついていたことは認めるのだな?」
「そ、それは……はい。申し訳ございません」
「認めるのだな」
嘘だとわかってついた嘘。念を押すお父様に潔くわたくしは頭を下げた。
「ガーデンパーティーで出会ったのも殿下と恋仲で西の宮で会っていたのも、結婚の約束も指輪を贈られたのも、全部嘘だったのだな」
こうして他者から自分のついた嘘を並べられると羞恥で身の置き所がなくなってくる。冷静に言葉を紡ぐお父様になおさら顔があげられなかった。