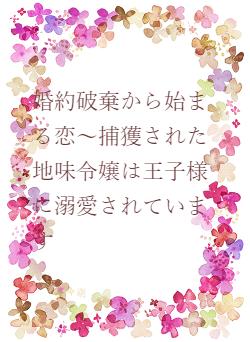「忙しかったのね。ごめんなさい、そんな時にお邪魔しちゃって」
謝るわりには悪びれた様子もなく、澄ました顔で扇子で首元をあおいでいる。気を使って遠慮するっていう気持ちは毛頭ないんだろうな。
「いいよ。で、用事は何?」
「あら、あら、あら。そんなにとがらなくてもいいのではないの? 機嫌が悪そうだけれど、何かあったのかしら?」
「何もない」
「そう? だったらよいけれど」
深く追求するつもりはないのか、軽く流したディアナは運ばれてきたカップを手に取り、紅茶の香りを楽しむと口をつけた。
一連の所作は見惚れるくらいなのだが、途切れた会話が何か含みを持たせているようで妙な緊張感を生む。