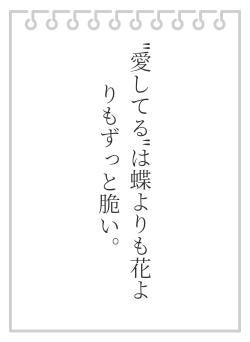お風呂場が恐ろしいほどの沈黙に包まれ、それを破ったのは智明くんの方だった。
「やっと思い出してくれたんだ。じゃあ、尚更語らないとね?」
「心の中にしまっておいてください」
あの夜のことを話すって考えただけで顔が熱いし、改めて何があったかなんて知りたくもない。
どうせならなかったことにしてしまいたいと、心の底から願った。
「蛍、こっち向いて」
「嫌です、向きません」
「こっち向けって」
「んっ⋯!?」
智明くんに何をされているのか考える時間、0.5秒。
唇に柔らかい感触があって、キスされてるんだと理解した。
そうだ、あの日もこんな風に優しいキスから始まったんだ。
「蛍、顔真っ赤にして可愛いね」
「智明くんこそ、真っ赤でしょ」
「お風呂場だからね、暑いんだよ。蛍はたしか、耳が弱かったよね」
「ちょ、それはッ⋯」
耳朶を甘噛みされ、思わず身をよじる。
耳だけは本当に弱いから、なんとしてでも回避しなきゃ。
「蛍、逃げないで。俺に体預けて欲しい」
「やっ、無理⋯」
「大丈夫、怖くないからね」
あぁ、どうして智明くんの声はこんなに安心するんだろう。
心の底から大丈夫だと思えるような、全て任せてもいいと思えるような声だ。
「やっと思い出してくれたんだ。じゃあ、尚更語らないとね?」
「心の中にしまっておいてください」
あの夜のことを話すって考えただけで顔が熱いし、改めて何があったかなんて知りたくもない。
どうせならなかったことにしてしまいたいと、心の底から願った。
「蛍、こっち向いて」
「嫌です、向きません」
「こっち向けって」
「んっ⋯!?」
智明くんに何をされているのか考える時間、0.5秒。
唇に柔らかい感触があって、キスされてるんだと理解した。
そうだ、あの日もこんな風に優しいキスから始まったんだ。
「蛍、顔真っ赤にして可愛いね」
「智明くんこそ、真っ赤でしょ」
「お風呂場だからね、暑いんだよ。蛍はたしか、耳が弱かったよね」
「ちょ、それはッ⋯」
耳朶を甘噛みされ、思わず身をよじる。
耳だけは本当に弱いから、なんとしてでも回避しなきゃ。
「蛍、逃げないで。俺に体預けて欲しい」
「やっ、無理⋯」
「大丈夫、怖くないからね」
あぁ、どうして智明くんの声はこんなに安心するんだろう。
心の底から大丈夫だと思えるような、全て任せてもいいと思えるような声だ。