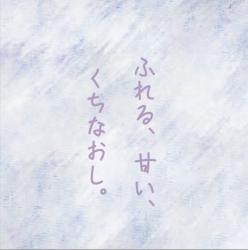****
それから一時間後。
お母さんに買い物を頼まれた私は真っ赤な目のまま外に出た。
あの後、結局は家に帰って枯れるまで泣いた。
大丈夫、もう吹っ切れたんだから。
今も無理矢理そう言い聞かせている。
そうしてボーッと近くのスーパーに寄って言われたものを買ってきた。
野菜やお肉、ジュースやお菓子。
少し重たいエコバッグを持ってまた家に戻る。
後は戻るだけ。
だけど、少し休憩したくなった私は近くの公園まで歩いた。
ベンチに荷物を置いて座る。
「はぁ。」
行き場の無いため息をついた。
少し錆びているベンチは冷たい。
だけども、それより空気が暖かった。
「──────小町?」
そう呼ばれた瞬間、さっきまで暖かかった空気が一気に冷めていった。
この声──────。
分かってる。だけど振り向きたくない。
雪くんの顔を見ると、涙が出ちゃうから。
「あれ?小町だよな……?」
するのベンチに座っている私の顔を覗き込むようにして座った。
「やっぱ、小町じゃん!
俺って気付かなかった?あ、聞こえなかったのか。」
そう言う声色は普段と違って穏やかでなんだか弾むような感じだった。
「─────雪、その子は?」
雪くんの隣から聞こえた声。
あぁやっぱり。
誰も優しくて頼りになってカッコいい雪くんをフるはずない………っ
そう気付いてしまった私は胸がズキズキと痛んだ。
そして、枯れるまで泣いたのにまた、涙が出そうになった。
「俺の恩人。
告白を手伝ってくれたんだ………」
照れているのか声はだんだん小さくなっていった。
「………」
私はどうしようも出来ずに、ただ座っているだけの置物だった。
もはや、二人にとっては荷物なのかもしれない。
こんなこと考えちゃいけないって分かってるんだけど…………っ
「小町に紹介するな。
この人が俺の彼女の芽衣。」
「この人って何だからちょっと堅苦しいよ雪。
初めまして、浦巾 芽衣です。」
そう言ってお辞儀をする雪くんの彼女さん。
その子は私が思っていたイメージと違く、何だか『お姉さん』みたいなイメージ。
それから一時間後。
お母さんに買い物を頼まれた私は真っ赤な目のまま外に出た。
あの後、結局は家に帰って枯れるまで泣いた。
大丈夫、もう吹っ切れたんだから。
今も無理矢理そう言い聞かせている。
そうしてボーッと近くのスーパーに寄って言われたものを買ってきた。
野菜やお肉、ジュースやお菓子。
少し重たいエコバッグを持ってまた家に戻る。
後は戻るだけ。
だけど、少し休憩したくなった私は近くの公園まで歩いた。
ベンチに荷物を置いて座る。
「はぁ。」
行き場の無いため息をついた。
少し錆びているベンチは冷たい。
だけども、それより空気が暖かった。
「──────小町?」
そう呼ばれた瞬間、さっきまで暖かかった空気が一気に冷めていった。
この声──────。
分かってる。だけど振り向きたくない。
雪くんの顔を見ると、涙が出ちゃうから。
「あれ?小町だよな……?」
するのベンチに座っている私の顔を覗き込むようにして座った。
「やっぱ、小町じゃん!
俺って気付かなかった?あ、聞こえなかったのか。」
そう言う声色は普段と違って穏やかでなんだか弾むような感じだった。
「─────雪、その子は?」
雪くんの隣から聞こえた声。
あぁやっぱり。
誰も優しくて頼りになってカッコいい雪くんをフるはずない………っ
そう気付いてしまった私は胸がズキズキと痛んだ。
そして、枯れるまで泣いたのにまた、涙が出そうになった。
「俺の恩人。
告白を手伝ってくれたんだ………」
照れているのか声はだんだん小さくなっていった。
「………」
私はどうしようも出来ずに、ただ座っているだけの置物だった。
もはや、二人にとっては荷物なのかもしれない。
こんなこと考えちゃいけないって分かってるんだけど…………っ
「小町に紹介するな。
この人が俺の彼女の芽衣。」
「この人って何だからちょっと堅苦しいよ雪。
初めまして、浦巾 芽衣です。」
そう言ってお辞儀をする雪くんの彼女さん。
その子は私が思っていたイメージと違く、何だか『お姉さん』みたいなイメージ。