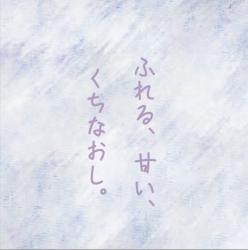だから雪くんがそんなこと思うことないのに。
私だって、非の打ち所はあった。
っていうか私にしか無かった。
こんな時、私が雪くんの彼女ならなぁ、なんて考えてしまう。
そうしたら今すぐ寝たフリなんてしないで雪くんの体に抱きつけるのに。
「ごめん。俺もう、帰るわ………
早く良くなって。
────待ってるから。」
そう残すと雪くんは私の部屋を出ていった。
バタン。
優しく閉められたドア。
私は雪くんが居なくなったのを感じると体を起こした。
あっという間だったなぁ。
時計を見てみると十分程経っている。
だけど私にとっては二分、三分位の一瞬。
ついさっきまで雪くんが居たすぐそこにはまだ面影を感じる。
雪くんの匂いが私の部屋いっぱいに広がっているんだ。
そんなこと考えると何だか嬉しいような嬉しくないような、そんな気持ちになった。
『────待ってるから。』
そんな言葉が私を惑わせる。
どうしよう。
さっきまで雪くんを忘れる、なんて思っていたのに。
そう決めてたのに。
胸の鼓動がだんだん早くなっていった。
やっぱり忘れられない。
温かい眼差しも、
柔らかい笑顔も、
優しい声も、
全部全部が私の頭に焼き付いて離れない。
諦めなきゃいけないって分かってるのに、
そんなの毎日毎日考えてるのに、
どうしても“好き”の思いに蓋が出来ないよ………っ
そうしてまた、静かに頬を濡らした。