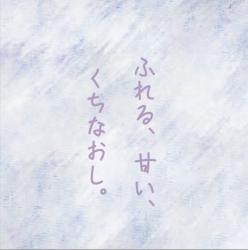冷たいような温かいような、そんな言い方。
だけど、私の手を掴んでいる雪くんの手はとても温かい。
「あり、がとう……っ」
私がそう言うと雪くんは手を引っ張って私を立ち上がらせてくれる。
「どーも。」
恥ずかしいのか、ちょっと顔が赤くなっている。
こうして、一つの傘に二人、私と雪くんが並んで歩いている。
「あの……追いかけてきて、くれたの?」
そこだけ、気になった私は雪くんに尋ねた。
「小町、俺に一言言ってから家出たでしょ?
その後、母さんが『雨なんだから小町ちゃんのこと、送ったら?』って。
それに小町は傘なんて持ってきてなかったし、きっとずぶ濡れだろうなって思って。」
「そっか。ありがとう。
お母さんにも言っておいてね。」
少しだけ、残念な気持ちがあった。
雪くんのお母さんに言われたから?
そう言ってしまいそうになってしまう。
そんなことも雨の音に紛れて消えちゃえばいいのにな。
「小町、寒くない?
上着、着る?」
今ではそんな優しさもただただ私の心が痛くなるだけだった。
優しくされると、余計好きになっちゃうよ。
でもいけない。
雪くんに気持ちを伝えちゃうと困るのは雪くんだもん。
だから───せめて卒業までは側に居させてね…………