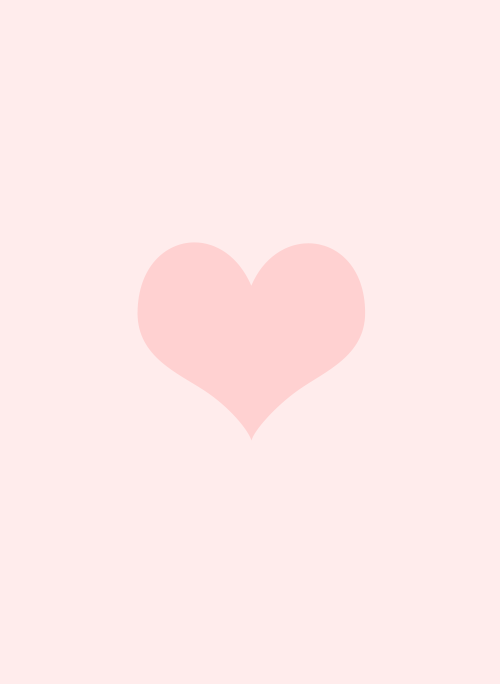勢いのままに着替えて、メイクして、カメラの前に立つ。
目が眩むほどのまぶしいライトの光と、周りの大人たちの視線が一気に私に注がれる。
心臓はドクドクとうるさい。
カメラテストのために、何度かシャッターがカシャン、カシャンときられる。
テストとはいえ、どう立っていればいいのかわからない。
「美鈴ちゃん」
横から声をかけられふと視線を上げると、楓君は私の隣でニヤニヤしている。
その意地悪そうな顔をにらみつける。
「そんな怖い顔しないで。カメラの前では笑顔」
「そう言われても……」
こんな状況で、どう笑えばいいのだろう。
心細さに目が自然と涼ちゃんの姿を探し始める。
涼ちゃんはスタジオの奥の方の壁にもたれかかって、こちらをじっと見ていた。
目が合っているはずなのに、涼ちゃんはにこりともしてくれない。
期待していた何かをあきらめるように、私は涼ちゃんから目をそらした。
「涼ちゃんのことが気になっちゃう感じ?」
楓君が再び隣から声をかけてきた。
「そりゃあ気になるよ。だって見てよ。明らかに怒ってる顔じゃん」
「え? いつもあんな感じじゃない?」
「違うよ。
涼ちゃんがあんな顔をするのは、私が相当大変な失敗をした時だけだよ。
それでもあんな鬼みたいな顔はしないよ」
「鬼って」と楓君は撮影用のすらっとした表情を崩さないように噴き出す。
「本当はすごく優しくて、気遣いができて、笑った顔も子供っぽくて、努力家で、まじめな人だよ。
ビターでダークな人じゃないんだよ」
「涼也のこと、よくわかってるんだね」
「一応、マネージャーだから。って言っても形だけだけど。代理だし。
こんなところでこんな服着て、こんなメイクして、ライトやカメラ向けられてへらへらしてちゃダメなのに」
「なんで?」
「え?」
「なんでへらへらしてちゃダメなの?」
「なんでって、私、マネージャーだもん。仕事中だよ」
「じゃあ、美鈴ちゃんは嬉しくないの?」
「え?」
「こういうかわいい服着て、かわいくメイクしてもらって、自分にライトが当てられて、かわいく撮ってもらえて。
こういう日常を離れた世界観の中にいるのって、わくわくしないの?」
「それは……」
正直、楓君の言っていることは、今の私にすべて当てはまった。
だけどそれを言ってしまったらいけないような気がした。
不謹慎というか。
だって私のせいで吉田さんは怪我をして、私はその代理でマネージャーをやっている。
しかもなんの役にも立っていない。
むしろ迷惑をかけている。
そんな私が、こんなところで浮かれているなんて知ったら、私に仕事を任せてくれている吉田さんを裏切る感じがするし、きっと涼ちゃんも……。
「すみません、姿見ってすぐに出ます?」
楓君がメイクさんに向かってそう言うと、キャスターのついた大きな姿見が私の目の前に持ってこられた。
「ほら、美鈴ちゃん、自分の姿をよく見てよ」
その言葉に従って、私はそっと目を上げた。
見慣れない自分の姿に、相変わらずドキドキする。
下に向かって裾がふんわりと広がっている、ドレスのような真っ白なひざ丈ワンピース。
メイクは普段涼ちゃんが仕事用にしてくれる大人っぽいメイクではなく、あえて幼さを前面に出しているメイク。
そして、空気が含まれてふんわりと気持ちよさそうな私のボブ。
姿見の中に、穏やかな表情の楓君が映り込んで、私の肩にそっと手を置いた。
「ほら、めちゃめちゃかわいいでしょ。あとは、背筋伸ばして、顎引いて。
これで、大丈夫。堂々としてたらいい」
「堂々となんて、できないよ。だって……」
私の視線は、また涼ちゃんをとらえる。
「あいつのことはほっとけば?」
「そういうわけには……」と言いかけたところで、顔が両手で挟まれて、ぐっと上に持ち上げられた。
とても甘ったるい表情の楓君が、私のすぐ目の前に現れた。
「あんなやつ、ほっとけよ」
「え?」
「今日は、俺のことだけ見てて」
その瞳が、優しく横にひかれ、口角が緩やかに上がる。
「では本番行きます」
その掛け声で撮影は始まった。