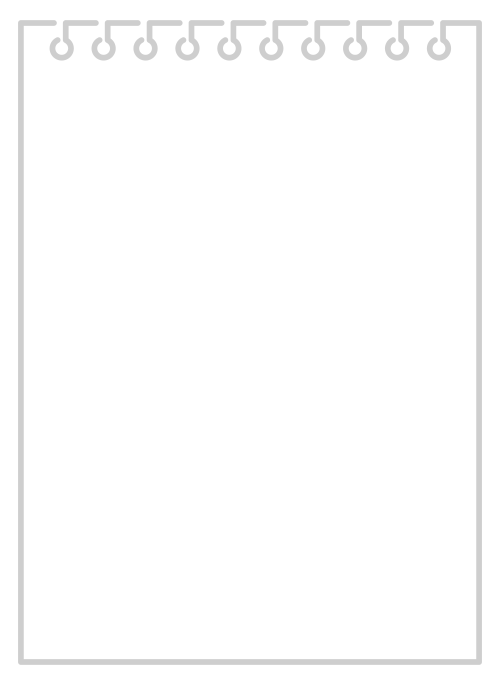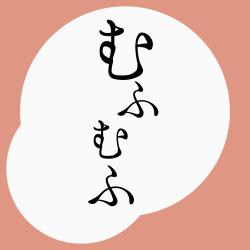「なんで剥がしたんですか」
急に話しかけてきたのは、知らない男だった。顔中に黒い塗料で奇妙な文様を描いており、頭には唐笠を被っている。
「気になったからじゃないのかな」
大滝は答えた。
「どうして他人事なんですか」
「おれが剥がしたんじゃないからね」
大滝はふうっと煙を吐き出した。
「なるほど」
奇妙な顔の男は腕組みをした。そして、言った。
「30万で貼り直しましょう」
「高いなあ。そんなに取られるなら自分でややりますからね。セロハンテープかなんかあったはずなんで」
やれやれ、わかってないな、と奇妙な男は言った。
「そんなことしたら効果がないどころか、何が出てくるかわかりませんよ。最悪死人が出ますよ」
「ほんとう? 剥がして何もないなら何もないんじゃないかなあ。ところで、おたくは誰なんですか」
「お祖父様の依頼で札を貼った者ですよ」
何者かの手によって札が剥がされた気配を感じ取って、駆け付けたのだという。
「そういうのわかるんですね」
「身体のどこかに、治りかけの瘡蓋を取るときの感じが来るのでわかります」
痛そうだな。と大滝は思った。
「自分のタイミングでやりたいので、勝手に剥がされるの結構嫌です。それはどうでもいいとして」
男はスタッフルームに入った。そこではストーブに当たっていた安見の全身が青く変色しており、泡を吹いて失神していた。