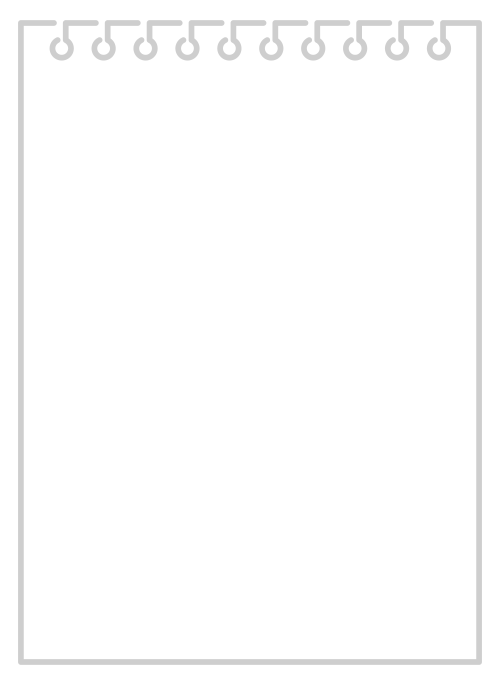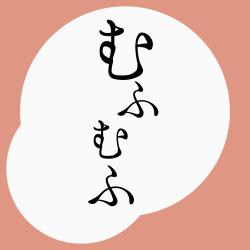安見は勤務中であるにも関わらず、缶ビールを開け始めた。プシュッという音が、大滝には悪魔の囁きのように聞こえた。
「こんな日があってもいいじゃないですか。さ、一杯」
「用意がいいやつだな。こんなことしていいと思ってんのか」
「我慢すると後悔しますよ」
「おいしいですよー!」
岩野はもはや肉とも呼べない黒い塊を含んだ口の中を見せびらかしながら言った。なんともグロテスクな映像だ。 大滝の意志はとうとう折れた。もちろん、岩野の口の中身を見てそそられたわけではない。
「ちくしょう。ちゃんと野菜も焼きなさい」
「毎度あり」
大滝はキャベツや玉ねぎを肉の横に整然と並べ始める。繊細な仕事ぶりだ。そして岩野はせっかく並べられた野菜を箸でつまんでは駐車場に捨てているのだった。
「やめろ、捨てるんじゃない」
大滝はせっかくの野菜を無駄にする岩野の腕を捕まえる。
「野菜はいらないです」
「食べたくないなら避けて肉だけ食べればいいだろうが」
「野菜の臭いがついてるじゃないですか」
「わがままなやっちゃな。食べてみろって。おれも野菜は特別好きじゃあないが、バーベキューの野菜なら意外と」
「いらない!!!!!!!」
ドサッと物音がした。