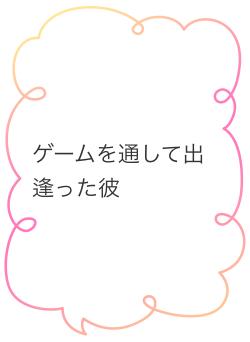「私でいいんですか?」
「違う。加恋ちゃんがいいの。」
「はい。」
「それって、OKってこと?」
「はい。」
「よかった。」
こんな嬉しいことはなかった。
私も、永遠くんが好きだって思っていた。
でも、永遠くんは、一緒に暮らしてても、何もしてこなかった。
だから、興味ないのだと思っていた。
「加恋。もう、俺、我慢しなくていい?」
「え?」
「ずっと、加恋に触れたくて仕方なかった。でも、触れたら、壊れちゃうんじゃないかって思って。」
『そんな風に想ってくれていたんだ。』
嬉しいかった。
「違う。加恋ちゃんがいいの。」
「はい。」
「それって、OKってこと?」
「はい。」
「よかった。」
こんな嬉しいことはなかった。
私も、永遠くんが好きだって思っていた。
でも、永遠くんは、一緒に暮らしてても、何もしてこなかった。
だから、興味ないのだと思っていた。
「加恋。もう、俺、我慢しなくていい?」
「え?」
「ずっと、加恋に触れたくて仕方なかった。でも、触れたら、壊れちゃうんじゃないかって思って。」
『そんな風に想ってくれていたんだ。』
嬉しいかった。