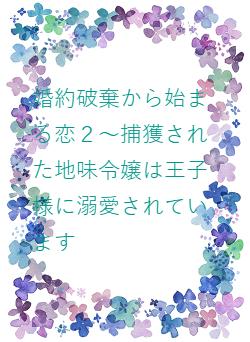「お嬢様、ランディーニ・ハイスター公爵様がいらっしゃいました」
「どうぞ、お通しして」
思ったより早かったわ。
しばらくしてドアが開いて、最初に目に飛び込んできたのは真っ赤な薔薇の花束。
「こんにちは。元気だったかな。僕の愛しい人」
大きな薔薇の花束の横から顔を出したのはランディーニ・ハイスター公爵。
わたしの婚約者。彼は王の甥で国王陛下の右腕として働いている公爵様。わたし自身も王族に近い地位にいるのですよ。
知らないということは怖いことですね。おバカさんたち。
「ええ、元気でしたわ。きれいな薔薇をありがとうございます」
花束を受け取ると薔薇の香りが鼻腔をくすぐる。甘い香りに先ほどのささくれだった心が癒されていくようですわ。あのおバカさんたちのことはあとで考えることにして、それよりも大事なことがありますからね。そちらを優先しましょう。
薔薇の美しさを愛でた後、部屋に飾ってもらうためにメイドに花束を渡した。
「どうしたんだい? 急用があると手紙をもらったけど」
「ええ、申し訳ありません。お忙しいのにお呼び立てして」
「忙しいけれど、婚約者殿ためならすぐにかけつけるよ」
ランディー様は嬉しいことを言ってくださいますわね。年齢が五才離れているのですけれど、子ども扱いはせずにわたしのことを尊重し大事にしてくれる。訪れるときは薔薇の花束を抱えて僕の愛しい人と言葉とともに渡してくださる紳士なお方。もちろんわたしもお慕いしていますわ。
ランディー様を椅子に座るように促すと、メイドたちがお茶の準備を始めた。その間に、先ほど書いた手紙を彼に見せた。
「どうぞ、お通しして」
思ったより早かったわ。
しばらくしてドアが開いて、最初に目に飛び込んできたのは真っ赤な薔薇の花束。
「こんにちは。元気だったかな。僕の愛しい人」
大きな薔薇の花束の横から顔を出したのはランディーニ・ハイスター公爵。
わたしの婚約者。彼は王の甥で国王陛下の右腕として働いている公爵様。わたし自身も王族に近い地位にいるのですよ。
知らないということは怖いことですね。おバカさんたち。
「ええ、元気でしたわ。きれいな薔薇をありがとうございます」
花束を受け取ると薔薇の香りが鼻腔をくすぐる。甘い香りに先ほどのささくれだった心が癒されていくようですわ。あのおバカさんたちのことはあとで考えることにして、それよりも大事なことがありますからね。そちらを優先しましょう。
薔薇の美しさを愛でた後、部屋に飾ってもらうためにメイドに花束を渡した。
「どうしたんだい? 急用があると手紙をもらったけど」
「ええ、申し訳ありません。お忙しいのにお呼び立てして」
「忙しいけれど、婚約者殿ためならすぐにかけつけるよ」
ランディー様は嬉しいことを言ってくださいますわね。年齢が五才離れているのですけれど、子ども扱いはせずにわたしのことを尊重し大事にしてくれる。訪れるときは薔薇の花束を抱えて僕の愛しい人と言葉とともに渡してくださる紳士なお方。もちろんわたしもお慕いしていますわ。
ランディー様を椅子に座るように促すと、メイドたちがお茶の準備を始めた。その間に、先ほど書いた手紙を彼に見せた。