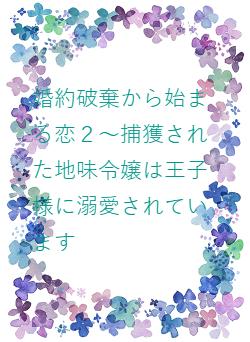「あら、祝福してくれるの? 侯爵夫人になり損ねちゃったのに? 心無い言葉なんて言わなくていいのよ。くやしいって、正直に言ってもあたし怒らないわよ。なんてたって未来の侯爵夫人ですもの」
ニヤニヤと勝ち誇ったように嗤っているリリア様。
私は侯爵夫人になりたかったわけではありません。もちろん、結婚したならば侯爵夫人としての義務も果たすつもりでしたけど。
「こいつに、侯爵夫人という大役が務まるはずないだろ。勉強ばっかりして部屋に閉じこもっているガリ勉女が社交なんかできるもんか」
「それもそうね。だからエドガーの両親も見切りをつけてあたしを選んだのよ。残念だったわね、フローラさん」
次々と二人から浴びせられる侮蔑の言葉に体が震えてきました。二人の顔が怖くてまともに見れません。
視界が霞んで気を失いかけた時、私の手に温かいぬくもりを感じました。不思議に思って見てみると、ディアナが私の手をぎゅっと握ってくれていました。おかげで正気を取り戻し徐々に心が落ち着いてきました。
「いい加減にしたらどうかしら? 一人の令嬢を寄ってたかっていじめるなんて。紳士淑女のふるまいではないわ」
ディアナがきっぱりと言ってくれました。
「なによ。伯爵令嬢風情が、次期侯爵と侯爵夫人にたてつくなんて」
リリア様は黙るどころか、さらに攻撃してきました。今度はディアナを睨みつけています。
ニヤニヤと勝ち誇ったように嗤っているリリア様。
私は侯爵夫人になりたかったわけではありません。もちろん、結婚したならば侯爵夫人としての義務も果たすつもりでしたけど。
「こいつに、侯爵夫人という大役が務まるはずないだろ。勉強ばっかりして部屋に閉じこもっているガリ勉女が社交なんかできるもんか」
「それもそうね。だからエドガーの両親も見切りをつけてあたしを選んだのよ。残念だったわね、フローラさん」
次々と二人から浴びせられる侮蔑の言葉に体が震えてきました。二人の顔が怖くてまともに見れません。
視界が霞んで気を失いかけた時、私の手に温かいぬくもりを感じました。不思議に思って見てみると、ディアナが私の手をぎゅっと握ってくれていました。おかげで正気を取り戻し徐々に心が落ち着いてきました。
「いい加減にしたらどうかしら? 一人の令嬢を寄ってたかっていじめるなんて。紳士淑女のふるまいではないわ」
ディアナがきっぱりと言ってくれました。
「なによ。伯爵令嬢風情が、次期侯爵と侯爵夫人にたてつくなんて」
リリア様は黙るどころか、さらに攻撃してきました。今度はディアナを睨みつけています。