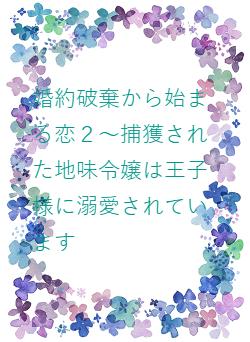相手が王子だからって、媚びることもないし馴れ馴れしく近づくこともない。好意を寄せていることくらいわかっているだろうに。それとも本当にわかっていないとか?
ローラなら、それもあり得るのか? だったら下手に自惚れないところもよいかもしれない。
「全然重くないから大丈夫。羽根みたいに軽いよ」
「羽根って、そんなわけありません。言い過ぎです。早く、下ろしてください。皆さん、見てますから、恥ずかしいです」
「あっ、そっち?」
俺たちの後ろには三人の護衛と侍従が一人ついてきている。王宮のプライベートな場所とは言えども一人で歩くことは許されない。人払いはできるけど完全に無人になることはないんだよ。
ごめんね、ローラ。
「彼らは空気だから、気にすることはないよ」
「空気ではありませんよ、人間です。だってその証拠に笑っていますもの」
ローラの声が湿り気を帯びてきた。
微かに震えて涙目で訴えている様子に、さすがにやりすぎたかと思って後ろを振り返ったと同時に
「プッ」
誰かが噴出した声が聞こえた。
よく見てみれば護衛の一人が口元を押さえていた。
リーダーのダン。
いつもは冷静沈着なヤツなのに声を出さないように口を覆っていても肩が揺れている。他の者たちも唇を噛みしめて笑いをこらえているようだった。
ローラなら、それもあり得るのか? だったら下手に自惚れないところもよいかもしれない。
「全然重くないから大丈夫。羽根みたいに軽いよ」
「羽根って、そんなわけありません。言い過ぎです。早く、下ろしてください。皆さん、見てますから、恥ずかしいです」
「あっ、そっち?」
俺たちの後ろには三人の護衛と侍従が一人ついてきている。王宮のプライベートな場所とは言えども一人で歩くことは許されない。人払いはできるけど完全に無人になることはないんだよ。
ごめんね、ローラ。
「彼らは空気だから、気にすることはないよ」
「空気ではありませんよ、人間です。だってその証拠に笑っていますもの」
ローラの声が湿り気を帯びてきた。
微かに震えて涙目で訴えている様子に、さすがにやりすぎたかと思って後ろを振り返ったと同時に
「プッ」
誰かが噴出した声が聞こえた。
よく見てみれば護衛の一人が口元を押さえていた。
リーダーのダン。
いつもは冷静沈着なヤツなのに声を出さないように口を覆っていても肩が揺れている。他の者たちも唇を噛みしめて笑いをこらえているようだった。