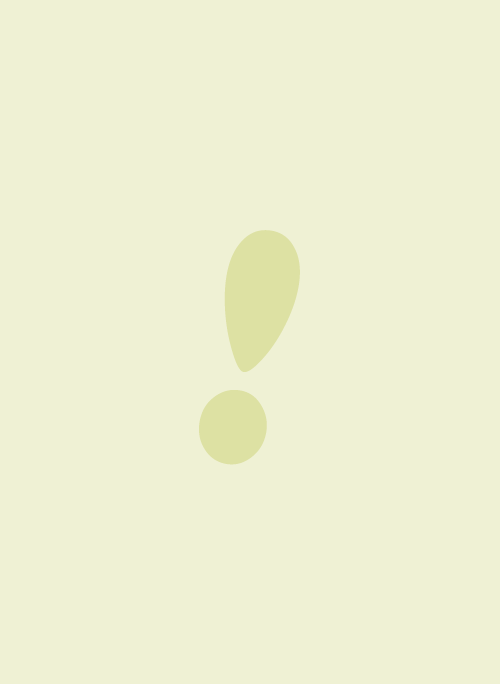その日、啓太は夢を見た。
ハッキリとは覚えていない。
一つ言えることは、どんよりした嫌な夢だ。
大切な物に手を伸ばすが届かない。そんな夢だった。
ハッと目が覚めると3歳の息子が啓太の上でゴロゴロしていた。
まるで大木にしがみつく猿のようだった。
「陸斗、おはよう。」
「パパ、起きたー!」
陸斗は嬉しそうに微笑んだ。
そのままパタパタと走り出し、母親の元へと行った。
おそらく「パパを起こしてきて!」と頼まれたのだろう。
言われてみれば、上でゴロゴロしていたのではなく、起こそうと奮闘していたのかもしれない。
啓太は重い頭と体をフラつかせリビングへと向かった。
妻は「おはよう!」と言って一杯の水を持ってきてくれた。
啓太は何も言わず水を飲み干す。
「ありがとう」この一言が言えなくなって何年が経つだろう。
家族であるべき理由を探し出したのはいつからだろう。
外で他の女を抱いて、平気で家族の元に帰るようになったのはいつからだろう。
啓太は朝食を済ませ部屋へと戻った。
数分後、玄関から「行ってきまーす!」と子供の元気な声が聞こえた。
「いってらっしゃい!」
子供と妻へ声だけで返した。
いってらっしゃいのキスはもう出来ない。
それは家族への冒涜だと思った。
ハッキリとは覚えていない。
一つ言えることは、どんよりした嫌な夢だ。
大切な物に手を伸ばすが届かない。そんな夢だった。
ハッと目が覚めると3歳の息子が啓太の上でゴロゴロしていた。
まるで大木にしがみつく猿のようだった。
「陸斗、おはよう。」
「パパ、起きたー!」
陸斗は嬉しそうに微笑んだ。
そのままパタパタと走り出し、母親の元へと行った。
おそらく「パパを起こしてきて!」と頼まれたのだろう。
言われてみれば、上でゴロゴロしていたのではなく、起こそうと奮闘していたのかもしれない。
啓太は重い頭と体をフラつかせリビングへと向かった。
妻は「おはよう!」と言って一杯の水を持ってきてくれた。
啓太は何も言わず水を飲み干す。
「ありがとう」この一言が言えなくなって何年が経つだろう。
家族であるべき理由を探し出したのはいつからだろう。
外で他の女を抱いて、平気で家族の元に帰るようになったのはいつからだろう。
啓太は朝食を済ませ部屋へと戻った。
数分後、玄関から「行ってきまーす!」と子供の元気な声が聞こえた。
「いってらっしゃい!」
子供と妻へ声だけで返した。
いってらっしゃいのキスはもう出来ない。
それは家族への冒涜だと思った。