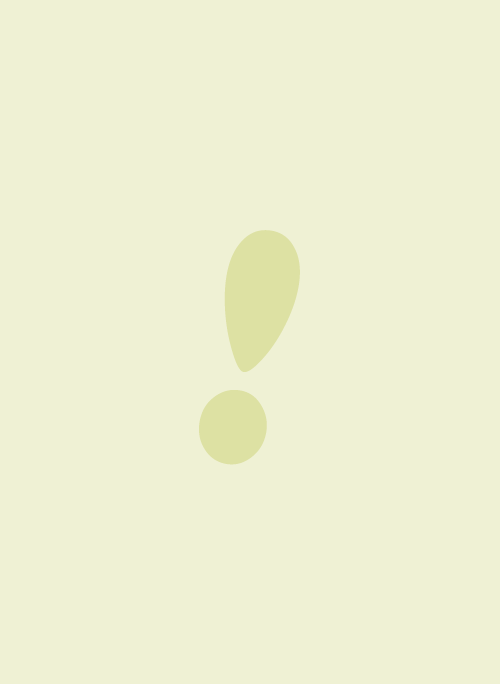「ただいま。」
家路についた時は既に深夜2時を回っていた。
スナックでバイトをしている愛人と会う日はいつもこの時間になる。
ダイニングにぼんやりオレンジ色の照明が灯されていた。
それはもう寝ている合図だった。
啓太は物音を立てないように注意をはらいながらキッチンに行った。
冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出し寝酒の水割りを作る。
ソファーに腰を掛けると、テーブルに手紙が置いてある事に気がついた。
“パパ、おしごとおつかれさま”
3歳になる息子からの手紙だった。
最近、字が書けるようになったと妻が誇らしげに言っていたのを思い出した。
「さすが私の子!」
妻はクイズ番組を見るたびに漢字の読み書きの問題には食い入るように取り組む。
漢検を持っている事を何度か自慢された。
啓太はその純粋な手紙を手に、心のモヤモヤを肴に水割りを飲み干した。
「人生ってなんなんだ、、、」
その感情に蓋をして子供が寝ている布団に潜り込んだ。
天使のような寝顔でスヤスヤと眠る息子にキスをしようとして止めた。
「おやすみ。」
家路についた時は既に深夜2時を回っていた。
スナックでバイトをしている愛人と会う日はいつもこの時間になる。
ダイニングにぼんやりオレンジ色の照明が灯されていた。
それはもう寝ている合図だった。
啓太は物音を立てないように注意をはらいながらキッチンに行った。
冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出し寝酒の水割りを作る。
ソファーに腰を掛けると、テーブルに手紙が置いてある事に気がついた。
“パパ、おしごとおつかれさま”
3歳になる息子からの手紙だった。
最近、字が書けるようになったと妻が誇らしげに言っていたのを思い出した。
「さすが私の子!」
妻はクイズ番組を見るたびに漢字の読み書きの問題には食い入るように取り組む。
漢検を持っている事を何度か自慢された。
啓太はその純粋な手紙を手に、心のモヤモヤを肴に水割りを飲み干した。
「人生ってなんなんだ、、、」
その感情に蓋をして子供が寝ている布団に潜り込んだ。
天使のような寝顔でスヤスヤと眠る息子にキスをしようとして止めた。
「おやすみ。」