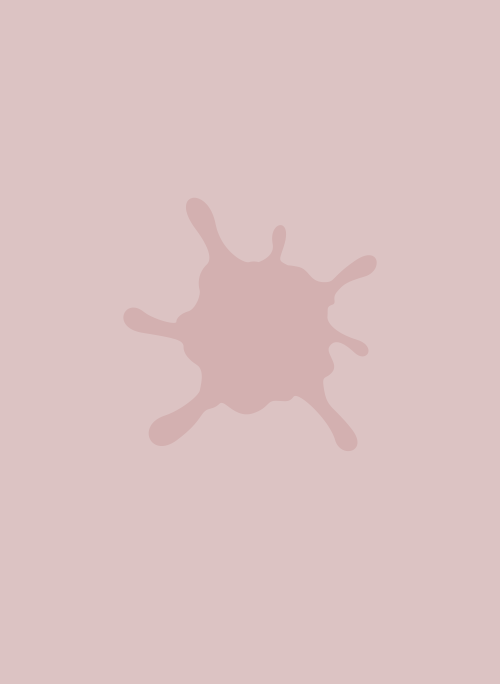先程も、かなりの速度で走ったつもりですが。
それでも、奏さんと車椅子を担いでいたので、どうしてもその分、速度が出ませんでした。
しかし、今は違います。
一瞬にして身軽になった私は、全速力でグラウンドを駆け抜けました。
一応通常モードのままなので、理論上、人間が出せる身体能力を越える速度は、出ていないはずですが。
それでも、素人の学生相手では、充分だったようで。
私は、次々と左右を走っている生徒をごぼう抜きにして、私の次に走ることになっているクラスメイトめがけて、走り抜けました。
何なら私の足が速過ぎて、次のクラスメイトがテイクオーバーゾーンに出てくるのが遅れていたくらいです。
何をやってるんですか。ちゃんと待っててくださいよ。
よく見たらあなた、さっき入場門に入るとき、奏さんに罵詈雑言を吐いていた男子生徒じゃありませんか。
これでもうあなたは、奏さんに罵詈雑言は吐けませんね。
「はい!」
と、私は言いながら、勢いのままにバトンをその男子生徒に手渡す…、
と言うか、叩きつけました。
「痛っ!」
と、男子生徒は言っていました。
ちょっと張り切り過ぎてしまったようです。
が、痛がっている暇があったら、早く走ってください。
散々奏さんを馬鹿にしたのだから、それなりの走りは見せてくれるのでしょうね。
ようやく我に返ったクラスメイトの男子生徒が、慌てて走り出したのを見て。
私は、全てをやり遂げた使命感でいっぱいでした。
依然として私は、唖然としている観客と生徒達には、全く気づいていませんでしたし。
「…恥ずかしい…」
と、真っ赤になった顔を両手で押さえている、奏さんにも気づいていませんでした。
それでも、奏さんと車椅子を担いでいたので、どうしてもその分、速度が出ませんでした。
しかし、今は違います。
一瞬にして身軽になった私は、全速力でグラウンドを駆け抜けました。
一応通常モードのままなので、理論上、人間が出せる身体能力を越える速度は、出ていないはずですが。
それでも、素人の学生相手では、充分だったようで。
私は、次々と左右を走っている生徒をごぼう抜きにして、私の次に走ることになっているクラスメイトめがけて、走り抜けました。
何なら私の足が速過ぎて、次のクラスメイトがテイクオーバーゾーンに出てくるのが遅れていたくらいです。
何をやってるんですか。ちゃんと待っててくださいよ。
よく見たらあなた、さっき入場門に入るとき、奏さんに罵詈雑言を吐いていた男子生徒じゃありませんか。
これでもうあなたは、奏さんに罵詈雑言は吐けませんね。
「はい!」
と、私は言いながら、勢いのままにバトンをその男子生徒に手渡す…、
と言うか、叩きつけました。
「痛っ!」
と、男子生徒は言っていました。
ちょっと張り切り過ぎてしまったようです。
が、痛がっている暇があったら、早く走ってください。
散々奏さんを馬鹿にしたのだから、それなりの走りは見せてくれるのでしょうね。
ようやく我に返ったクラスメイトの男子生徒が、慌てて走り出したのを見て。
私は、全てをやり遂げた使命感でいっぱいでした。
依然として私は、唖然としている観客と生徒達には、全く気づいていませんでしたし。
「…恥ずかしい…」
と、真っ赤になった顔を両手で押さえている、奏さんにも気づいていませんでした。