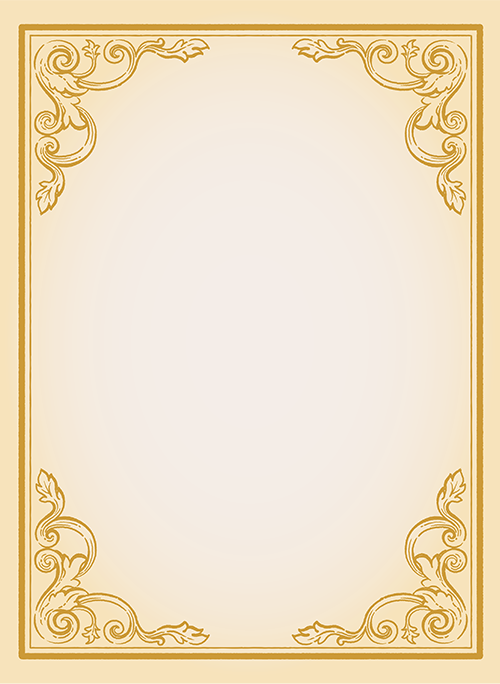「…こんなに…持ってきてくれたの…?」
テンションをあげてこんなものばかりを大まじめに持ってきた俺に対し、おとなしい煌野を見てなんだか恥ずかしくなった。
「ま、まあ煌野、何が好きかわかんないからさ…試そう、全部!」
「…ありがとう…」
煌野は前のときよりもさらに少しだけ笑ったような気がした。
そのあと煌野は飽きた様子も見せず、また夕方まで俺に付き合ってくれた。
煌野はたまになんだか目がキラキラ輝いている気がして、喜んでくれてるのかもしれないと思い嬉しくなった。
「けっこう遊んだこと無いんだな。ゲームはまた今度。…直に触るのが怖いなら、ゴム手袋を使うとか…?」
機械は怖いと言った煌野に、ゲームはハードルが高かったらしい。
「…どうして…どうして私にそんなにしてくれるの…?」
そう俺に尋ねた煌野は、なんだかとても申し訳なさそうに見える。
「え…」
なんでだろうと考えてみたけど、やっぱり答えは一つだった。
「煌野としゃべりたかったし、遊びたかったからだよ。…やっぱ、慣れなれしすぎた…?」
「ううん。…私、つまんないでしょう…?」
テンションをあげてこんなものばかりを大まじめに持ってきた俺に対し、おとなしい煌野を見てなんだか恥ずかしくなった。
「ま、まあ煌野、何が好きかわかんないからさ…試そう、全部!」
「…ありがとう…」
煌野は前のときよりもさらに少しだけ笑ったような気がした。
そのあと煌野は飽きた様子も見せず、また夕方まで俺に付き合ってくれた。
煌野はたまになんだか目がキラキラ輝いている気がして、喜んでくれてるのかもしれないと思い嬉しくなった。
「けっこう遊んだこと無いんだな。ゲームはまた今度。…直に触るのが怖いなら、ゴム手袋を使うとか…?」
機械は怖いと言った煌野に、ゲームはハードルが高かったらしい。
「…どうして…どうして私にそんなにしてくれるの…?」
そう俺に尋ねた煌野は、なんだかとても申し訳なさそうに見える。
「え…」
なんでだろうと考えてみたけど、やっぱり答えは一つだった。
「煌野としゃべりたかったし、遊びたかったからだよ。…やっぱ、慣れなれしすぎた…?」
「ううん。…私、つまんないでしょう…?」