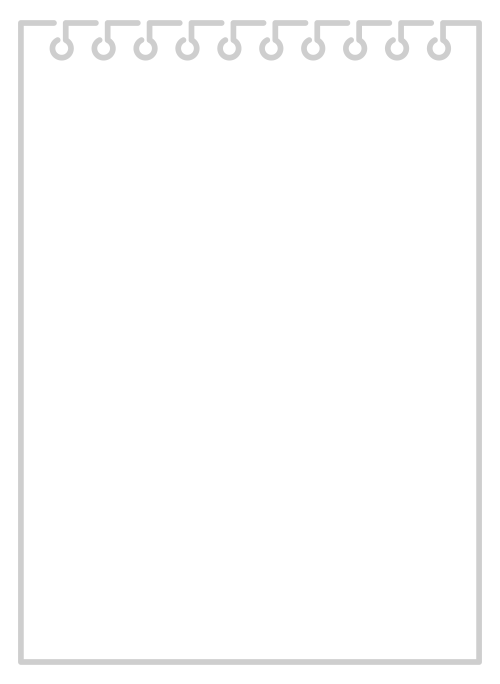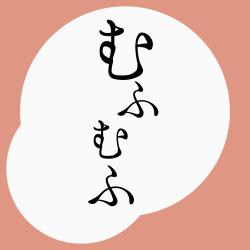気球を囲み、各々両手を翳す。
ライナルトが高く飛び、そして猫になって戻ってくることを、全員で祈る。ばかばかしいシチュエーションだが、みんなどこか真剣だった。最後までばかばかしいと思っていたジオを除けば。
かくして気球はゆっくりと浮上し始めた。生徒たちの額にじわりと汗が浮かぶ。
イリヤは唇をかたく結んだライナルトの表情を見た。そしてそれも、やがて遠のいて見えなくなる。
晴れていて、星が美しかった。空高く飛んだらいっそう綺麗に見えるだろう。イリヤは気球に乗った自分の姿を想像した。その想像の自分の隣に自然とジオを思い浮かべていることに気がついて、密かに顔を赤らめる。
シルフィはさすがに緊張した様子で、主人の行方を見守っていた。
そして。
おそらくここが限界だ、という高さにたどり着いた気球は、今度はゆっくりと下降し始めた。
中にいるライナルトはもう猫だろうか、それとも。
近づいてきた気球を見て、シルフィは安堵とも落胆ともつかない表情をした。
昇ったときと変わらない姿で気球を降りたライナルトは、「すみません。やっぱり無理だったみたいです」と悲しそうに笑った。
ジオはふう、と息を吐くと、「だろうね」と言い、くるりと背を向けてさっさと寮に戻ってしまった。