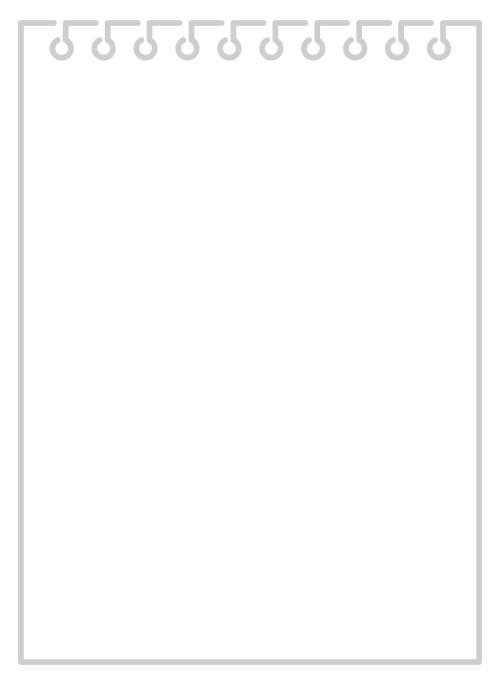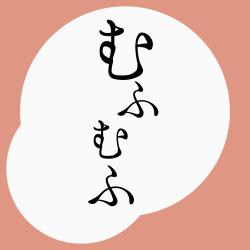「で、どうするつもりなのさ」
「どうする、といいますと……」
じりじり近づいてくるジオから、ライナルトはじりじり距離を取る。だが、ジオが壁に手をついて追い詰めた。怖い、壁ドンされた、とライナルトは怯えた。あれ、壁ドンって怖いんだっけ。
「わかるでしょ。人間になったあの子を受け入れるか、それともこれまで通り飼い主と猫で暮らすのか」
ライナルトはげほんと咳払いをしたが、今度はしゃっくりが出てきた。苦しいが、このまま話すしかない。
「シルフィには、猫のままでいてくれと伝えてあります……」
「ふーん、そうなんだ」
ジオは訊いたわりには興味なさそうに返事をする。
そんなジオに、ライナルトは言うつもりなどなかったのに、つい勢いで「僕が猫になれるならどれだけいいか」と口走ってしまう。
引かれたかな、と思ってジオを見たが、彼の表情は変わらなかった。
「おたく、猫になりたいんだ」
「そうなんですよ。シルフィが人間になって辛い思いをするくらいなら、その方がずっといい。なにしろ、人間社会なんてクソですから! むしろ僕は、猫になれたら最高ですよ!」
「……それ、本気で言ってる?」
ぶっちゃけ過ぎて今度こそ引かれただろうとライナルトは思った。しかし、言ってしまったものは仕方ない。
しかしジオはからかうでも非難するでもなく、なにか真剣に考えているようだった。