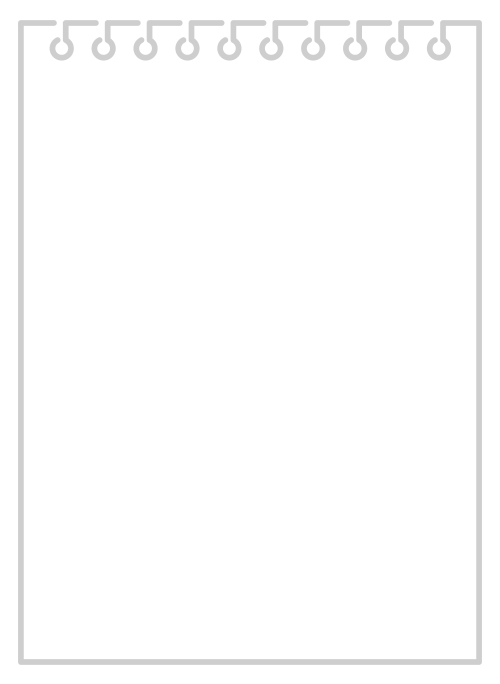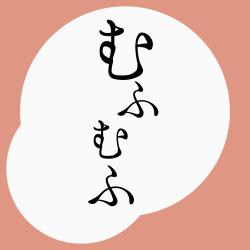「ジオルタのやつ、遅いな」
レンは眠っているイリヤに話しかけたが、当然返事はない。すぐに居場所を割り出してすっ飛んでくると思っていたのに、悠長なことだ。レンは舌打ちをした。
「ナメやがって」
アルバムのなか、いつだってジオルタはスカした表情をしている。いつも、いつも、いつも、いつもだ。
ひとり立ちした時だって、兄弟子たる自分になんの挨拶もなかった。タミヤから出て行ったと聞かされたのは、その直後のことだった。そもそもなんで弟弟子の方が先に独立できるんだ。意味がわからない。
ジオルタのことを思い出すたび、決まって彼の「バカ」という声が蘇った。ある時は舌ったらずな幼児の声で、ある時は声変わりを経たあとの声で。レンと呼ばれたことよりバカと呼ばれたことの方が間違いなく多い。
自分の出来が悪いのはよく分かっていた。兄弟子として教えてやるつもりが、勉強も魔術もすぐにジオルタに抜かれて、あっという間に教えられる側になっていた。
そして今。
どこにも働き口がなくて学校の手伝いをしているレンの目の前に、ジオルタはやって来た。レンにはなることの出来なかった、教える側の存在として。
ほかのページが汚れるのも厭わず、レンはアルバムを閉じた。
握り拳に力を込めると、電気の青い光が溢れ出してくる。
一度だけ。
どうせ自分の攻撃など、一度見ればジオルタは軽やかに躱してしまう。
一度だけ当てられれば、それでいい。