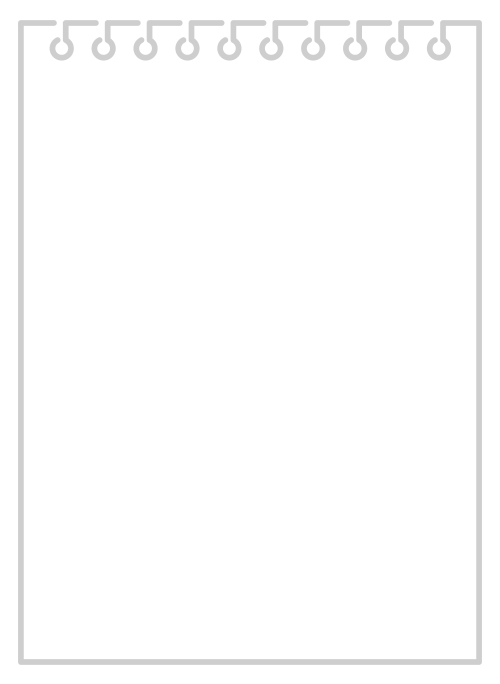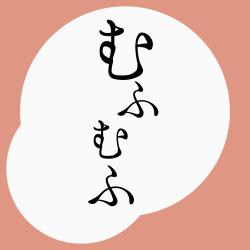レンブラントはきっぱりと言い切った。
「好きですよ。……家族、ですから」
家族だから。主人だから、の方が正確だ。
「そういう意味じゃねえ。お前、思ったより素直じゃねえな。ジオルタのしつけが悪いのか?」
ジオは悪く言わないでほしいーーと反論しようとしたが、それ以上に素直じゃないという言葉の意味を考えて、イリヤは沈黙するしかなかった。
ほらよ、とティーカップが置かれる。甘い匂いの湯気をわっと顔に浴びて、イリヤはくらくらした。ひと口飲んだだけで、強烈な眠気に襲われる。
「……わたしの気持ちなんて、どうでもいいじゃないれすか」
眠気で呂律が回らない。
「どうせ、わたしはただのーー」
唐突にイリヤの言葉は途切れて、うつ伏せに倒れた彼女の手が当たってカップが横倒しになる。開きっぱなしのアルバムにお茶がかかり、幼い二人の少年の写真を汚した。
「ずいぶん効きが早いな。がきんちょだからか」
レンブラントはお茶の効果ですやすや眠っているイリヤの向かいの席で頬杖をついた。
「でも良かったな、がきんちょーーもしかしたらジオルタの本音が、少しはわかるかも知れないぜ」