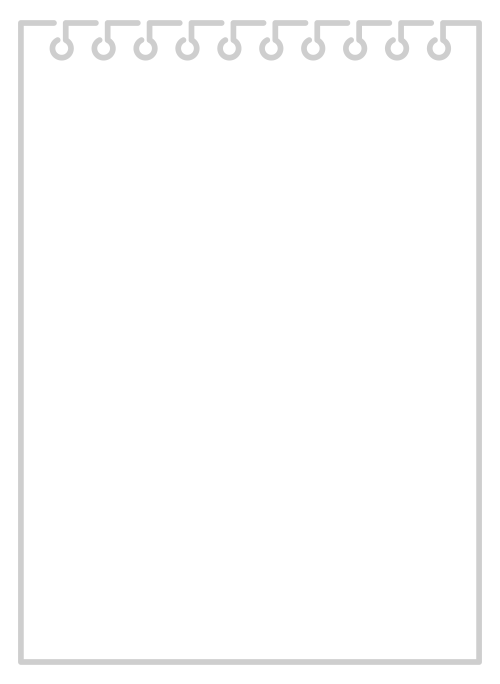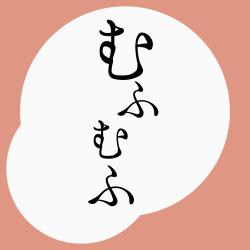「いや、交際していたかどうかはわかんないっすよ。密かに想いをしたためるぐらいですから、先生の片想いだった……という説も」
詳しく読み込んだわけではないのでわからないが、日記の最後の一ページーー十年前の日付、マリア、という名前と、その上からでたらめに引かれた黒い線のことをイリヤは思い出し、心臓が痛くなった。
「でも、昔の女のことでしょう。関係ないっすよ」
そうかな、とイリヤは思う。十四歳の少年だったジオにとって、それはどんな恋だったのだろう。もしかして、その人が初恋だろうか。
イリヤはビニールボールから空気がゆっくり抜けていくような長いため息をついた。ヒルデはこれは重傷だね、と言い、うなだれるイリヤの背中を撫でてあげる。
「イリヤちゃん、ジオ先生が大好きなんだね」
「うん」と、萎れながらイリヤは言った。「できれば、ずっと一緒にいたいよ」
あまりに素直に肯定の言葉に、ナターリアは驚きと興奮のあまり激しく咽せる。
しかし、続くイリヤの言葉はもっと切実だった。
「けど、もし、ジオに好きな人ができたら、わたしは邪魔になってしまう」