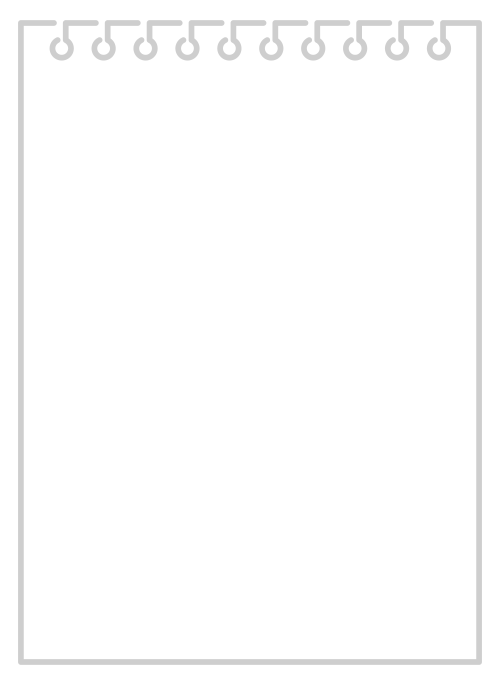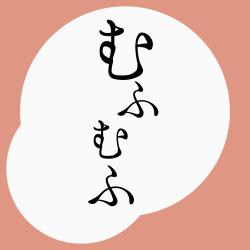いきなりそんなことを言われたイリヤは「何言ってるんですか!?」と結構な大声で言ってしまい、大いに慌てふためいた。
「ないですそんなの! ないない!」
「ほえー、そうなんですねぇ。そんな全力で否定したら、先生がお気の毒って感じですけど」
「そんなことないです! 畏れ多いですよ恋愛だなんてそんなの……」
イリヤは自分で恋愛などという単語を口にしてみて、改めて顔を真っ赤にする。
「そんなの、ジオさんに失礼じゃないですか!!!!」
わー、っとイリヤは勢いよく廊下を駆け出し、それを見咎めた爽やかな短髪の教師に「こらー、廊下は走るなー」と爽やかな口調で叱られる。
一人残されたナターリアは、「いやバリバリに恋愛の匂いでしたけどねぇ……」と鼻をすんすんさせた。あの様子だと先生の恋心の方が重たそうだ、と思う。
そして、ナターリアが自分のクラスに行くと。
まだ顔が赤いまま俯いているイリヤがいた。
「ども、イリヤさん。ウチら同じクラスなんですね。よろしくお願いしますね!」
「はっっっ」
イリヤはびくっと顔を上げ、怯えた目でナターリアを見た。これは面白いものが見られそうだーーと、ナターリアは思い、ししし、と笑った。