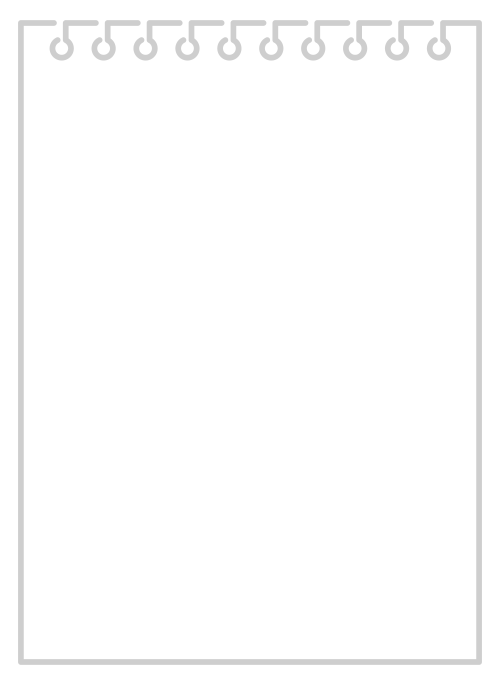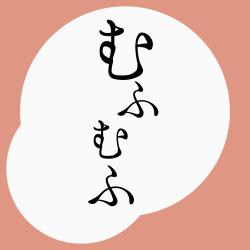「あの……ありがとうございます」
イリヤはかしこまって椅子に腰掛け、まずはお礼を言ってみた。
向かいに座っているこの人が、「根はいい子」なのだろうか。
足を組み、ふんぞり返ってこちらを睨みつける鋭い眼光に、いい人っぽさを見出す感性は今のイリヤにはなかった。イリヤは栄養不足で十歳という年齢のわりには小さな体をさらに縮こまらせた。
「あのさ」
男の不満げな声に、イリヤはすっかり青ざめる。大人の怒りはいくら受け止めても慣れるものではない。
「お茶、冷めるんだけど」
「え、あ……」
緊張のあまり、出されたお茶も見えていなかった。
「せっかく淹れたのに失礼なんじゃない」
「ごめんなさい……」
おそるおそるマグカップに口をつけてーー驚いて吐き出しそうになる。不思議なお茶だ。口の中で次々と味が変わる。よく見れば、色も少しずつ変化しているようだ。これは一体なんなのだろう。
「素早く飲んでよね。それ、冷めたらただの紅茶に戻っちゃうんだから」
イリヤは怖くて声も出せないままに、得体の知れないお茶を勢いよく飲み干した。
すると男はもっと不満げに、「一気に飲めなんて言ってないんだけど。味わわないなんて失礼すぎ」と言い始める。なにがなんだかわからなくなり、イリヤはやはり「ごめんなさい」と言うしかない。
孤児院の大人たちもみんなそうだった。何もしなければ怒るし、何もしなくても怒る。このひとたちは一体いつ笑うのだろうと、いつも不思議で仕方がなかった。
反抗する子はただ怒られるよりもずっと辛い目に遭う。ある秋の暮れ、下着姿で外に出されたことを思い出して、イリヤは身震いをした。
「お前、もしかして寒いの?」
不意に問われて、イリヤは滅相もないとばかりに首を振る。
「そうーー」
一瞬。
男は哀しげな目をしたように見えた。
「 」
唇がかすかに動く。何を言われたのかは聞き取れない。
そして彼は、今度ははっきりと言った。
「僕はジオ、君は今この瞬間を以って僕の下僕。わかったら、今日はもう寝ること」